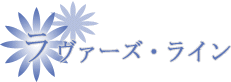 |
ある晴れた日の早朝。 歩道を走る制服姿の女子高生。 さらさらの黒髪。 背中の中ほどまであるそれが、風にさらされ、翻っている。 高校生としては童顔ぎみだが、十二分に美少女といって差し支えない。 背は155cm程度。ウエストは細く、スタイルはそれなりに良い。 息を切らせた彼女が、高級マンションの前に立ち止まり、中に入っていく。 エレベータに乗り込み、向った先はマンションの5階。502号室の前。 鞄から鍵を取出し、扉を開ける。 玄関に靴を脱ぎ、そのままキッチンへと入っていった。 棚から食器類を取り出し、手際良くコーヒーを入れる準備を始める。 挽いた豆とサイホンを用意。 その隣では水が沸き、湯気を上げる。 コポコポとお湯を注ぎ入れたサイホンからカップへと、茶色の液体が滴り落ちてゆく。 「ん、準備オッケ。」 満足そうに呟くと、少女はキッチンを出てリビングの先にある扉の前にぱたぱたと歩いて行った。 ノブに手を掛ける。鍵は掛かっていない。 ガチャリ。 躊躇無く、部屋のなかへと足を運ぶ。 部屋の中はベッドの他にはクローゼットとナイトテーブルがあるだけの簡素さ。 窓にはブラインドが下ろされ、薄暗い部屋の中央あるベッドには人がいる気配。 少女はそれを確認すると、ずんずんとそちらに向いだした。 「ゆーうきちゃーん。あっさだよぉ――。」 勢いをつけて、ベッドの上に少女の体が乗っかる。 ベッドの中から、うるさげに頭をもたげる男の姿。 やや眼つきは悪いものの、通った鼻筋に薄く引き締まった唇。 額に掛かる前髪を煩げに振り払う。 精悍な体つきに、整った顔立ち。 そしてその隣には、黒髪ロングの女の姿。 まず、目覚めた女が悲鳴をあげる。 「きゃっ!!……ちょっとあんた誰?!ゆうき、誰よこの子!?」 ベッドの上に起きあがった女は何も着けていない胸元にシーツを手繰り寄せ、少女と、隣でまだ横になっている男に詰問する。 「おはようございまーす。私、ゆうきちゃんの幼馴染、兼、目覚まし係の比呂平 華ですー。よろしくー。」 にこやかにベッドの上に乗ったままの少女が自己紹介する。 「……じょっ、冗談じゃないわよ。なにこの子……。勝手にはいってくるなんて……!!」 女が興奮ぎみに華に詰め寄ろうとする。その時、男の手が女の腕をつかみ、冷たい一瞥をなげかける。 「……かえれよ……、もう用は済んだだろ……」 女の頬が紅潮する。 男につかまれていない方の手で、男を払いのけ、ベッドの周辺に脱ぎ散らかしてあった服を拾い身に付け終わると、男の方を睨み付けた。 「もう二度と誘わないでよねっ。じゃあね。」 バタバタと玄関へと向かい、バタンッと思い切り扉をたたきつけるように閉め、早足で去って行く。 「ゆうきちゃん、また違う女の人だったの?私が起こしにきたとき、同じ女の人がいたことないよー?」 あまり関心がなさそうに、華はゆうきに問いかけ、再びキッチンに向かった。 ゆうきは、やっとベッドから起きあがり、華の後ろ姿に向け、聞こえないようにボソリと呟く。 「一晩限りの関係で、名前も聞かない女ばっかりだよ。」 *** 日中。 日が高く上り、初夏の日差しが白壁の校舎へと降り注ぐ。 昼を少しまわったばかりのこの時間、校内は学食や購買部に行く生徒達でざわめきあっている。 雑談が交わされる教室の中。一つの机を囲んで、華は二人の友人とお弁当を食べていた。 「華、あんた今日も例の幼馴染のとこにいってきたの?」 華の左前にいるショートカットの大柄な少女がパンを口に運びながら、華に尋ねた。 「ん、昨日ケータイにメールが入ったの。今日は朝から仕事なんだって。」 華の右前に座っている髪をアップにした顔立ちのはっきりした少女が驚いたように目を見開く。 「えーっ、華ってばまだやってたの?目覚まし係。その幼馴染って大学卒業してすぐマンションに引っ越したんでしょ?もうご近所さんじゃないのによくやるねー。」 華が箸を止め、苦笑しながら返事をする。 「そうかなぁ。でもね、早紀ちゃん、どうせ学校にくる通り道だしー。」 早紀と呼ばれた少女は今一つ納得しかねる顔で、隣の少女に問い掛ける。 「でも、もう引っ越して4年だっけ?その人今26歳でしょー?華と10歳違いじゃない。彼女とかいるんじゃないの?どう思う、あゆ?」 ショートカットの少女、あゆは困ったように笑いながら華に向き直る。 「そうね、どうだろ。でもさ、華にはもう一人いるじゃない?幼馴染。うちの優秀な生徒会長様の叶さん。彼女がいるってうわさ聞かないけど、どうなの?」 華が不思議そうに首をかしげた。 「奏のこと?……うーん、私も奏の彼女はみたことないなぁ。そういう話し、しないしぃ……。」 言いよどんでいる華に、あゆと早紀がじれったそうに口を挟んだ。 「あー、そうじゃなくてぇ!華がその彼女じゃないかってことよっ。」 ぐっ、ゴホっ。食べていた茶巾包みが華ののどにつかえた。 「……奏とは、そーゆう関係じゃないってば……。」 えーっ、と二人は声をあげ、なーんだと当てが外れたような顔をした。 「あのね……。」 あきれたように溜息をつき、これ以上詮索されないうちにとばかりに華はお弁当を黙々と食べ始めた。 「華、今日もゆうきのところにいったのか?」 放課後。帰り支度を整え教室をでたところで、華は声を掛けられた。銀縁眼がねを掛けた長身。やや茶色がかった髪が光りに透けると金に見える。 華のもう一人の幼馴染、華より二学年上の叶(かのう) 奏(かなで)である。 「うん。朝寄ってきた。これからコーヒー豆買ってからもう一度よってくるね。朝みたらもう切れてたから。」 華がやわらかく微笑む。 「あんまり遅くなるなよ。」 奏が心配そうに眼を翳らせた。 「大丈夫。それに今日は母さん、出張でいないし。適当に外でご飯食べてくるから。」 そういうと華は元気に駆け出す。その後ろ姿を奏は不安そうに見守っていた。 *** 「あー、やっぱりゆうきちゃん帰ってないかぁ。」 ゆうきのマンション。片手に紙袋、もう片方には鞄。華は鍵を開けるとリビングへ荷物を置きに行った。 時間は18:30を少し回ったところ。案の定ゆうきは帰ってきていない。 しかたないので、リビングのソファに腰掛け、テレビをつける。特にゆうきに用があるわけではないが、一応帰りを待ってみることにした。 明日は休日なので多少おそくなっても支障はない。 コーヒーと一緒に買ってきた調理パンと烏龍茶をテーブルに並べ、夕食をとった後、ぼんやりテレビを眺めているうちに、華はソファで寝こんでしまった。 ガチャンッ。ドタ。 不意の物音で華は目覚めた。 「……寝ちゃってたんだ……。ゆうきちゃんかな?」 ソファから起きあがり、眼を擦りながら玄関に足を向けた。 「ゆうきちゃん……?」 玄関の床に黒い影が見えた。ゆうきが床に倒れこんでいる。 「えっ、やだ。ゆうきちゃんどうしたの?」 華がゆうきを起こそうと、腕を抱えあげる。鼻腔をつくアルコールの匂いがした。 「……お酒飲んできた?もしかして、酔ってる?」 恐る恐るゆうきの顔を覗き込みながら華は一応確認してみた。返答がない。 影になったゆうきの顔からは表情が読取れなかった。 「今、お水持ってくる。ちょっと待っててね。」 華がキッチンに向かおうとしたその時、ゆうきの腕が華の腕を引き止めた。 バランスを崩し、玄関の上がり口に華が倒れこむ。 「……いったーーー……」 頭を押さえて起きあがろうとした華の背後にゆうきが覆い被さってくる。 「……ゆうき、ちゃん……?」 背後を振向き、ゆうきと目が、あった。 ゆうきの手が華を仰向きにさせ、その華奢な肩を床に押し付ける。 「やっ、なに、ゆ……んっ」 華の唇をゆうきのそれが塞ぐ。 ゆうきの胸を押し返そうと華の腕に力が込められる。 しかし、びくともしなかった。 しかもさっき倒れこんだ反動でスカートが捲れ、華の足はほぼ露出している。 その上をゆうきの手が滑る。 「いやぁ、やだぁ、ゆうきちゃ……」 顔をそむけた華の首筋にゆうきの唇が這う。 ゆうきの真意がつかめず、突然の行為に混乱した華の目尻に僅かに涙が滲む。 ベストのボタンが外され、シャツのリボンがほどかれる。 スカートから引きぬかれたシャツの裾からゆうきの手が入り、直に華の背中に触てきた。 華の身体がびくりと強張る。 ピン、ポーン。 突然、チャイムが鳴った。ゆうきの動きが止まる。 「ゆうき、いるんですか?華、きてませんか?まだ帰ってないんですよ。……ゆうき?」 インターホン越しに僅かにノイズの混じった音。 奏の声であった。 奏の手がノブに掛けられたらしく、がちゃりと回った。 鍵のかけられていなかったドアが、ゆっくりと開いていく。 ドア越しに現れた奏の姿が泣き濡れた華の目に映る。 「……華?」 ゆうきに組み敷かれた華の姿を目にし、奏の表情が凍りつく。 そして一瞬後には、ゆうきを華から引き剥がしていた。奏の腕が華を抱え込む。 「なにやってんだよっ、ゆうきっ!!」 激しく詰問する奏。 だが、ゆうきからの弁解は、ない。奏に背を向け床に座り込んでいる。 「……さいっていだな。華、帰るぞ。」 侮蔑した視線をゆうきに向け、震える華を支えるようにして奏が踵をかえした。 勢いよく玄関の扉が閉ざされる。 「なにやってんだよ、俺は……」 虚空に向かって、にがにがしげにゆうきは吐きだした。 *** 華の家の門前。 華を送り届け、隣にある自宅に向けて奏が歩き出そうとしたとき、震える華の手が奏のシャツを僅かに引いた。 「どうした?」 奏が華を見つめる。 既に華の着衣に乱れはなかった。 僅かに赤くなった目元がその痕跡を残すのみである。 奏の視線が痛々しげに細められる。 うつむいたままの華が口を開いた。 「……あのね、ゆうきちゃん、お酒飲んでたの。……だからきっと、さっきのこと、明日になればおぼえてないよ……」 奏の眉が僅かに上がる。 「酔ってた?ゆうきが?」 こくりと華がうなずく。 そしてやっと顔を上げ、真っ直ぐに奏を見つめた。 「だからお願い。ゆうきちゃんにはなにも言わないで。そうすればきっと、いままで通りだから……」 奏が華の顔をじっとうかがう。そしてしばらくしてから華に問い返した。 「本当に、それでいいんだな。」 再び華が頷く。奏は深く溜息をつくと、わかった、とだけ言い残し帰っていった。 華は、奏の姿が隣家に消えるまでその場でぼんやりと見送り、 「だって、私は。……ゆうきちゃんにとって、対象外、だもの……」 と呟くと、とぼとぼとした足取りで自宅へと入っていった。 *** それから6日後、木曜の夜にゆうきから華の携帯にメッセージが入った。 『明日、朝、仕事。起こしに来てくれ』 迷った末、華は奏には告げずにいくことにした。 たぶん奏はひとりでいかせてくれないだろうし、奏が一緒にいったりしたらゆうきが不信に思うかもしれないと考えたからだった。 それにたぶん、また女の人が、いる。 あれは、ゆうきちゃんがお酒に酔ってた、だけ。 でなきゃ、私にあんなこと……するはずが、ない。 華は携帯の簡素なメッセージを眺めながら、4年前の出来事を思い出していた。 ゆうきの家に横付けされた大きなトラック。 わいわいと騒がしい数人の男女。皆、大学で知り合った友達だと華はゆうきから聞いていた。 突然決まったゆうきの引越し。 社会人になるから、オレもそろそろ親元を離れないとな。 軽い口調で言われたその一言で、ゆうきは華の傍から簡単にいなくなってしまう。 それが華は悔しくて、最後までゆうきにだだを捏ねていた。 「華、わがまま言ってゆうきを困らせちゃ、だめだよ。」そう、奏に諭されたのは引越しの三日前だったろうか。 憮然としながらも、華は承諾するしか、なかった。 もともと華にゆうきを止める資格などない。幾らゆうきを好きでも、華はゆうきからみればまだまだ子供なのだ。 そう。華は、ゆうきに恋心を抱いて、いた。 もっと大人になったら、ゆうきちゃんにちゃんとした女の子として見てもらえる? 自宅の門柱に凭れながら、華はぼんやりとゆうきの家を見つめていた。 ゆうきは今日、ゆうきの父親が所有している不動産の一つであるマンションへと移っていく。 ゆうきの父親は都内にいくつか両親から譲り受けた不動産を抱えているのだ。 「あら。あなたゆうきくん家のお隣の子?」 不意に、声をかけられた。華やかな女性の明るい声。 驚いてゆうきの家とは反対方向へと振り向く。 そこには、背中の真ん中程度まであるさらさらの黒髪を一本に結わえた目鼻立ちのはっきりとしたキレイな女の人がいた。 両手には買い込んできたのであろうスナック菓子と飲み物の詰まったビニール袋を抱えている。 華が驚いて無言でいると、その女性は袋からがさりとスナック菓子の袋を一つつまみ出し、ハイ、と華に手渡してきた。 「あ、ありがとうございます。」 さしだされたその勢いに押され、思わず華は受け取ってしまう。 「どういたしまして。」 お礼をいった華に目の前の女性がにこやかに微笑む。 「白里、何してんだ?」 ゆうきの声が、華の背後からかけられたのはその時だった。 「かわいいお隣さんとお話。」 華を通り越し、白里と呼ばれた女性の視線はゆうきへと向けられる。 だが、華は背後を振り返ることなく、振り向かなくても判るゆうきの声をじっと聞いていた。 「白里、みんな待っているぞ。先、入っててくれ。」 ざっざと大股にこちらへと向ってきているのであろうゆうきの足音に耳を済ませながら、華がむっとした表情を作る。 奏に諭されたとはいえ、華は完全に納得しているわけでは、もちろんなかった。 そんな華の横を白里と呼ばれた女性が「じゃ、バイバイ」と手を振りながら軽やかに通り過ぎていった。 「華、こっちを向いて。」 華の背後まできていたゆうきの手が、華の髪を一房手に取り軽く引っ張る。 「……向かない、もん。」 出来るだけ不機嫌に聞こえる声で華は答える。 子供っぽい態度だとは思っても、今の華にできるささやかな抵抗だった。 「はーな。」 軽い溜息と共に吐き出されたゆうきの呼ぶ声に、華の心臓が跳ねる。 ――呆れられた? 両手できつく胸元を握り締め、強く唇をかんで俯く。 華の中に後悔が、生まれた。 「あのな、これ新しい住所と地図。ここからそんなに離れてないから。」 華の顔の横からゆうきの手が差し出される。 思ってもいなかったゆうきの言葉に華がぱっと後ろを振り向いた。 「……いっても、いいの?」 差し出されたメモをしっかり掴み、華が聞き返す。 「いつでも、どーぞ。というか。できれば、朝起こしにきてくれると助かるんだけど?」 わずかに苦笑しているゆうき。その言葉に、うれしさのあまり相好を崩す華。 内心、ゆうきの新居を訪ねるのは迷惑がられるのでは思っていた華にとって、それは信じられないくらい嬉しい言葉だった。現金なもので、その途端、華の機嫌が急上昇する。 「うん。絶対、絶対いくから!」 満面の笑顔で答える華。その様子を苦笑しながら見つめるゆうき。 その時まで、たしかに華はゆうきに女の子としてみてもらえる未来を夢見て、いた。 華がその会話を聞いたのはまったくの偶然だった。 姿の見えなくなったゆうきを探して、ゆうきの家の裏に回りこんだところで、話し声がしたのだ。 「ねえ、ゆうきくん。そうなんでしょ?華ちゃん、かわいいもんねぇ。」 自然に華の足が止まった。盗み聞きなんて、よくない。そうは思っても、どうしても華はその場を動くことができなかった。 聞こえてきた声は、先ほど聞いた声より幾分粘着質ではあるものの白里という女性。 そして、それに答えた声は。ゆうき、だった。 「なんのことだ?華は妹みたいなもんだよ。妹を女として見ることなんてありえないだろ。……対象外だ。」 対象外。その言葉に華が、固まる。 ――対象、外?……私は、絶対にゆうきちゃんに女の子としては、見てもらえない、の? 涙すら、出てこなかった。 華が普段聞いているよりも幾分低い声で告げられたゆうきの言葉。 それは華の中にあった恋心を完全に否定するものだった。 そして。華はゆうきに思いを告げて現在の関係を壊すよりも、妹して傍にいることを、選んだ。 ……女の子としてみてもらえないなら。せめて、妹としてでも構わないから傍に、いたい。 *** ゆうきからのメールが入った翌日。 曇天の中を華はゆうきのマンションに向けて走っていた。 いつものように高級マンションの前に立ち止まり中に入っていく。 マンションの5階。502号室の前。鞄から鍵を取出し、扉を開ける。 そしていつもの様にコーヒーを用意し、リビングの先にある扉の前に行く。 ノブに手を掛ける。鍵は掛かっていない。ガチャリ。躊躇無く、部屋のなかへと足を運ぶ。 窓にはブラインドが下ろされ、部屋の中央にベッドが配置されている。 「ゆーうきちゃーん。あっさだよぉ――――。」 勢いをつけて、ベッドの上に少女の体が乗っかる。 そこにはいつものように、ゆうきの姿。 だが、その隣に女性の姿は、なかった。 「あ……れ……?ゆうきちゃーん、女の人、帰っちゃったの?」 不機嫌そうにのっそりとゆうきがベッドに起きあがる。 わずらわしそうに前髪を押し上げ、目の前にいる華の顔を見る。 「きてない。」 華の眼が見開かれる。 今までゆうきに呼ばれて起こしにきた朝には、必ず側に女性が寝ていたのだ。 そのまましばらく無言でいると、ゆうきがベッドから足をおろした。 「まだ、時間あるんだろ?コーヒー付合えよ。」 半ば強制的にリビングのソファに座らせた華と、ゆうきは向かい合ってコーヒーをのんでいた。 だいたいにおいて朝のゆうきは機嫌が悪いが、今日も例外ではなく、極端に口数は少なかったが、それでもとりあえず、華の努力により会話らしきものが成立していた。 が、そろそろ学校の始業時間が迫っているらしく、華がそわそわとしだしている。 「あの、ゆうきちゃん、わたしそろそろ行かなくちゃなの。ごめんね。先行くね。」 始業時間に促され、とうとう華が席を立ちかけたその時。 ゆうきは不意打ちのように華に問いかけていた。 「このコーヒー豆、いつ持ってきたんだ?」 一瞬、華の動きが止まる。だが、すぐに笑顔を浮かべ、返事をしてくる。 「こないだ。ゆうきちゃんがいないとき、だよ。なんで?」 ゆうきが口元に僅かに笑みを刷いた。 朝、何事も無かったように現れたときから予想していたが、華が、ゆうきの行為を無かったことにしようとしているのが確実となる。 そんなこと、させるわけ、ないだろ? 一度堰をきった思いをいまさら無かったことにされるなんて冗談じゃ、ない。 ゆうきが心の中で苦く呟く。 この間、ゆうきが華を押し倒したのは、酒に酔っていたからなんかではなかった。 いつまでたっても自分のことを男としてみようとしない華に苛立ち、ゆうきの我慢が限界を迎えたのだ。 奏がこなければ確実に華を抱いてたと、ゆうきが思う。 そして、いつでも華の傍で、華を守ろうとする奏をうらやましく思っている。 奏が華のことを女として見ていることになんてとっくに気づいていた。 でも、渡すつもりなど、針の先ほどもゆうきにはなかった。 「俺がいないとき?……違うだろ?俺が帰ってきたとき、華、いたよな。」 今度こそ、華の動きが止まった。不自然な動きでゆうきのほうへ顔をむける。 「ゆうきちゃん、おぼえて……?」 ゆうきの顔に苦笑が浮かぶ。ゆっくりとソファから立ちあがり、華に近づいていく。 「俺は、酒を飲んで前後不覚になったことは一度もないよ。」 華の足が後退りしようとする。しかし、ゆうきの手がそっと華の腕を捕らえた。 「華、おまえが、欲しい。……意味、わかるよな?」 ゆうきの眼差しに捕らえられた華は困惑も顕にゆうきを振り仰いでくる。 「あ、の、だって幼馴染でしょう?わたしはゆうきちゃんにとって女じゃない、よね?」 おろおろと見つめてくる華の様子を見守りながら、ゆうきは上体をゆっくりと傾むけた。 華にとっては二度目の口付け。今度はきつく華の華奢な身体を抱きしめる。 「女、だよ。6年前からずっと。」 切なげにゆうきが華の耳元でささやく。 だが、その言葉に。明らかに華の身体が強張った。 「……華?」 「う、そ……嘘、だよ。……そんなの……どうしてぇ……、どうして、そんなこというのぉ」 ゆうきが抱きしめている細い体も、声も、震えていた。 必死に紡がれる言葉の中に微かに嗚咽が混ざる。 「……だって、ゆうきちゃん。云ったじゃない。私は……妹、だって。全然、対象外だって……。」 ゆうきの目が驚きに見開かれた。 華はゆうきの肩に頭をつけ、本格的に泣き出している。 しばらくそのままの体勢で佇む二人。ややしてゆうきが軽い溜息を、ついた。 その台詞には、覚えがあった。今のマンションに引っ越した日。 手伝いにきた女友達に華との関係を問われ、ゆうきは確かにそう答えたのだ。 「……あの時、聞いてたのか。」 ゆうきの言葉に、華がこくりと頷く。 きつく抱きしめていた腕を緩め、華の顔が見えるようにゆうきはそっと体を離した。 「そうか。言い訳は、しないよ。確かに、そういった。」 華の目が苦しげに伏せられる。 「じゃあ。私は、やっぱりゆうきちゃんにとって対象外、なんでしょう?」 「違う。そうじゃ、ない。」 「何が、違うの!?」 華がぱっと顔を上げる。はらはらと頬を流れ落ちる透明な涙。 まっすぐに見つめてくる激情を孕んだ眼差し。 ゆうきは思わず見蕩れていた。 「……ゆうき、ちゃん?」 無言のまま見つめてくるゆうきに、ややして華が訝しげな声を掛ける。 ゆうきがはっとしたように、苦笑を浮かべた。 「――これでも、随分悩んだんだ、よ。」 「?」 ぽつりと呟かれた言葉。話の方向性が見えずに華がやや首を傾げる。 「あの時。お前、まだ十二歳だったんだぞ?ランドセル背負って小学校にいってるような年齢の子供に欲情する成人の男を世間一般ではなんて言うと、思う?」 「――ロリコン?」 僅かに逡巡した後、真剣な表情で答えた華に、ゆうきが噴出した。 「そう。ロリコン。あの時いた女、あいつにもそう、言われた。」 「え?」 「女って、そういうことに聡いよな。お前を見てるオレの様子で、気づかれたらしい。」 なおもおかしそうに笑うゆうき。その話の内容に戸惑う華。 「で、華の聞いた会話に、繋がる、と。」 「――あ、そう、か。」 こっそりと華とゆうきのやり取りを伺っていた女、白里だったか。 華の機嫌を直して戻ったとき、やけに意味ありげな視線を投げてきた女の顔を忌々しげにゆうきが思い出す。 そう。だから、華の聞いたゆうきのあの台詞、は。彼女に問い詰められて、ゆうきが仕方なく吐いた言葉だった。 「本人にも告げてない思いを、わざわざあの女に正直に教えてやる必要なんて、ないだろ。」 無言のままゆうきの言葉に聞き入っている華。まだ目が潤んでいるが、どうやら涙は止まったらしい。 ゆうきの指が目と頬に残っている涙の痕跡をたどりながら華の顔の上を滑っていく。 「……じゃ、あ。私、妹じゃ、ない……の?」 そっと。小さな小さな声で、華がようやく呟いた。 華が、ゆうきの顔を食い入るように見据えてくる。 「いまさら、妹でいたいなんていわれても困る、な。」 再び苦笑しながらゆうきが言うと、華の眼からまた涙が流れ落ちた。 「華?」 泣き出した華の真意がつかめず、ゆうきがやさしく華の名を呼ぶ。 はらはらと涙を流しながら、華がにっこりと微笑んだ。 「……ゆうきちゃんが、スキ。ずっと、ずっと……スキだった。」 華の思いがけない、告白。 ゆうきの指が華の涙をふき取り、そのまま、強引に引き寄せると奪うように深く口付けた。 抵抗せず、ゆうきを受け入れる華。 ゆうきの中に甘い歓喜が広がる。長年の思いが一気にあふれ出すのを感じた。 「華、愛してるよ。」 ゆうきがささやく。華の両腕がゆうきの背中に回され、二人はきつく抱きしめあった。 *** 「華……、ちょっと……限界っぽいんだが……」 ゆうきからの思いがけない言葉を聞けた幸福感に浸かっていた華の耳元で、不意にゆうきがささやいた。 なんのことだか判らず、華は顔をうずめていたゆうきの胸から視線を上に向ける。 そこには、やや困ったような表情を浮かべたゆうき。 「?」 ゆうきを見上げる華をみて、ゆうきが溜息をつきながら天を振り仰いだ。 「さっき、華が欲しいって、オレいったよ、な?」 確認するように、ゆうきが先程華へと告げた台詞を再度呟いた。 「!?」 やっとゆうきの真意に気づいた華が、動揺しまくりながらなんとか捉えられている腕の中から抜け出そうとする。 だが。とき既に遅く。ゆうきの手は華の衣服を脱がせにかかっていた。 「ええ?まっ、まて、やだ!ゆうきちゃん、わたし学校いかないとっ。……ああっ、それにゆうきちゃんも仕事でしょ?仕事っ。」 必死に言い募る華を無視して、ゆうきが華を抱えあげた。 「ああ、あのメールか。うそだよ。今日は仕事なし。一日中OFF。」 慌てまくる華をよそ目にしれっと答えてくるゆうき。 なんとなく、その回答が予測できたとはいえ、華はくらりとめまいを覚えた。 やっと。やっと手に入れることが、できる。 長い間。ずっと我慢してきた。 華が16になったらこの手に捕まえて見せる。そう、思いながら。 この柔らかな身体を抱くことのできる日をどれ程狂おしく願っていたことか。 腕の中でじたばたと暴れる華。 その様子すら、愛しく感じる自分にゆうきが心の中で苦笑する。 くるくると表情の変わる妹の様な存在だった華。 それが、ゆうきの中で女になったのは、6年前。 初めて華に欲情したのは、華の父親が亡くなった二日後。 葬儀の夜のことだったと、華の体を抱えながらゆうきがふと、思い出す。 もともとあまり体の丈夫でなかった華の父親・康弘は、雪の降る真冬の深夜に息を引き取った。 ある程度覚悟していたとはいえ、康弘の妻であり華の母親である澄香はひどく泣き崩れ、その悲しみようは傍から見ていても痛々しいものだった。 澄香の友人でもあるゆうきの母親が子供のように泣きじゃくる澄香の背をさすり、そのまま一晩中静かに澄香の傍にいたことをゆうきは今でもはっきりと覚えている。 ――華は、泣いてなかった、な。 父親の亡骸の傍に座り込み、きつく唇をかみ締めたままじっと下を向いていた、華。 その横には、華の手を握り、同じように下を向いた奏がいた。 その光景に、僅かに感じた苛立ち。 多分、自覚してなかっただけで、もっと前から華は自分にとってとっくに特別な存在になっていたのだろうと、今にしてゆうきは思っている。 そして、そっと華の傍にいき「大丈夫か」と声を掛けたとき。 華がはっとしたようにこちらを向いた。 しばらく無言でいた華が、こっくりと頷く。 「うん。……うん、大丈夫。」 そういうと、ふいっと横を向き、華は再び黙り込んでしまった。 それからゆうきはもろもろの雑用を、自分の父親と奏の両親と共にこなし。そのまま通夜、そして葬儀とあっというまに時間が過ぎていた。 その間、華が泣いている姿は、一度も見なかった。 集まった親族たちが気の毒そうな視線を投げかける中、気丈に振舞う華。 だいぶ落ち着いたとはいえ、まだ幾分顔色の悪い澄香を気遣ってすら、いた。 だからこそ。 葬儀がすべて終了し、両親より一足先に自宅に戻ったゆうきの部屋に華がいたときは、本心から驚いた。 おまけに、その黒々とした両目からはぼろぼろと大粒の涙が流れていたのだ。 「華?……どうした?」 扉を開けた格好のまま、やや呆然と問いかけるゆうきの腰辺りにどん、と華が飛びついた。 「ゆぅきちゃ……う゛……ふ……うぅ……」 そのまま堰を切ったように嗚咽を漏らし始める。 「うわぁぁあん――っ」 ゆうきはやっと、わかった気がした。華が、泣けなかったことを。 取り乱した母親の姿に、自分がしっかりしようと思ったのだろうこと、を。 「……ここでなら、好きなだけ、泣いていいぞ。……華、苦しかったな……。」 そっと華の頭を撫でながら、なだめるようにやさしくその華奢な背中をぽんぽんと叩く。 ゆうきは、開きっぱなしになっていた部屋の戸を静かに閉めると、泣きじゃくる華の体をしっかりと抱えなおした。 ――こんなに小さな身体で受け止めるには、父親の死は重過ぎる、な。 華の泣き声が止んだのは、それから数十分後。 ゆうきの腕に支えられてた華がそのまま眠り込んでしまってからだった。 ゆうきは腕の中でずるずると滑り落ちるように寝入ってしまった華を抱え上げ、ベッドに運び、ふとんをかけてやった。そのままベッドの枕元に腰かけ、閉じられた華の目に残った雫をそっと指で掬い取る。 涙に濡れた長い睫。無防備にすやすやとたてられる寝息。やや顔色は悪いものの、ふっくらとした頬。 枕の上に広がるつややかな黒髪。 そして。わずかに開かれたさくらんぼ色の、唇。 気づいたときには、ゆうきは華の上に屈みこみ。その唇に自身のそれを重ねていた。 触れた瞬間。一気に身のうちが、熱くなった。 華が起きないのをいいことに深く唇を重ね。口腔内を思う存分貪った。 「……ん、う。」華の、苦しげな……声。 はっと、した。急いで唇を離し。だが、自身の熱さは収まらず。 そうして。その時。 ゆうきは、眠り込んでしまった華の寝顔にありえない感情を抱いている己を自覚、した。 自覚してからしばらくの間、ゆうきは自分の性癖に随分疑問を持ち悩み。手当たり次第に女を誘っては、寝た。 普通の女でも、ちゃんと男としての機能は働くことを確認したかったのだ。 その結果行き着いた結論は、華だから、ということ。幼い少女に性的興奮を感じるわけじゃ、ない。 華だから。華だから、こそ。 しかし、その思いを告げるには華は幼すぎ。 そのまま隣人としてただの兄役を演じることなどできるわけがなかったゆうきは。 とうとう二年後、華の傍にいることに限界を感じ、社会に出ると共に引越しを決意したのだった。 だが、もちろん、華との繋がりが切れることなど考えられなかったので、自分の寝起きの悪さを理由に華の訪問を促すことも、忘れなかったが。 *** 「だだ、だめってば、ゆうきちゃんっ。」 半分以上服を脱がされた状態でベッドの上に放り出された華の上に、ゆうきが圧し掛かって来た。 不意に声を低めてささやくゆうき。 「嫌がるなよ……。6年、待ったんだから……。」 切なげにそう言われると、華は何も言えなくなる。 それでも、いきなりこの展開は華にとって急過ぎた。ゆうきの手が華の体の上を滑っていく。 華は、身をよじりなんとかゆうきの下か這い出そうとこころみたが、しっかり押さえつけられ、どうにもならない。 「ゆうきちゃんっ。やだってば。やっ!」 華の脚に触れていたゆうきの手が這い上がり、ショーツ越しに触れてくる。 「っ!んっん」 華の眼がきつく閉じられる。スカートのホックが外され、華の足から滑り落ちた。 「……華、いい子だから。力、抜いて?」 ゆうきの要求に、華が首を左右に振り、厭々をする。困ったようにゆうきが華の耳元に口を近づける。 「華、傷つけたくないから。言うこときいて。」 だが。なおも首を振り続ける華の眼から大粒の涙が、零れ落ちた。 「や、だ。……ゆうきちゃん。……このベッドは……や……」 ゆうきから顔を背け、華が小さな声で告げる。 確かに行為そのものにも、動揺し、困惑している。 だが、それ以上にこのベッドでゆうきに抱かれることが華は耐えられなかった。 ゆうきに呼ばれた日の朝。このベッドに眠るゆうきと見知らぬ女性。 どんなに平気な振りをしても。やっぱり心は痛んでいた。 「……ああ、そう、か。」 華の心情を理解したのか、ゆうきが気まずげに上体を起こす。 「悪かった。華、おいで。」 返事を待たず、ゆうきが華を再び抱え上げた。 そのまま大股で部屋の中を進み、リビングへと続く扉を開け放つ。 華が不安げにゆうきを見つめる中、その足はリビングを通り過ぎ、客間へと進んでいた。 ゆうきはこの四年間、華を朝呼ぶときは、必ずその前の晩に女を連れ込んで、いた。 選ぶのは、本気の恋愛ではなくゲームのような関係を求めている後腐れのない女ばかり。 一晩限りの関係を持ち、その後何度か同じ女から誘われることがあってもすべて断っていた。 理由は、簡単。華に特定の女と付き合っていると思われのを避けたかったから。 華に会う前に性欲の処理。最低だとは、思っていた。それでも、止める事は出来なかった。 でなければ、確実にこの四年の間にゆうきは華を押し倒している。 嫌がろうと抵抗しようと、きっと途中で離してやることなど無理にきまっていた。 だが。その行為が華を傷つけていたことを知り、ゆうきは今現在、深く後悔していた。 客間に入ったゆうきは、そっと華をベッドの上に降ろす。 不安げにゆうきを見つめてくる華。 安心させようと、ゆうきの手が華の頬をやさしく撫でる。 くすぐったそうに目を細める華の唇に軽くキスを落とすと、恥ずかしそうに華が目を伏せた。 華のほぼ顕になっている上半身に残っていた服をゆうきがすべて取り払う。 覆うものが無くなった胸を華の両腕があわてて覆い隠した。 「あ、の……ゆうき、ちゃん?……本気、で……?」 伺うような顔でゆうきを見つめてくる華。 「何をいまさら。往生際の悪い。」 ――いまさら止められるわけがないし、冗談でこんな状況に持ち込めるわけがない。 「ほら、はーな。」 ゆうきが華の膝に手を掛け、足を開くように促す。 顔を真っ赤にして逡巡しながらも、華が緩慢な動作で白い脚を僅かに開く。 その隙間へゆうきが体を滑りこませた。 華の上に覆いかぶさったままゆうきは着ていた服を脱ぎ捨てる。 大きな手を華の胸のふくらみへと伸ばし、外側からゆるゆると撫で上げていった。 「ん……ゆうき、ちゃん」 華の甘い、声。 首筋から胸へ。ゆうきは華の体に唇を這わせる。 胸の頂を口に含み軽く甘噛みすれば、僅かに震える華の身体。 ショーツの中へゆうきが指を忍び込ませる。だが、その狭さにゆうきの指が浸入を拒まれた。 「痛っ!」 華が、顔を顰める。 「やっぱり、きつい、な。」 ゆうきがその感触に僅かに笑みを漏らした。 華が受け入れる男は、間違いなく自分が一番最初であることに安堵と幸福感を覚える。 性急に奪ってしまいたい衝動を抑えながら、華の快感を引き出そうとそのまま華の下腹部へと頭を下げていった。 ゆうきの唇が華の中心へとたどり着く。 「え!?」 華の動揺した、声。 あわてて上半身を起こそうとする華の足を押さえつけ、ゆうきがそこへ舌を這わせる。 「ん、んんっ」 ささやかな抵抗をすべて封じ込め、ゆうきは華の中心部を舐め上げ、舌を差し入れる。 「や、やぁん……ん、ん」 ややすると、華の中からとろりと蜜があふれ出てきた。 とどまることなくあふれ出るそれをゆうきが舐め取っていく。 その味に、自身が高ぶっていくことが判っていたが、今は何とかなだめながら、ゆうきは華を執拗に責め続けた。 「あ、ん、あああ!」 甘く、艶やかな声を上げ、華の一度張り詰めた体からゆっくりと力が抜けていく。 痙攣を繰り返す秘所に、華が達したことを確認したゆうきが、そこにそっとキスを落とす。 ゆうきの指がやさしく華の中に浸入してきた。 「んっ。」 華の眉が僅かに顰められたが、今度はすんなりと受け入れる。 内部で蠢くゆうきの指が華の内部をゆっくりとほぐしていく。 「ゆ……うき……ちゃ……、あっ……ん、……だ……め……、やっ、動かさない、で……」 華の肌がうっすらと上気し、薄紅に染まっていく。なまめかしく動く肢体に、ゆうきが煽られる。 クチュリ、と音をたてゆうきが指を引きぬくと、華の体がわずかにふるえた。 荒い呼吸を吐きながらきつく眼を瞑っている。 これ以上は、我慢できそうもない、な。 自身の限界を感じたゆうきの手が華の腰へとかかる。 「華、少し腰上げて。」 華は眼を閉じたままゆうきの指示にしたがった。 ゆうきの手が腰の下にまわされ、熱い高ぶりが華の中心部に当てられる。 ゆっくりと華の中に侵入を開始するゆうき。 華の眼が開かれ、痛みにより再び閉じられた。 華の爪がゆうきの背に食い込んでいく。 「んん、……いっ……たぁ」 内部に入り込んでくる異物感と痛みに耐えているのだろう。 華の顔が苦しげに歪んでいる。 「ごめんな、辛いか?」 驚くほど狭い華の中を進みながら、ゆうきが華の頭をそっと撫でてやる。 目に涙を滲ませながらもゆうきに微笑みかけ、ふるふると頭を横に振る華。 ゆうきは眩暈がする程の愛おしさに襲われながらも、慎重に華の中へと沈み込んでいった。 ゆうきを全て受け入れたときには、華はくったりとしていた。 だが、ゆうきもそうとうきつかったのか、額に汗が滲んでいる。 華がそっと見上げたその先には、華の中に入ったまま、額に張りついた髪をうっとおしげに掻き揚げるゆうき。 いままでゆうきに感じたことのない色っぽさに華の心臓がどきどきと早鐘を打つ。 見られていることに気づいたのか、ゆうきが華を見つめながら甘い笑顔を浮かべた。 華の耳元へ口を寄せてゆうきが囁く。 「……華、愛しているよ。」 ゆうきの言葉に華の頬が朱に染まった。 その様子を見たゆうきが小さく笑いを漏らす。 「動いても、大丈夫か?」 こくりと、華は頷いた。 痛みはだいぶ薄れてきている。それに、ゆうきの感触になれてきたことにも華は気づいていた。 華の承諾を得て、ゆうきがゆっくりと華の中で動き始めた。 その律動にあわせるように華の中でいままで感じたことのない感情の波が打ち寄せてくる。 「あ、あっ……」 小さく声が漏れた。 痛みは既にほとんどなく、甘い痺れが華の体を震わせる。 「ゆうき、ちゃん、大好き。」 ぽんと口をついてでた言葉に、華の中に納まっているゆうきが反応した。 驚いてゆうきを見れば、困ったように苦笑していた。 「……あんまり煽られると、やさしくできなくなるだろ。」 「……やさしくなくても、いい、よ?」 再び口をついてでた言葉。華は自分自身に驚く。 だが、それ以上にゆうきは驚いたらしい。動きを止めて、まじまじと華を見てくる。 僅かの沈黙ののち、ゆうきがふっと笑った。 「その台詞、後悔するなよ?」 甘い声音でゆうきが華へと告げる。 そして、そのまま華へ口付けると、深く深く突き上げてきて――。 「あ、ああ……ふ、あ……ああぁっ」 ゆうきにより齎される強い刺激に華は何も考えられなくなり、頭の中が真っ白になっていった。 この後。華は自分のいった台詞にたっぷりと後悔しながらも、ゆうきにより何度も上り詰めさせられ……やっとゆうきが満足して華を解放したのは昼も大分過ぎてから、だった。 踏み越えることの出来なかった恋人への境界線。 10年間目にしてそれをやっと超えることの出来た二人は、ベッドの中でシーツに包まり。 満ち足りた顔で深い眠りに落ちていた……。 〜Fin〜 |
| ラヴァーズ・ラインINDEX |
TOP ‖ NOVEL |
Copyright (C) 2003-2006 kuno_san2000 All rights reserved. |