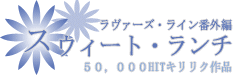 |
照りつける太陽が中天に昇りきるほんの少し前の時刻。 心地よい寝心地を誇るベッドの上より、ゆうきは漸くのそりと起き上がっていた。 ほんの少し寝癖のついた髪を鬱陶しげにかきあげ、まだ幾分ぼんやりした表情のまま欠伸をかみ殺す。 そして昨晩は隣にいたはずの華の姿を捜して、軽く伸びをしながら床へと足を下ろした。 フローリングの床をキシッと軋ませ、ゆうきが寝室の扉まで足を進める。 ドアノブに手を掛け、僅かに扉を開いた。 リビングから流れてくる空気。その中に混じる香ばしい匂い。 おそらく華が昼食を作っているのだろう。 ゆうきはいつものように楽しげにキッチンに立っているのだろう華の姿を思い、口元に笑みを刻んだ。 ドアノブに触れた指に力を掛け扉を開け放つ。 壁のほぼ一面を埋める窓から差し込む陽光。 それはリビングの中にある見慣れた家具類を照らし出していた。 ソファとローテーブル。それに電化製品が少しとローボード。 眩しさに眼を細めながらゆうきが視界におさめたそれらは、いつも見慣れた物。 しかし意外なことにその中には、床に座り込みながらソファに肘を掛けて寄りかかっている華の姿があった。 ゆうきが起きて来たことにはどうやら気づいていないらしい。 熱心に何かに見入っている華の背中だけがゆうきから伺えた。 ―――珍しいな・・・。 常であれば、すぐに向けられるはずの華の笑顔。 なのに、今日はそれが無い。 何をそれ程熱心に見ているのかと、ゆうきが華の視線が向いているのだろう先を伺ってみれば、そこには29インチのTV画面。 ただ明るい陽光が反射していて、ゆうきのいる位置からでは放送している番組まではわからなかった。 ゆうきがそっと寝室から一歩足を踏み出す。 そして、華に気づかれないように歩を進めようやくTVの見える位置に来た時。 『君が―――君のことが・・・好きなんだ。』 唐突に響いてきたのは低い男の、声。 ゆうきが目を細め訝しげに顔を顰める。 ブラウン管の中では―――ゆうきもよくTVで見かける俳優が丁度相手役の女優に告白した場面が繰り広げられている、らしかった。 その映像に、ゆうきが僅かに目を見張る。 華はどちらかといえばあまり恋愛ドラマの類は見ない。 しかも今華が見ているのは、確か噂では悲恋物だったはずである。 どう考えても、華の好みには会わなかった。 不思議に思いながらも、ゆうきは足音を立てずに華の真後ろへ立つ。 「・・・おもしろいのか、それ。」 「え・・・っ!?・・・あ、ゆうきちゃん。あれ、いつの間に起きてたの?」 背後から声を掛けたゆうきを、ぱっと振り向いた華が心底驚いたというように見上げてきた。 やっぱりまったく気づいてなかったのかと、ゆうきが口元に苦笑を浮かべながら 「今さっき。」と答えると、華が困ったように笑った。 「そうなんだ。全然気づかなかった。えっと・・・ゆうきちゃん、おはよう。」 「はい、おはよう。・・・珍しいな、華がこういうの見てるのは。」 挨拶を返した後、ゆうきがちらりとTV画面に目を向ける。 華もそれにつられたように再びそちらへ顔を戻した。 「ああ、うん。あゆにね、面白いからみてごらんって進められたから。」 華のその一言に、ゆうきがなるほどと納得する。 たまに話題に上る華のその友人は、確か大層なドラマ好きだったはずなのだ。 ―――それで、見事に嵌ったわけか・・・? 真剣に画面に魅入っている華の姿に、ゆうきが苦笑しながら肩を竦めた。 ドラマが終わるまで動きそうに無いその様子に、ゆうきは華が凭れかかっているソファにどさりと腰を下ろす。 組んだ足の上に肘を着き、軽く頬杖をつきながら。 ゆうきは華と同じように、画面へと目を向けた。 それからほぼ三十分。 展開されていったのは、かなり使い古されたストーリー。 ドラマが終わった頃、ゆうきは欠伸をかみ殺していた。 しかも見終わった後の感想といえば、主人公の人気で持ってるドラマって噂はあながち外れじゃないらしい、という程度のものだ。 そんなゆうきの前で、華がふうと息を吐いた。 くるりとゆうきの方を振り返る。少し目尻に涙が溜まっていた。 使い古された展開とはいえ、華には充分効果があったらしい。 優しく笑い、ゆうきが「泣いてる。」と言いながら華の目元に指を当てる。 少し頬を赤くしながら、照れたように華が笑った。 「えっと・・・。主役の人が凄くオススメだよってわれたんだけど。・・・格好良いね、やっぱり。」 ごしごしと掌で目元を拭いながらの、おそらく何気ない華の一言。 特に意識していったわけではないのだろう。 だが、ゆうきの眉がぴくりと上がった。 何故なら―――・・・ 華が格好良いといったその俳優は、さらさらの茶髪、銀縁眼鏡を掛けた長身の男。 それは―――確実に誰かを連想させる。 そう。ゆうきがはじめてこの俳優をTVで見たときの感想は、奏に似ている、だった。 華はそのことに気づいているのか、いないのか。 まだ目元を拭っている華の手をゆうきがそっと押さえた。 動きを止められた華が驚いたようにゆうきを見つめてくる。 「華、こういう男がタイプ?」 口元に薄く笑みを刷き、ゆうきが尋ねた。 何のことかわからないというように華が数回瞬きする。 じっと見つめるゆうきの前で、華が考え込むように首を傾げた。 と。急に思いついたように小さくあっと声を上げる。 「―――あのね、もしかして・・・主役の男の人・・・?」 ―――奏に、似てる? 自信なさ気に最後の部分が消えた問いかけ。 言外に篭められたその言葉を、ゆうきは無言の笑みで受け止めた。 何も言わないゆうきを、華がちらりと困ったように上目遣いで見ている。 どうやらゆうきの態度を肯定と受け取ったらしい。 ここははっきりとした華の答えを聞いておきたいゆうきは、そのまま華の出方を待つことにした。 「・・・えっと。・・・私のタイプの人は、ね。・・・」 少し黙り込んだ後、ようやく華が口を開いた。 思わずゆうきが聞き入る。 だが、華は一旦そこで言葉を切った後、一度顔を伏せ―――突然ぱっとあげた。 「秘密。」 悪戯めいた笑みを浮かべ、華がゆうきに答える。 華の腕を掴んでいたゆうきの手がするりと外された。 かわされたことに驚きながらも、素早く立ち上がった華を捉えようとゆうきが腕を伸ばす。 「はーな、大人しく白状しないと――――・・・」 しかし、伸ばしたゆうきの腕からするりと身をかわし、華が笑い声を立てながらキッチンのある方向へと逃げだした。 ゆうきがソファから立ち上がり、後を追おうとして。 華がキッチンの入口で振り返る。 ゆうきの足が反射的に止まった。 「あのね、私のタイプは―――ゆうきちゃん、だよ?」 少し頬を染めながら、華が笑う。 不意をつかれて、ゆうきが言葉を失った。 華がぱたぱたとキッチンの中へ姿を消す。 ゆうきは華の消えたキッチンの入口を見つつ、くしゃっと髪をかきあげながら、溜息を落とした。 ―――いつの間に、こんな予想できない行動をとるようになったんだか・・・。 そう思いながらも、ゆうきの口元に覗いているのは甘い笑み。 ・・・振り回されてるな。 ぽつりと思う。しかも、案外それは的外れでは無い。 だがゆうきはそれをまったく不快に思ってはいなかった。 自らの手の中で日々成長してく華の姿はとても甘くゆうきを誘う。 それに一度知ってしまった華の蜜は格別で―――・・・。 再び溜息を一つ落とすと、ゆうきはゆっくりとキッチンへと向けて歩き出した。 *** キッチンの中を覗くと、そこにはぱたぱたと忙しそうに動き回っている華の姿があった。 ふと見渡せば。クッキングヒーターの上に鍋に入ったスープがのっている。どうやらそれが、ゆうきがリビングに入った時嗅いだ香ばしい匂いの元らしい。 ぎっと床を軋ませたゆうきの方へ、ミルクパンを持った華が振り向く。 はにかんだような笑顔。 ゆうきは無言で華の傍まで近寄ると、華が手にしていたミルクパンの取っ手を掴み、素早く取り上げてシンクの中へと置いた。 まだミルクパンを持っていた体勢で不思議そうにしている華に、ゆうきが甘い笑みを浮かべる。 華の腰に手を廻し、強引に引き寄せた。 「きゃ・・・っ、・・・ゆうきちゃん、なあに?」 華が強引なゆうきの仕草に、戸惑った声を上げる。 それには構わず、ゆうきは抱き寄せた華の耳元に口を寄せた。 「―――華、さっきの答え、本当?」 吐息を吹きかけるように華の耳元で囁く。 腕の中の細い体がびくっと震えるのを感じる。 その反応が可愛くて、ゆうきは答えを待たずに華の背中にすっと指を走らせた。 「あ・・・っ!」 ゆうきの腕を掴んで、華が背を反らす。 ゆうきを見上げてくる目は、既に幾分熱を孕んでいた。 「華?」 柔らかな耳朶を甘噛みしながら、ゆうきが華を促す。 「・・・・・・ん、ほ、本当・・・。」 小さく落とされた答え。 ゆうきはそれを聞くなり、華の頭に手を廻し上向かせると、その唇に深く自らのそれを重ね合わせていた。 「ゆ、・・・き・・・ちゃ・・・」 キスの合間。華が甘えるような声を上げる。 今、ゆうきの耳に届くのは、甘さを含んだ華の吐息。 何度も何度も角度を変えてキスを交わす度に漏れる蜜の音。 ゆうきの手が華の胸あたりを彷徨う。 薄手の布と下着の感触。 「・・・ん・・・っ」 甘い声をあげていた華が僅かに身じろいだ。 ゆうきは構わずに手を滑り降ろすと、華の上着の中へと差し入れる。 薄手の上着が捲くれ上がって、華の白い肢体が覗く。 少しひんやりとした肌の感触を楽しみながら、ゆうきは華の胸を覆っていた下着に指をかけ、肌を愛撫しながら上へとずらした。 柔らかな胸。桜色に染まった頂も全て顕になる。 少し固くなったその頂を、ゆうきが親指の腹で優しく撫でた。 「や・・・駄目・・・。」 ゆうきの腕を掴んでいた華の細い指に力が籠もる。 「どうして?・・・ここ、ほら・・・固くなってる。」 「ん・・・、や、だ・・・ゆ、ゆうきちゃん・・・いじわる・・・なんだも、ん・・・。」 拗ねたような華の答えに、ゆうきが苦笑した。 意地の悪い事をしているつもりは無いが、もしかしたら無意識のうちにいつもより強引にはなっているのかもしれない。 先程の華の言葉と行動。それらに煽られていることに気づきながらも、ゆうきは続きを止めるつもりはまったく無かった。 「華・・・。」 軽く額にキスを落とし、ゆうきが甘く囁く。 「あ・・・、ん・・・ゆうき、ちゃ・・・、ま・・・っ」 華がいい終わるより早く、ゆうきは言葉尻を捉えて華の唇を塞いでいた。 *** 「ん・・・やあ・・・あ、ああ・・・っ!」 びくんと華の体が数回震え、絶頂の余韻を残したままゆうきの腕の中に崩れ落ちた。 荒く息をつく華を片腕で支えながら、ゆうきがくちっと音をさせ、華の中から指を引き抜く。 華が気だるげに目を開けた。 「・・・ゆうきちゃん、は?」 汗の滲んだ華の額に口付けたゆうきに、華が小さな声で問いかける。 華だけを高みに追い上げ、ゆうき自身はまだ昂ぶったままだ。 「いじわるだから、嫌なんだろう?」 先程の華の言葉を持ち出して、ゆうきが甘く微笑む。 もちろん華が本気でいったわけではないことくらいわかってはいたが、でも今は華がどう返してくるか・・・その反応を見たかった。 「だって・・・それは・・・っ」 答えに窮したらしい華が、ゆうきに向けてきた潤んだ瞳。 それは、初めて抱いた時となんら変わってはいない。 ゆうきはゆっくりと腕を持ち上げると、その先にある自身の指を、黙り込んでしまった華の目の前に翳した。 華が頬を朱に染めて、顔を背ける。 ゆうきの指には、先程の華の蜜がとろりとした質感を持って絡んでいた。 華がほんの少し、ゆうきへ視線を戻す。 ゆうきはそれを確認して、華の蜜が絡んだ自らの指を唇にあて、舌で舐めとった。 「や・・・っ!」 華がぱっと目を見開いて、ゆうきの腕にしがみ付いてくる。 「・・・いつもしてるのに?・・・華の、美味い。」 「・・・でも・・・だって・・・とにかく、駄目!」 華は真っ赤だった。 確かにゆうきはいつも、今の様にわざわざ見せつけるような真似はしない。華が恥ずかしがるからだ。 ゆうきは苦笑しながら、唇に当てていた手を離して広げた。 「はいはい、お姫様。・・・他にご所望は?」 「―――ありません。・・・もう。ゆうきちゃんの、馬鹿。」 ぷいっと華が顔を背けた。 その恥らう姿も初めて抱いた時と変わってはいない。 ゆうきは甘く笑いながら、華をきつく抱きしめる。 成長していく姿を見るのは、嬉しい。 だが、まだ自分の手の中にいて欲しいとも思う。 いつか自分の手に負えない程、華は女になる。 その時にはきっと今以上に振り回されるのかもしれない。 それは、ゆうきがこの日覚えた―――確信めいた予感、だった。 *** 「じゃあ、続き・・・ベッドに行く?」 華の額と自分の額を合わせながらゆうきが囁く。 「・・・うん。」 僅かに躊躇った後、華がこくりと頷いた。 と、そこで―――ゆうきは不意に眉根を寄せた。 現在いるこのキッチンではあまり嗅いだことの無い匂いが鼻についたのだ。 「華・・・?」 「ん・・・何?」 ゆうきの腕の中に収まっていた華が顔を上げる。 「焦げ臭くないか・・・?」 ぽつりと落とされたゆうきの言葉に、華がしばし固まった。 ぱちぱちと数回瞬きをして―――・・・ 「え・・・・、あ、あ!大変っ!」 慌ててゆうきの腕の中から身を引き剥がし、オーブンの取っ手へと手を伸ばす。 音を立てて開けたその中。 そこにはすでに真っ黒となった・・・グラタンの残骸があった。 通常10分程度入れておけばいいところを、その数倍オーブンの中に入れておいたのだ。当然といえば当然の結果といえる。 「・・・やっぱり・・・。」 華の悲壮な声。 項垂れる華の後ろ姿を見つめつつ、やっぱりオレの責任だろうなとゆうきが苦笑いを浮かべて首に手を当てる。 くるりと華が振り返った。 「・・・もう、材料ないの・・・。」 眦を下げてゆうきを見上げながら、キッチンの床に座り込んでいる華を見て、ゆうきが噴出す。 「ゆうきちゃん、酷い。」 華が黒焦げになったグラタンを取り出しながら、ゆうきを軽く睨んでいた。 だが、ゆうきの笑いは収まらない。 華の今の姿は、昔―――華がはじめてゆうきのマンションで料理を作った時と同じだった。 ―――あの時は確かオーブンの調節を間違ったんだったかな? 懐かしく思い出しながら、ゆうきは手近にあったスプーンを手に取る。 そして華の持っているグラタン皿から一掬い。 口の中に、じゃりっとした感触と、苦さ。 「やっ、何しているの!?ゆうきちゃん!」 華が慌てて皿を引いてゆうきを止めた。 ゆうきが口元を押さえる。忘れていた味だったが、そういえば随分な食感だったと・・・昔これを食べた瞬間を今ようやく思い出していた。 泣きそうだった華の顔。 ―――これも、変わってないな。 ゆうきは華が慌てて差し出したコップを受け取り、口内のものを全て水で流し込む。 「もう、ゆうきちゃんて時々無茶なことするんだもん。・・・昔も、そうだった。」 呆れたように華が呟く。どうやらゆうきと同じようにしっかりと昔の記憶が蘇っていたらしい。 シンクの中にコップを置き、ゆうきはそっと華の頬に触れる。 「じゃあ、あの時と同じに―――外に食いに行くか、昼。」 「―――うん。」 華がにっこり笑って頷いた。 結局。こうしてマンションでの二人の甘いランチタイムは―――中途半端なままお預けとなったのだった。 〜Fin〜 |
| ラヴァーズ・ラインINDEX |
TOP ‖ NOVEL |
Copyright (C) 2003-2006 kuno_san2000 All rights reserved. |