| WebClapお礼小話 主人と執事と聖夜の誓い・続編 ※こちらのお話はR指定作品につきwebclapお礼としては使用しておりません 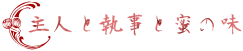 |
冷たい闇夜の中、澄んだ空気の中に佇む豪奢な館があった。 ゴシック様式を取り入れたと思しき建築は尖頭アーチが様様なバリエーションを誇り、大きめに取られた窓は日中溢れんばかりの光を注がれるだろうことが容易に想像できる。 その中でもとりわけ、陽光を充分に望めるだろう位置にある窓。 漆黒の帳に覆われた館の中で唯一人の気配が感じられるそこは、僅かな蝋燭の明りが映りこむ布帛に覆われていた。 件の窓を有する一室の持ち主――、この館の主人に他ならない少女は今、一糸纏わぬ姿で豪奢な寝台の上にいる。 しかし一人寝をしているわけではなく、そろそろ有能な執事の仮面を脱ぎ捨てにかかった青年に組み伏されている真っ最中だ。 純白で整えられた清潔な亜麻の織物は、情事の色を感じされるように少女の下でくしゃくしゃに乱れている。 「……や……っ、もういい加減に……んっ」 何故か蜜口の浅いところで動きを止めてしまった執事にたまりかねて自ら動こうとした少女が、それを押し留められ不満の声を漏らした。 体の奥が疼き、咎めの言葉にすら甘い吐息が混じっている。 だが、細い腰は執事の両手に捕らわれ、どうすることもできなかった。 「如何なさいましたか?」 「……本当にお前って……」 形の良い唇をきりりとかみ締め、少女が瞳に涙を浮かべる。 慇懃無礼な執事、彼はこんなときだけたまらなく淫らな男の顔になる。 「底意地の悪い変態だわ」 「お嫌でしたら、いつでも止めて差し上げますよ?」 組み敷いた少女を倣岸と見下ろし、執事が薄く笑った。 「だから意地が悪いというのよ……っ」 惑うように少女の瞳が揺れ、白い頬が羞恥に紅く染まる。 酷く可憐なその姿を見たいがために、執事が無体を強いることを少女は知らない。 「…………もっと奥まで……ちょう、だい……」 悔しげに顔を背け、矜持をねじ伏せ、少女は懇願した。 「――んっ、やぁ、な、に……っ、」 「いい子にしていなさい。奥まで欲しいのでしょう? ――ミナ」 恭順から征服へと執事の態度が豹変する。 この男が敬称をつけず主人の名を呼ぶなど、寝台の上以外では到底ありえない。 ――こんな時ばかり、卑怯者……っ。 一瞬掠めた詰責の言葉は、けれど身体を揺する青年に封じられた。 凶悪な激しさ。 激しく突かれる程、主人である少女、ミナの中で疼きがいや増す。 執事を受け入れる前、舌と指で散々に焦らされていた彼女の限界は間近だった。 甘く上がる声の感覚が短くなっていく。 容赦のない執事に最奥を嫌というほど突かれる。 突いてはギリギリまで引き抜き、それを何度も繰り返されて、ミナは我知らぬうちに執事の背中に爪を立てていた。 「ん、ん……っ、あ、シュロ、シュロイ……んっ!」 瞑った瞼の裏が白く弾ける。漸く許された絶頂感にミナの全身が震える。 「……っ」 紅く色づく艶やかなミナの唇が戦慄く。 上り詰めた瞬間、執事の名を紡いだその紅い唇は本人により塞がれ、普段の冷たさからは比べるべくもない熱い精がミナの中に放たれた。 *** 快楽の余韻を残した瞳でぼんやりと横たわった少女の汗ばんだ額に張り付いた金の髪を、執事の指がそっと払う。 「お体をお拭き致しましょう。ご用意致しますので少々お待ちください」 寝台を降り、着衣を整え、情事の欠片も残さず有能な執事に戻った青年が寝台に背を向ける。 初夏に入った頃とはいえ、夜露に濡れる草木が齎す空気は冷やりしていた。 白い肌を惜しげもなく晒す主人をこのままにしておくわけにはいかないと、執事は曇り一つ無く磨かれた革靴に足を納め歩き出す。 「……いかないで……シュロイ……」 小さな、ともすれば聞き逃してもおかしくはない程の囁き。 が、聞き逃す事の無かった執事の足はぴたりと止まった。 聞き間違いかと眉をひそめる。 けれど背後に感じる主人の息を詰めたような気配が聞き間違いではないと教えている。 「如何なさいました……ミナ様?」 いぶかしげなそれは、途中から驚愕を含んだ問いかけとなった。 執事が振り向いた先には、気の強く、意志の強く、時に気まぐれな猫のようでもある主人の姿があるはずだった。 けれど彼の目が映し出したのは、常とはまるで違う、不安げで頼りなげな風情の少女だ。 「――マリーは……可愛い子ね」 突然の名に、執事の片眉が僅かに上がる。 マリーは、ほんの数ヶ月前から使用人として雇っている娘だ。 まだ若いがどこか婀娜っぽさを感じさせる娘で、男衆の間で度々話題にのぼっていることも手伝ってか、恐らく現在は使用人の間で噂される人物の筆頭にのぼっている。 が、この気性のはっきりした主人が殊更に気に入るような種類の娘ではない。 「それがいかが致しましたか?」 「お前、マリーが好きなの?」 真摯な瞳で問いかける少女に、執事は僅かに目を瞠った。 言われた事の意味を図りかねる。 「一体、何を仰って――……。」 言いかけ、言葉を切った。 やや思案気に少女を見つめ、執事は不意に薄い唇の端に笑みをのせた。 心得顔で優雅に踏み出された歩は、しとどに乱れた寝台でまだうつ伏せている少女へと向けられる。 「見ていらっしゃったのですか。覗き見とは随分はしたない」 「――覗いてなど、いないわ。お前が私の見ている前で勝手に……」 「それで? いかがなさいました? まさかとは思いますが、妬いていらっしゃる?」 寝台の端、身を屈めた執事は少女の頤に指をかけた。 一瞬見開かれた少女の目、それが挑戦的な執事の物言いに、徐々に勝気な色を取り戻す。 どうやらいつもの調子が戻ってきたようだと、執事は喉の奥で漏れそうになる笑いを殺した。 「自惚れないで」 「今の貴方をみたら、私でなくとも自惚れる」 「……っ、もういいわ! 下がって……っ」 少女が勢い良く顔を逸らし、執事の手を振り払う。 いつもは駆け引きのように楽しむ主従の沈黙が、今回ばかりは奇妙なほど重い。 室内に蝋燭の焼ける音がやけに大きく響く。 情事の間くらいは消して欲しい、と懇願できない女主人を良い事に灯されている仄暗い光源。 光陰を浮き彫りにするその中で、俯き峻拒を示すミナの様子に執事は苦く微かに笑うと、溜息をついた。 「――彼女は貴方の叔父君が送ってくださった間者です」 少女の頤を掴んで再び自分へと向き直させ、淡々と執事は告げた。 *** 「叔父君の、間者……?」 あからさまに訝る少女に、執事はええ、と軽く頷く。 確かにあの叔父であれば在りそうな話ではある、と些か親族としてはどうかと思うような事を考えるが、それでもミナにとってそれは、俄かに信じがたいものだった。 どうしても執事が繰る言い訳の様に聞こえてしまう。 「――お前、マリーを抱き締めて、口付けをしていたわね?」 まだ燦燦と陽光の照る屋敷の中で、物陰に隠れた二人が影のように寄り添っている場面に出くわした時の衝撃をまざまざと思い出しながら、確かめるように一言一言をはっきりと口にする。 執事の相手が自分ひとりだけだと自惚れていたわけではないが、よりにもよって屋敷の中で逢引をされるとは思っていなかっただけに、受けた打撃は相応に大きかったのだ。 「多少手を出さなければ信用していただけなかったもので。私は貴方を守る為ならどんなことでも致しますよ? それが例え貴方の意に添わないことだとしても。」 主人の為である、といけしゃあしゃあと言う所が実に憎らしく、引き合いに出された少女は眉間に皺を寄せた。 如何なる抗議をも封じる術を見につけているこの執事は、扱いづらい事この上ない。 ――なんで私、こんな男の事が好きなのかしら。 何やら改めて考えると、寧ろ己が腹立たしくなってくる始末だ。 「……私には見せたことない、顔、してたわ」 「ああ、それで拗ねていらっしゃる?」 「拗ねてないわ」 「困りましたね。私も流石に貴方相手に自分を偽るゆとりはございませんので。ですが、貴方が望まれるのでしたら極力努力してみないこともありませんが」 どう贔屓目に見ても、とても努力する気があるようには見えない。 けれど困ったように笑う執事の言葉を全て偽りだとは思いたくはなかった。 「――マリーの目的は?」 「私を誘惑し、あわよくば取り込むように、というところでしょう」 「……叔父君も馬鹿なことを……お前のような男を懐に入れれば、取り込むどころか逆に飲み込まれかねないというのに」 落ちたと思わせて油断させたマリーから、一体何を聞き出す事に成功したのやら。 何にせよ、叔父がまた一つ、それと知らずに弱みを握られたのは間違いない、と少女は詰めていた息を吐き、漸く納得の意を示した。 「彼女には明日暇を出します。概ね状況は把握いたしましたのでもう必要はありませんし、次に採用する使用人も決定致しましたから」 「マリーは納得しているの?」 「必要ありませんでしょう?」 拒否する権利など与えないと暗に告げ、執事はにこやかに微笑んだ。 この執事がぞっとする程冷酷になる瞬間を、ミナは知っている。 それはまさしく主人である自分の身に危害が加えられそうになるときに他ならない。 けれどもそれは、自分がこの男の主人であるからなのか、それとも自分が自分であるからなのか、ミナには判別がつかなかった。 「お前って男が、わからない。ほんの少しはわかったつもりでいたけれど、それは本当に”つもり”でしかないのだもの」 溜息混じりにごちた少女は、軽く身をよじり執事の手から逃れた。 寝台の上で膝を抱えて蹲り、抱えた膝に顔を埋める。 「――私の忠誠は、生涯貴方だけのものです」 「忠誠だけだわ」 「ご不満ですか?」 執事に切替され、馬鹿な事を言ったと後悔した。言葉に詰まって黙り込んだミナの耳が紅く染まる。 「……お前はいつもそうね……忠誠心で、私のことを抱いたんでしょう」 もう自分でも何を言っているのかわからなかった。こんな事を言うつもりなど無かったのに、と唇を噛む。 羞恥により、まともに顔を上げる事も出来ない。 その少女の豊かな金の髪に、執事の指がそっと触れた。 ゆるりと掻き分けられ、少女の紅く染まった耳が全て顕になる。両耳を押さえて全てを拒否しようとしたが、逃げる事を少女の自尊心が良しとはしなかった。 「――忠誠心で抱いたのでしたら、もっと優しくしておりましたよ」 往生際悪く俯いていたミナの耳元へ、執事が秘め事のようにそっと囁いた。 低い声と吐息に、ずくりと体の奥が疼く。 「これでおわかりになりませんか?」 尚も耳元にかかる執事の吐息に、堪りかねた少女は双眸に非難を込めて執事を見上げざるをえなかった。 「わからないわ……っ。」 「困りましたね。きちんとお教えしたと思っておりましたのに。では、これからもう一度教えて差し上げましょうか?」 「何、……ま……っ、」 待って、と言いかけた少女の唇は執事により塞がれた。 従順に見せかけながら、その実そんなものは欠片も持ち合わせてはいない慇懃無礼な執事が、少女を翻弄する青年へと変貌する。 「貴方は――本当にわかっていらっしゃらない」 「……お前が、教えてくれないからよ」 嬲られた咥内に残る熱に酔いながら、少女は赤らむ目元で執事を睨んだ。 「十二分にお教えしております。貴方がそれに気付いていらっしゃらないのですよ」 「私がお前から学んだのは、口付けと肌の熱さ。それに嫌味の言い方だけだわ」 「――それも違いなくはありますけれどね」 ふっと笑った執事が優雅に少女の背へ腕をまわし、細い喉元に唇を這わせはじめる。 「では、私は貴方に何をお教えいたしましょうか」 「――私はお前の、何?」 「もちろん、生涯ただ一人私がお使えする主人です」 からかう様に執事が答えると、ミナは息を詰めて執事を押し返し、強い瞳でしっかりと彼を射た。 「違うわ、そうじゃない。私を主人としか思っていないのなら、お前もただの執事に戻っ、」 「貴方の全てを食い尽くしてしまいたいほど想っております」 躊躇いのない間髪入れずの返事に、少女の方が面食らう。 絶句しながら、二度三度、瞼を瞬かせた。その度に少女の頬に落ち陰影を変化させる長い睫が震え、動揺を如実に表してしまう。 しかし続いた執事の言葉に、少女の口元は忽ち不機嫌なそれに変わった。 「けれど貴方を食べてしまったら、私はもう貴方にお会いできなくなってしまうでしょう? だから我慢しております」 揶揄されているような、弄ばれているような状況に「私をからかってるの?」と、つい口をつく。 「滅相も無い。私はこれ以上無いほど貴方を大切にしているつもりですが?」 不満も露な少女に執事は啄ばむように口付け、平然と言い放った。 狡賢い誤魔化し方だと思う。 だが、どうやらこれ以上本心を聞き出せそうもないと悟り、ミナは諦めの溜息をついた。 「――なら、事が済んだ後に早々と寝台を降りるのは止めて……義務でされているみたいな気がして、嫌。」 本心が聞き出せないのならせめて、常々不満に思っていることを一つぐらい、という軽い気持で言ったものだった。 しかし言った後で、これでは執事に何かを期待している様に聞こえる、と気付いた。 ――今日の自分はどうかしている。 紅くなった頬を隠す為、ミナが執事の視界から逃れるようにじりっと寝台の上をあとじさる。 それなのに、執事は寝台の縁に片膝をかけ、少女があとじさった分よりも多く傍に近づいてきてしまう。 「心いたしましょう。ほかにご要望はございますか?」 先ほど着なおしたばかりの着衣を自らの手で緩め始めた執事は、どこか楽しげだ。 何かよからぬ言質を与えてしまった予感がするが、今更後の祭りだった。 「――私だって時には言葉が欲しくなるのよ? お前はもっと女心を勉強すべきだわ」 「……女心……でございますか?」 溜息交じりに要求した少女に、執事は笑いが滲む声で答えた。 「ええ、そう」 ややむっとしながらも厳かに頷いた少女に、執事がとうとう声を立てて笑い出す。 「――シュロイ、お前って本当に無礼な男」 「失礼致しました、ですが貴方に女心を説かれるとは些か……」 ミナは、謝りながらも大概無礼な物言いをする男に呆れながら呼気に怒気を混じらせた。 けれど久しぶりにみることができた公々然とした青年の笑い声に、悪い気分では無いと気付いてしまう。 ――仕方がないわ。どうしようもないこの男が私は好きなんだもの。 己の趣味の悪さにいっそ清清しささえ感じながら、ミナはまだ笑いを滲ませる執事の首に両腕を回し、噛み付くように自らの唇で執事のそれを塞いだ。 〜Fin〜 |
| WebClapLOG INDEX |
TOP ‖ NOVEL |
Copyright (C) 2003-2006 kuno_san2000 All rights reserved. |