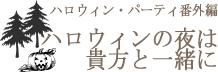 前編 もしも片方が誘拐されたら (カップルにもしもの10のお題「04」より) |
何がどうなって…私は今こんな状況に陥っているんだろう。 私が今居るのは、かなり豪勢な…というか。無駄に装飾の多い馬車の中。 それだけでも私の日常からすればありえないこと。 なのに。その上更に。 唯一外を覗うことができる窓には厚手のカーテンが引かれているので、もう今はどこを走っているのかすらわからなくなっている。 がたごと走る振動で軽く揺れるカーテン。 ああ。これ…引っ剥がしたい…。 恨みがましい一瞥をくれ、結構乱暴なことを考えてみる。 けれどその試みは既に一度実践しようとして。 ばっちり阻止された後、だったりした。 もうもうもう!一体全体なんだっていうんだ!! ああ、どうにもむかっ腹が立って仕方ない! 苛立ちに任せて、私は再び目の前に泰然と座している男を睨みつける。 ついでに、洗いざらしのスカートを揺らしながら足でごんごんと馬車の床を蹴飛ばした。 「―――私をどうするつもりですか?ついでに貴方誰ですか!」 先程から何度もしている詰問。 答えはもうわかりきっているのにそれでも聞かずにはいられない。 睨みつける先には外見だけはやけに爽やかそうに見える―――けれど私のまったく知らない男。 そして、一目で上等なものだとわかる服を身に纏い、しかもある階級に特有の優雅さと―――人を見下すような雰囲気を醸し出す、男。 多分、貴族階級だ…。 どうしてそんな人物の馬車に私がのる事になっているのか。考えれば考えるほどわからなくなってくる。 でも…これはどうにも良くない事態であるとしか思えないことは確かだった。 男は、私のきつい視線をあっさりと笑顔で受け止る。 「さて。何度も言っているように…僕が誰かは後ほど。貴方については―――さて、どうしましょうか?」 そして、やっぱりこれまた先程から何度も耳にしている答えを、返してきた。 だから!後程って一体いつ! 後ろで纏めてある髪に両手を突っ込んでがりがり掻き毟りたくなる。 ……そんなことしても、無駄だってことはわかってるからしないけどさ。 それに―――なんだかこの人、私の様子を見てとっても楽しんでいるような気がする。ならこれ以上取り乱した様子なんて見せてたまるか。 それにしても。 ひたすら延々と繰り返されている押し問答。 いい加減怒鳴りつける気力も無くなるってものだ。 はあ、と力なく溜息を落とす。 ああ、おかしい。おかしいってば、この状況はっ。 朝はあんなに楽しかったはずなのに。 今日のハロウィンをどう過ごそうかって。 つい一月ほど前に結婚した…レンと。 つまり、私の……旦那様、と…話していたはずなのに。 それがなんだってこんなことになっているんだ、私! つらつらと考えてみるけど、さっぱり思い当たる節なんて見当たらない。 そうだよ。私は今朝…今夜訪れてくるだろうご近所の子供たちに配るはずのお菓子を作る材料を買いに街に出て。 お昼前には全部材料をそろえ終わったから、さあ帰ろうと辻馬車に乗ろうとしていて。 そしたら。 いきなり路地の角を曲がってきた――多分一瞬だったけど豪く豪華なつくりだった気がする――この馬車が物凄い速度で私の傍まで来て。 あっと思う間もなく開かれた扉から伸びた腕にかっさらわれていたんだし。 そしたらそこには見知らぬ男が座っていて。 命令口調で私に向って「座りなさい」と言って。 本当に誰なんだ、この誘拐犯。うーん、絶対に見覚えは、無い、と思う。 多分私とそう年は変わらない風に見える。整った顔立ちに、とても誘拐なんて犯罪を行うようには見えない、やけにのんびりとした、でも爽やかな雰囲気。その姿に私も何だか緊張感がなくなっちゃってはいるんだけど。 これは立派な誘拐だし。 こんな真似をするような知り合いを持った覚えはない。 もっとも突発的犯行だとしたら幾ら考えても無駄か。 だけどそれにしたって。つい一月程前まで私は至って普通の標準的な市民の娘で。今は…至って普通なお勤め人である旦那様を持つ…まあ、若奥さんってやつで…。 そんな私を誘拐して一体何の得がこの男にあるっていうんだろう…。 あ、まさかどこかに売り飛ばされる、とか…?噂でしか聞いたことは無かったけど、そういう商売を生業にしている組織とかもあるらしい、し…。 実際貴族階級の人間が黒幕だったりすることも、ありえるわけで…。 わ、わぁっ!それは怖いってば!ど、どどどうしよう!! どうするどうするどうする!ぐるんぐるん考えながら、今更ながらにとんでもない事態になっているんだってことをひしひしと感じる。 レ、レン…っ!助けてーっ!折角!折角結婚したばっかりなのに!新婚さんなのに!!私どこかに売り飛ばされちゃうかもーーーっ! 自分の考えに没頭しまくって、辿りついた結論に流石に青くなった。 まさに血の気が引くってこういうことをいうんだと思う。 「どうかした?気分でも悪い?」 私のその様子を見て、心配そうに尋ねてくる誘拐犯。 何を白々しく!そりゃ気分も悪くなるでしょう! ああ、でも。迂闊に何か言って刺激しない方がいいんだろうか。 ……もう、充分過ぎるほど迂闊に何か言っちゃっている気はするんだけど。 でも一応これ以上は事態を悪化させたくない。 ふるふると頭を左右に振ってじっと黙り込む。 誘拐犯は何故か面白そうに私を見ていた。 「そう?気分が悪かったら言って。それともう一つ。訊きたいことがあるんだけど。」 訊きたい、こと?私に? や、寧ろ私の方が訊きたい事があるんだけど。 でも今さっき無用な刺激を避けようと思ったばかりだし。 仕方なく 「…何、ですか?」と促してみる。 「―――君、結婚してるの?」 「え…は?」 結婚?結婚、は。してますが。 でも。何でそんなこと訊かれるんだろう。 この場合、やっぱり素直に答えたほうがいいのかな。 えっと。うううう。どうするべきなんだろう。 「素直に答えて。」 私の葛藤をしっかり見透かしたように有無を言わさぬ口調で誘拐犯が言う。 う。何で読まれてるんだ、私の考え。この人なんだか怖い。 びくびくしつつ。だけど、こくっと頷く。 誘拐犯が何故か黙り込んで、次にふうと溜息をついた。 「そう。結婚してるんだ。あんまり関係ないけどね。一応訊いときたかったから。」 あまり関係ない?何と関係ないんだろう? 私が結婚してようがしてまいがこれから起こる事態はかわらないってこと? 私……これからどうなるんだろう。 レン、心配してるかな…。 本当ならもうとっくに家に帰れていたはずなのに。 そっと首筋に触れる。 朝、私が出かける前に…レンが触れたところ。 確かにいつもと同じだった筈の朝。 私はいつの間にかそれを思い返していた。 *** それは朝、家を出る前のこと。 「レン、今日は早く帰れる?」 「ああ。昼前には帰ってくる。」 朝食の席で私が尋ねた質問に、切り分けたパンを口に運びながら。 静かに笑って答えたのは、レン。私の、旦那様。 普段は無愛想でブラックなオーラが漂っているレンが、私と二人きりで居る時にだけ見せてくれる笑顔が、とても好き。 単純だけど、それだけで幸せ気分になれて、自分の意思とは関係なく顔がにやけちゃうぐらいに。 「そっか。じゃあ、私もそれくらいには帰ってくるね?」 へろっと笑いながら、本日の帰宅時間をレンに告げる。 今日はレンも私も午前中、家を空けることになっていた。 私は街に買い物に行く予定があり。 レンはお仕事でとある伯爵家に赴く予定。 腕のいい服飾職人であるレンに対して、仕事の依頼をしてくる貴族は珍しく無く、今日は依頼されたドレスをおさめに行く日だった。 「わかった。…じゃあ、俺はもう出るぞ?」 私より一足早く朝食を終えたレンが席を立つ。 「あ、うん。ちょっと待って。」 大変大変。お見送り。 慌てて私も席を立ってレンの仕事鞄を腕の中に抱え込んだ。 う。重い…。 ずしっと腕にかかる重さ。よたよたと歩く私を見かねたのか、苦笑したレンが、私の腕からすっと鞄を抜き取った。 「じゃあ、いってくる。」 「はい。いってらっしゃーい。」 ぶんぶんぶん。扉を開こうとするレンの背中に向って手を振る。 だけど。レンは何故かそのままぴったりと動きを止めてしまった。 あれ?どうかした? つられて私も振っていた手を止めてちょっと首なんて傾げてみる。と。レンが軽く溜息をついた。 「……ナナヤ、この場合何か忘れてないか?」 扉に手をかけたまま、レンが顔だけ私のほうに向けてくる。 はて?何か忘れてるものなんかあったけ? ちゃんと今日の路銀は渡したし。お仕事道具の入った鞄も今さっき手渡したよ? この上何を忘れてると? ……うん。や…実は一個だけ心当たりがなくもないんだけど…。 でもそれはあえて選択肢から外したいというか…。 だから私はさっぱり思い当たらないという風を装い、パチパチ瞬きしながらレンを見た。 あ。なんとなく…不機嫌そう…。 「ううん、何も?」 ちょっといやな汗をかきつつも、私はふるふると首を左右に振ってみる。 すると。 「いや、忘れてる。」 きっぱりレンが言い切って、扉にかけていた手が私に伸びてきた。 あっという間に腕を引かれて抱き寄せられる。 …ああ!!やっぱり行ってらっしゃいのちゅーか! はっとして。 レンの意図していた忘れ物が何であるかが…確定的になった。 ……というか…。私は意図的に忘れるようにしてたんだけど…。 だって。毎朝毎朝…。そりゃ新婚だけど。そりゃ…軽いちゅーならいいんだけど! レンってば朝っぱらから思いっきり深めなの、するんだもんさ! 挙句の果てにはそれ以上のことをしようとしてきたことも一度や二度じゃないし! 「レン!待っ…っ。」 「待てない。」 一言の下、言い切られ。 私の抵抗むなしくしっかりと顎が固定されて。 レンの唇が、私のそれに…落とされた。 「ん、ぅ…」 どん、と心臓が激しく鳴る。 なんというか…もう何度もしてはいるんだけど…キス…もそれ以上も…毎回毎回すっごく胸がどくどく、する。 レンが色っぽいというか…扇情的というか。 そういうことをする時、凄く意外な一面が垣間見えるというか。 とにかく。どうにもこうにも、私がなかなかこういうことに慣れないのは確かだと思う。 だから。ちょっと…ちょっとだけ不安になったり、して。 だって。つまんない女、とか思われてたらどうしよう、とか。思ったり。 もっと積極的に答えたほうがいいのかな、とか考えるんだけど…どうしたらいいものかわからないし。 滑り込んできたレンの舌。 くらくらしながらも、私はつらつらとそんなことを考える。 と。レンの熱が、急に感じられなくなった。 え?あれ?あ…。 びっくりして見上げれば。レンが不機嫌そうに私を見下ろしていた。 「ちゃんと俺のことだけ考える。」 う。集中してなかったのばれてる…。 ある意味レンのことを考えてはいたんだけど。 でも、確かにキスの最中に考えることではなかったかも。 「…ごめん、ね?」 ちらっと目を上げ、しおっとしながら謝る。 レンが溜息をついて、もう一度私の上に身をかがめてきた。 再び触れる唇。 今度は余計なことを考えずに、レンの感触だけを追う。 深く浅く私の中を探る熱にだんだんと息が上がってくる。 「は…ふ…ぁ、レ、ン。」 「ナナヤ…」 キスの合間。すこしかすれた声でレンが私の名を呼ぶ。 そのたびにぞくぞくっと身体の奥が熱くなるのを感じる。 ん、んん!こ、これ以上は、駄目っぽい! そろそろ臨界点。これより先に進んだら…レン、お仕事に間に合わない、はず! 「だ、駄目…っ、駄目だってば!…お仕事…お仕事間に合わなくなる、から!」 あらん限りの理性を総動員して、ぐぐ、とレンの胸を押し返す。 ギリギリまで私の唇に触れていたレンの唇が名残惜しそうに…離れた。 「―――続きは、帰ってから、だな。」 私を見下ろして、艶っぽくレンが笑う。 …何を言ってるんだか。 やけにポカポカする頬を両手で隠して、むぅっと口を引き結んだ。 「……今晩はハロウィンだから、駄目。おかし貰いに来る子達が来るし。」 「籠に詰めて扉の前に出しておけばいいだろ。」 にやっと唇の端を持ち上げてレンが言う。 「もう!馬鹿なこと言ってないでほら早く行かないと!」 本当にそろそろ時間が来ていた。私はぐいぐいレンの背中を押して扉に向わせる。レンが鞄を手にして、扉を開いた。 ふっと手ごたえが無くなる。 「ん、きゃ!」 急にレンが私の手から離れて、つんのめりそうになった。 けれど倒れる前にレンに支えられ、しっかりと私が身を起こしたところで、レンの手が離れた。 「あ、ありがと。…いってらっしゃい。」 「ああ、行って来る。」 そして、今度こそちゃんと扉を出ていく。 でも、その直前。 レンは素早く身を屈めると、私の首筋に口付けを、した。 *** 「さあ、ついたよ。」 はっと気づけば。馬車の揺れは既に止まっていた。 ばばっと左右を見渡せば、馬車の扉が開き、そこから私を攫った男が手を差し出している。 これはやっぱり降りろ、ということだよね…。 差し出された手をじとっと眺め、だけどこのまま馬車の中にいるよりはきっと逃げる隙もあるかもしれないと、しぶしぶ立ち上がる。 でも伸ばされている腕には掴らない。 扉の前でじっとしていると、諦めたように手が引っ込んで、私は漸く外の空気を吸うことができた。 でも。馬車と地面の段差を埋めるべく据えられた台に足を置いて。 …凍り、ついた。 ―――…なにこの豪邸…。 私の目に映っているのは、豪奢な館。 馬車が止まっているのは、その館の入口に続いている白い砂利道の上。 幾ら入口近くに馬車が止まっているとは言っても。 ぱっと見ただけじゃ、全体の大きさを見渡せない程の建築物って…。 呆然とする私の手が、急に引っ張られた。 うわ、なにす…っ! 台の上から飛び降りる形になって、砂利道に顔から突っ込みそうになる。 でも実際に私が顔を突っ込んだのは……砂利道じゃ、なくて。 「大丈夫?ここは偶に使うだけの別荘だから、小さくて吃驚したでしょう?」 ……は?小さい?何を言っているんだこの男は! しっかりと私を抱きとめている誘拐犯を信じられない気持で見上げる。 なんだか私は、とても厄介で面倒そうな男に攫われてしまった、らしい。 ぐっと足を踏ん張って、誘拐犯を押し戻す。 ぎっと睨みつける私を、にっこりと笑ったままの男が歩くように促す。 私は―――半ば呆然としたまま、屋敷の中へと連れ込まれた。 そして、通されたのは。 幾つもの豪華なソファが並んだ…多分サロンのような場所、だった。 これから私、どうなるんだろう。 ぎゅっと両手を握り合わせて、足の上に置いたそれをじっと見つめる。 とてもクッション性にとんだソファ。それに腰を下ろしてはいても、私の心はさっぱり落ち着かなかった。 でも、それもそのはず。だって、中央に一つだけ置かれたテーブルを挟んで、私の向かい側に誘拐犯が座っている。 「まず、君の名前を。」 誘拐犯が、余裕のある態度で静かに切り出した。 不安に押しつぶされそうな心に活を入れ、どうにか顔を上げる。 そういえば…名前、訊かれてなかったんだっけ。 この男の名前も聞いていなければ、私も名乗った覚えは無かった。 「私が名乗ったら…貴方も名乗りますか?」 「もちろん、名乗るつもりだよ?」 爽やかな笑顔を崩さないまま、男が答える。 「ナナヤ…ナナヤ=シズキ。」 とりあえず、男の名前を知ることが出来るならと、私は自分の名前を偽ることなく告げた。 「ミセス・ナナヤ、か。僕は、ここより南にある土地をおさめている侯爵家の当主アオ=オクニ。」 「…侯爵、様…。」 ああ、やっぱり。支配者階級って感じだとは思ったけど。 間違ってなかったんだ。 それにしても、侯爵だなんて。 恐らく私が普通に暮らしていれば、一生言葉を交わすことなんて無かったはず。 でも―――。益々訳がわからない。 一体その侯爵様が私に何のようがあるっていうんだろう…。 多分私は不信感一杯って顔をしていたんだと思う。 オクニ侯爵が困ったように笑った。 「うーん。困ったな。その顔は私に何の用なのよってところ?」 「はあ。まあ。」 本当に全然検討がつかなかったので、こくりと頷く。 馬車にのっているときは売り飛ばされるのかも、と思っていたけど。 だったらわざわざ別宅とはいえ、自分と関連のある場所に白昼堂々連れ込んだりはしない、様な気がする。 「じゃあ、単刀直入に。―――本当に突然で悪いんだけど。」 「何、ですか?」 やけに溜めた言い方に、嫌ーな予感、がした。 背筋がぞくぞくして寒気がする。 んん、そう。聞きたいけど、聞きたくない、みたな。 けれど、侯爵様の言葉は止まらなかった。 そして次の瞬間飛び出した、それは。 「―――君、僕の愛人になる気はない?」 と、いうのもだった。 「は、ぁ……???」 何を、何を言った今この人。 頭が上手く…私に向けて吐かれた言葉を認識できない。確か…うん。確か… 「うん。だからね。僕の愛人にならない?」 そうそう。アイジンにならないかって…。アイジン…。 つまり愛する人とかくあれなわけで…。愛人、あいじ…。 「…はあああああ????!!!!」 再び私に向けて放たれたとんでもない言葉、それによって何を言われたのか漸く理解する。 この瞬間。私の脳みそはホワイトアウトした挙句、見事なまでに…ブラックアウトした…気がした。 |
| Back ‖ Next ハロウィン・パーティ INDEX |
TOP ‖ NOVEL |
Copyright (C) 2003-2006 kuno_san2000 All rights reserved. |