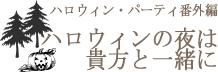 後編 もしも記憶喪失になったら(1) (カップルにもしもの10のお題「05」より) |
「ナナヤさん、ナナヤ、さん。大丈夫?」 肩を軽く揺すられた感触。 意識がフェイドアウトしてから多分しばし。 私はようやく脳みそを手繰り寄せ。引っ張り戻し。 自我を取り戻していた。 は!私、どうしてたんだっけ? 何だか物凄いことを言われたような気がするんだけど。 き、気のせい?気のせいだった? だらだらと嫌な汗を流しながら、一縷の希望に縋ってみる。 でもそれは目の前にいる男により見事に砕かれた。 「いきなりで吃驚したよね、ごめんね?でも僕の愛人になって欲しいんだけど。」 す、少しも悪いと思っていない態度で謝られたって全然嬉しくなんてないーっ!! あああ、しかもしかも。やっぱりさっきのは私の気のせいとかじゃないんだ! 愛人になれって。愛人に………。冗談じゃない!!! 何が悲しくて新婚の身で愛人になんて!しかもついさっき会った男の! 「私!帰らせていただきます!」 すくっと。柔らかなソファから立ち上がる。 これ以上こんなところに長居は無用!とっとと帰ってやる! ここがどこだかわからないけど、なんとかなる…ううん、なんとかするし。 ここにいるのだけは、絶対御免だ。 ぐるっと扉へ身体ごと向き直る。 …でも。 私が向おうとした部屋の出口には…やけに屈強な男の方が一人いたり、した。さっきまでは居なかったはずなのに…。 む、無理だ!あの人に勝つのは絶対無理! これはもう違えようが無い事実。 悔しくて、相変わらず座ったままの侯爵を感情に任せて睨みつける。 「私、帰りたいんですが!」 「いいよ。ただし、これを飲んでくれたら。」 やけにあっさり返された了承。…え、なんだ帰ってもいいの? でも、……飲めって…? 侯爵の指し示した先には、テーブル。 目を向けたそこには、いつの間にか…非常に怪しげな液体が入った、実に上品なグラスが置かれていた。 敢えて、飲み物ではなく液体と称したそれ。 何というか…鈍い光を放つ…ヘドロ色…? おまけに熱を加えてもいないのにぐらぐらと泡立ち、何か、うん、多分爬虫類系の尻尾?みたいなものが、見え隠れしている。 「………これを………私に……?」 再びいやーな汗をかきながら、私は相変わらずにこやかに、かつ爽やかに笑っている男を見た。 「そう。飲んでくれる?」 テーブルに両肘をついて、組んだ手の上に顎をのせ、侯爵様がなんでもないことのように言ってくださる。 飲めるかこんなものーーーっ! 危うくテーブルを蹴り倒しそうな勢いで叫びそうになった。 でもここはぐっと拳を握り締めながら、堪えて。 「…いやです。」 押し殺した声で拒否。 「それは困ったな。それじゃあ、帰してあげられない。なんなら、僕が飲ませてあげようか?」 「もっといやです!!」 ぶんぶんぶん。今度は激しく頭を振って拒絶した。 うう。話が通じない…。頭痛いし、ちょっと眩暈がする。 レンー、助けに来てーっ! もうかなり泣きそうになりながら、必死に頭を振り続ける。 …と。かたん、と音がして。 振っていた頭を止めて見て見れば。侯爵が、立ち上がったところだった。 手には、実に怪しげな液体の入った例のグラスを持っていて。 テーブルをぐるっと廻って、侯爵が私に近づいてくる。 まさか無理やり飲ませる気、とか…? かなり真実味を帯びてきた危機感。侯爵から離れるべく、知らず知らずの内に身体がじりっと後ずさろうとする。 だけど軽い感触が足に触れ、ソファに後退を阻まれた。 間近に来た侯爵に、腕を掴れ引き寄せられる。 「ちょっとやめ…っ!」 「はい、あーん。」 ……ん……く…っ!?何!? 拒否しようと、開いた口。 そこへ放り込まれたのは侯爵が手にしていたグラスの中身―――ではなく、どこに隠し持っていたのか…やはり侯爵の手からではあるけれど…何か丸い物体だった。 驚いて口を閉じた瞬間に、私はそれを勢いで丸呑み。それはもう、吐き出す間もなく。 うわ!本当に何これ!!苦っ!!!しかも何か熱い! 喉を過ぎてどんどん滑り落ちていく、何か。 げほげほと咳き込む私の背中を侯爵がさすっている。 でもそれを振り払うこともできず、私は床へとへたり込んだ。 「ちょ……っ、これ…ごほ……、一体何…っ」 「ああ。それ?実は、君が飲むのを嫌がったあのグラスの中身を固形化したやつなんだ。」 ――――――っ!!!!! ののののの、飲んじゃったーーーーっ! ど、どうし…、や…そもそもこれどんな効果が? でも。でも! にこやかに笑っている侯爵のこの様子…。 絶対にろくでもない効果に決まってる。 ああ、でも! 「解毒剤!解毒剤とか!!持ってるんでしょ!?それ、ください!」 思いつくままに、侯爵の胸倉を掴んでがくがく揺する。 この際、不敬だのなんだの言っていられる状況じゃない。 でも相変わらず笑っているだけの男は、私に大人しく揺すられながら、とんでもないことを、言った。 「嫌だな、解毒剤だなんて。毒じゃないよ?それに効果をなすく方の薬は、実は僕も持ってないんだ。」 そ、そんな薬!使うなーーーーーっ!!!! まさに絶望的。どう、すればいんだろう。 真っ白になりながら、侯爵の胸倉を掴んでしばし呆然。 だけど―――。 呆然とする私の耳に、しっかりと閉じられている筈の扉の向こうから…僅かとはいえ、何か怒鳴り声のようなものが―――聞こえてきた。 「…何?」 「何だ?」 胸倉を掴みあげたまま、そちらを見る。 同時に侯爵もそちらをみたので、どうやら私の聞き間違いではないらしい。 騒がしさはどんどん増してくる。 …あ。この声…。 複数の怒鳴り声の中に、聞き覚えのある、声? そう思った瞬間。私の目の前で頑丈そうな扉が激しい音を立てて開かれた。 あ。あ。あーーーっ!!! 無意識のうちに、ぼろっと涙が零れる。 扉の先頭に居たのは、えらく不機嫌なオーラを垂れ流している見知った人物。 「ナナヤ。」 私を低い声で呼ぶのは…レン。 彼は間違いなく私の旦那様、だった。 「レン!!!」 掴みあげていた侯爵の胸倉を離し、ばっと立ち上がる。 そのまま一直線に私はレンの腕の中へと飛び込んだ。 *** 「何とも凄まじいね。もしかしなくても君が彼女の夫君かな?」 レンの腕の中でほっとしたのも束の間。 私の背後に居た侯爵から声が掛かる。 んん?凄まじいって…何が…? 侯爵の言葉に、ふと顔をレンの胸から逸らして辺りを見回して。 吃驚、した。 長い廊下に点々と。ついでに私たちの周りにも、何やらちょっと襤褸っとした…警備兵さんたちがいて。 でもその殆どは屍累々という感じに床に転がり呻いている。 え、これって。やっぱりレンが…? うわぁ。そりゃ強いとは知ってたけど。それにしてもこれは確かに凄い、かも。 「―――これは俺の妻だ。連れて帰らせてもらう。」 目を丸くする私を抱きしめたまま、レンが静かに言葉を紡ぐ。 でもその静けさには、明らかにレンが怒っているのであろう気配が漂っていた。 「ここから無事に帰れると思う?一応、侯爵家の屋敷なんだけど?」 軽い口調でレンに告げる公爵。でもその内容は剣呑なもの。 レンの腕の中でくりっと首をめぐらせた私の目に、公爵がにっこりと笑いながら肩を竦めている様子が映る。 ……は、腹黒そう…。 ひくっと口元を引き攣られせ、レンにぎゅっと抱きついた。 私を抱きとめるレンの手に安心しろっていうように力が篭る。 「そちらこそ、あまり騒ぎ立てるのは不味いんじゃないのか?」 「……どういうことかな?」 レンの一言に、僅かだけど公爵の声音が変わった気がした。 どういう、ことだろう? レンの謂わんとしている事がわからなくて、首を傾げる。 見上げると、怖いくらいの無表情でレンは侯爵のいる方向を見ていて。 「今こちらの来ているのは、公爵家の令嬢との婚姻話が持ち上がっているからだろう。」 再び静かに、私にとってはかなり衝撃的な事を、言った。 ん、んん!?公爵家令嬢との婚姻話ーーっ! なのに私に愛人になれとかいったのか!! こ、この人、最低だーーっ! レンのシャツを更にきつく握り締めて、侯爵をぎっと睨みつける。 どうやら侯爵も、レンの言葉に少なからず驚いたらしい。 でも完全に動揺しているわけじゃないところをみると、少しはその話が出ることを予測していたのかも、しれないような…気がした。 それでも。私のきつい視線に気づくと流石にバツが悪いのか、苦笑を浮かべる。 だけどそれも僅かの間で、さっと私からレンに視線を移すと…今度は挑戦的な笑みを口元に刻んでいた。 「……へえ、ちゃんと僕のことも調べてきたってことか。なかなか優秀だね。」 明らかに上から物をいっている侯爵の態度に、レンが目を眇める。 まあ、実際普通の市民階級である私たちからすれば、本当にかなり上の階級の人、ではあるから当然といえば当然なんだけど。 これまでなんとなくその辺の意識が曖昧だったのは、侯爵の態度が表面的にはやけに温和だったから、かもしれない。 でも今はその仮面も大分剥がれてるけど。 現にくすくす笑っている侯爵の姿は…とてもじゃないけど、温和になんて見えない。絶対腹に一物隠し持っている気配がぷんぷんする。 でも。そんなことを考えながら胡乱に眺める私の前で、侯爵は突然降参するように両手を広げた。 「…ええと、レン君、だったかな?そんなに怖い顔をするものじゃないよ?何も取っ手食おうっていうわけじゃないし。…僕としても今のこの時期にスキャンダルは困るしね。帰りたいなら、どうぞ?ちゃんと正門から馬車で送り出してあげよう。」 ……え? 突然の侯爵の受諾。あまりに呆気なくて、拍子抜けする。 なんだ、やっぱり貴族特有の気まぐれって奴だったのか。 ―――ううん、もう、何でもいいや。とにかくこれで帰れるし。 ほっと息をついてレンを見る。 だけど。レンはやけに厳しい顔で相変わらず侯爵を見据えていた。 「…レン?」 そっと名前を呼んでシャツを引っ張る。 僅かに私に視線を移したレンは、やっぱりまだ全然不機嫌そうで。 …どうしたのかな。 折角帰れるんだから侯爵の気が変わる前にさっさとここから逃げ出さないと。 その思いを込めてじっと見つめる。 と、しばらくしてレンが諦めたように一つ溜息をついた。 「もう二度とナナヤに構うな。…次は、無いと思え。」 「心して置くよ。」 レンが侯爵に多分最後の一言。それに少しだけ皮肉気な笑みで侯爵が答える。 これできっと、一段落になる、はず。 よかった。大事にならなくて。 安心したのか身体の力が一気に抜けた。 ああ、私ってば大分緊張してたのかな…。 それにしては、なんだか身体がふわふわする気が…。 …あ、れ? 「ナナヤ?」 「レン…何か、変。」 上手くたっていられなくて、レンの腕に両手で掴る。 様子がおかしいことに気づいたらしいレンが、私の腰に腕を回して支えてくれた。 「―――何をした。」 低く、重低音。かなり迫力のある声でレンが侯爵に問う。 だけど、侯爵の態度はまったく今までと変わりなく。相変わらず笑みを浮かべたまま、肩を竦めて見せた。 「さあ、何も?それよりも彼女、具合が悪そうだし、ここで休んでいった方がいいんじゃない?」 「断る。いきなり人の妻を攫っていくような男のところに長居するつもりはない。」 「それは、残念。―――だけど、ただ出会うのが君より遅かっただけで…僕の方が先に彼女と出会っていたら…否、先に彼女を求めていたら、彼女は僕を選んだかもしないよ?」 「仮定なら無意味だろ。」 「そう。仮定だよ。……今は、ね。」 レンと侯爵、二人の遣り取りがふらふらする私の上を通り過ぎていく。 なんだか元々険悪だった雰囲気が更に悪化して行っている気がする、けど。 どうにも頭がぼんやりして…おまけにお腹の辺りを中心にして、やけに身体が熱くって…。 「どういうことだ。」 「さあ、言葉のままの意味だよ?」 一触即発。流石にぼんやりした頭その雰囲気を察することは出来た。 このままここにいれば状況が更に悪化するのは間違いない。 力の入らない手でどうにかレンの腕をひく。 「レン。レン…もう、家…帰りたい…。」 本当に、我が家が恋しかった。油断すると何も考えられなくなる頭を働かせ、必死にレンに訴える。 多分物凄く縋りつくみたいな表情をしているんだろうな、と思う。 だってレンが眉間に浅い皺を寄せて、困ってる、し。 縋りついたまま、レンの言葉をじっと待つ。 しばらくすると、レンの手が私の前髪を掻き揚げ、額に触れて。 安心させるようにそっと撫でてくれた。 少し冷たいその感触がとても気持ちよかった。 「ナナヤ…。わかった。帰ろう。」 「うん。」 こくっと頷く。足元が覚束ない私をレンが抱き上げてくれた。 ふわふわふわ。僅かな振動。このお屋敷の人たちが、遠巻きに私たちを見ているのがなんとなくわかったけど、どうやら侯爵の命令が行き届いているのか、行く手を阻もうとする人はいなかった。 「レン…どうして私がここにいるってわかったの?」 ぼんやりとする頭で、やっぱりどこかぼんやりとレンに尋ねる。 「帰りが遅いから街に迎えに行ったら、お前が馬車に連れ込まれて攫われたと、その場に居た人間に聞いた。後は馬車についていた紋章を頼りに。」 「そう、か。馬車に紋章がついてたん、だ…。」 「ああ。……ナナヤ…ナナヤ?」 感じなれた体温。レンが心配そうに私を呼んでいる。 でももうそれに答えることはできなかった。 いつの間にか私の意識は飛んで――――レンの腕の中で幸せな眠りに落ちていた。 *** ……あれ。ここ…どこだろう? 少し薄暗くなっている室内。ふと気づけば。 私は何故か見覚えの無い寝室にいて。 どうしてこんなところに寝てるんだ、私…? やけに重い身体をどうにか起こして、窓の外を眺める。 茜色に染まる街が見えた。 もう、夕方みたいだけど…。私今まで何してたんだろう。 ああ、大変。とにかく早く起きて夕飯の支度を手伝わなくちゃ。 慌ててベッドから足を降ろす。 すると、がたんと何かが足に当たって。 「あ…っ!」 見たときには、床は水浸しだった。 …しまった。水桶を倒しちゃったんだ。それにして、何だってこんなとこ置いておくのかな、もう。 何か拭くもの拭くもの。 水の零れた部分を避け、扉を目指す。 でも。私が開くよりも早く、それは外から開かれてしまった。 扉を開いたのは、長身で、だけど均整の取れた体つきをした男の、人。 端整な顔だけど、やけに無表情。 ……だけど。 その無表情さは…多分私を見た瞬間に、静かな笑みに塗り替えられた、気がする。 え、と。この人…は?ああ、でもここがそもそもどこなのって話で。 ということは、もしかして私暢気に拭くものなんて捜している状況じゃ…ない…? かなり混乱していたのかもしれない。現状が理解できない程度には。 「ナナヤ、起きたのか。」 ぎっと床を軋ませ、扉を開けた男の人が寝室に踏み込んでくる。 それにも吃驚したんだけど。 今、この人私の名前、呼んだ!? なんで、どうして?だって…ええええ? この事実が、一番私に衝撃を与えていた。 摺り足でじりっと後退する。 私のその様子に気づいたのか、寝室に入り込んできた男の人の足が止まった。 「貴方―――誰?」 かなりの勇気を搾り出して尋ねた一言。 様子を覗う私の前で、扉を開けて入ってきた男の人の笑みは消え、再び無表情という仮面が被りなおされていた。 もう窓の外はすっかり暗くなった頃。 私はついさっき初めて会った男の人と、それに昔からの友人であり幼馴染でもあるユキがいる見覚え無い寝室で、混乱した頭を抱えてベッドの上に座り込んでいた。 あれから…つまり私がここで目覚めた後ってことなんだけど。 見知らぬ男の人は私に何個が質問をしてきて。 それに私が答えると溜息をついて寝室から出て行ってしまい、再び戻ってきた時には、何故かユキを連れてきていた。 そして聞かされた衝撃の事実。 どうやら私はここ一年半の記憶をすっぽり忘れてしまっている、らしい。 「本当に覚えていないのか…?」 「ええ。残念だけど…綺麗さっぱり。貴方と会った一年半前からの記憶が無いわ。」 私が座っているベッドの横で、ユキが溜息混じりに言葉を吐き出した。 壁に凭れかかっている見知らぬ男の人―――ユキの話ではレンと言うらしい――が、真っ直ぐに私を見据えてくる。 何だか無表情で怖い人、かも。 なのに…この人が私の旦那様、だなんて。 そう、なんと。私はまったく覚えていないって言うのに、結婚まで済ませちゃっているらしくて。 だけどそれは結構半信半疑、なんだけど。 でもユキが私に嘘をつく理由なんてないし。事実、ユキと話したり微妙に変化してる世の中の状況を確認して、この一年半の間の記憶が抜け落ちているらしいことはなんとなく自覚しちゃったし。 だけどだけど!やっぱり覚えてないし! そんなにじっと見られたって思い出せないものは思い出せないんだってば! 逸らされること無く私に向けられるレン――さん?の視線がとっても居心地悪い。 思わずユキのブラウスの裾をきゅっと握って、私の傍にあったその細い体の影に顔を隠す。 うう、困った。一体どうすればいいのかなぁ? 父さんと母さんのいるお家に帰りたい、かも…。 「―――ナナヤ。」 壁から身を起こしたレンさんが私の傍まで来て。顎を、つかまれた。 凍りつく私を、眇めた目でレンさんが見ている。 ヤダ、怖い、んだけど…。 「ちょっと!今の貴方はナナヤにとって見知らぬ男なんだから。怖がらせないでちょうだい。」 レンさんの腕を拒絶することも出来ずいたら、ユキが庇うように腕を伸ばして私とレンさんとの間に立ちふさがってくれた。 緊迫した空気。 ちょっとドキドキしつつ見上げていると、レンさんが諦めたように私から目を逸らし、ついでに顎も離してくれた。 ああ、よかった…。 でもほっとする私とは対照的に、レンさんは…なんとなく…機嫌が、悪そう、な…? そうはいっても本当に何も覚えて無いし。 私にとっては今日はじめて見た男の人、なわけで……。 ああ、うちに帰りたいーっ。ここじゃなくて、父さんと母さんの居る家。 ……うん!やっぱり今日は家に帰ろう。 レンさんだってこのままじゃ気詰まりだろうし。ちょっと距離を置いて冷静になれば私も何かしら思い出すかも、だし! レンさんにそう言って、帰して貰おう。 心の中で拳を握り締めて、固く決意する。 だけど。 「…悪いが、今日はもう引き取ってくれ。」 ぱかっと口を開いた私の前で、レンさんが冷静な声でユキに言った。 「え、えええ!?」 レンさんの言葉に驚愕の声を上げたのはユキ―――ではなく、私。 だって!ユキが帰ったら私この人と二人きりになっちゃうわけで! そんなの絶対無理! 多分きっと物凄く情けない表情になっているだろう顔を上げて、ユキを見上げる。 ユキは少し眉根を寄せて、私とレンさんの両方を交互に見て。 最後に、私に対して少しすまなそうな目を向けた。 う、なんとなく…嫌な展開…。ま、まさか、帰っちゃうの!? 「ナナヤ、ごめんね…今日は一旦帰ることにするわ。…私じゃ手負いの獣を懐柔するのは無理みたい。」 的中した予感。ちょっと涙ぐみそうに、なった。 ん?でも最後の言葉…手負いの獣って…えっと、もしかしてレンさん、のこと? 手負いってことは…怪我しているってことだよね? そりゃ、迫力があって多少怖い。でも見ている限り冷静っぽいんだけど。 「ナナヤ、じゃあ私帰るわね?大丈夫?」 うんうんと私が頭を悩ましている間に、ユキは外套を羽織り帰り支度を整え終えていたらしい。 「え、あ。ちょ、ちょっと待って!」 扉から出て行こうとするユキの後を追い、急いでベッドから飛び降りる。 寝室の扉を潜りざま、レンさんに向って「ごめんなさい!少しユキと二人だけで話がしたいの!」と告げ、ユキに続いて家の外へ出た。 茜色だった空はすっかり闇色になっている。 聞いたところのよると、今日はハロウィンらしくって。 いつもの夜より大分賑やかだ。 私がユキと二人で少しだけ話したいって言ったので、レンさんは家の中。 ぱたりと扉を閉めて、家の中に話し声が聞こえないようにする。 そのうえで、どうしてももう一度確認したいことがあった。 「あの…ユ、キ?」 「なぁに?」 明かりの灯ったランプを手に、ユキが黒い外套のフードをすっぽりと被りながら小首を傾げる。 その様子は文句無く可愛いかった。…なのにどうしてユキが一人身で、私が先に結婚なんてしちゃってるんだろうなぁ。どう考えてもユキの方が先に結婚するって思ってたんだけど。 「本当にあの人、私の…その。」 ―――夫なの? なんとなくその単語が気恥ずかしくて、曖昧に言葉を濁していると、察してくれたらしいユキが苦笑いを浮かべた。 「ええ、認めたくないけど、本当。―――ナナヤのお父さんが大分反対して…結構な大騒動だったのよ?また綺麗さっぱり忘れちゃったわねぇ。」 「そんなこと、いわれても。」 私には忘れているっていうこと自体さっぱり実感が無いわけで。 ああ、でも父さんには反対されたんだ。うん、なんとなく想像できるかも。 家の場合、母さんはかなりおおらかというか…大雑把というか…まあ私が誰を選んだとしても、自己責任よという一言で済ませそうだけど、父さんはその辺り厳しかったもんなぁ。 「まあ…、なんだかんだと言ってもナナヤが無くしてる記憶の大半を占めているのはあの人だもの。また一緒に居れば何かの切っ掛けで思い出すかも知れないし。だけど何か変なことされそうになったら容赦なく蹴飛ばして私のところにいらっしゃいね?…私の今の家はあそこ。」 ふんわりと笑いながら、5軒ほど先にあるレンガ造りの一軒家を指差す。 今もご近所さん、なんだ。うん。それならちょっと安心。 こくりと頷く私の肩を、励ますようにユキがぽんと軽く叩いた。 「じゃあ、私帰るわね。明日また来るから。」 「……うん。待ってる。」 ユキが手にしたランプの明かりが遠ざかっていく。今日はハロウィン…。まだまだ宵の口である今の時間、子供たちは元気に駆け回っている。 お菓子かいたずらかと、これから家々の扉を叩いて廻るんだろう、な。 ああ、それにしても。ユキが帰っちゃって不安、だ。 |
| Back ‖ Next ハロウィン・パーティ INDEX |
TOP ‖ NOVEL |
Copyright (C) 2003-2006 kuno_san2000 All rights reserved. |