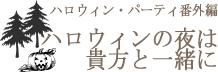 後編 もしも記憶喪失になったら(2) (カップルにもしもの10のお題「05」より) |
ぱしん、と肌の触れ合う乾いた音が響いたのは、私がテーブルの中央に置かれた籠からパンを取ろうとした直後だった。 「…あ。」 小さく、声が漏れる。 手を上げたままの状態で固まりながら、たらたらと冷や汗が流れるのを感じた。 思いっきり、振り払っちゃった、よ…。 そう。私と同じようにパンを取ろうとしてたレンさんの手が私に触れて。 咄嗟に、本当に思わず…振り払っちゃったのだ。 これは流石にまずかった…? 「ご、めんなさい!」 僅かに目を瞠って…驚いているらしいレンさんに対して慌てて謝る。 でも「いや…」と静かに言うと、あっという間に何事も無かったかの如く、レンさんは再び食事を開始してしまった。 …どどど、どうし、よう。とっても空気が重い…、気が…。 俯いて、じっとテーブルを見つめる。 だって、怖くて顔を上げられませんってば。 でも。いつまでもテーブルと睨めっこしていてもどうなるものでなし。 私はどうにかなけなしの勇気を掻き集めると、そっと顔を上げてみた。 そこには相変わらず黙々と食事を続ける男の人が一人。 うう、なんていうんだろう…。この人、私が居ても居なくても別に構わないんじゃないのかなぁ…。 じっと様子を覗っていると、物凄くそう思えてくる。 何でこの人は私と結婚したんだろう、とか。本当に私のことが…その、スキ…なのかな、とか。 私はこの人のことがスキだったのかな、とか。 …………。 ああ、もう!ダメダメ! 幾らこんなことを考えてみたって、何も思い出せないし! ぐるんぐるんと思考の迷宮に嵌り込みかける頭に喝を入れ、丸まり気味だった背をぴんと伸ばして。 「あの…っ!」 食事を続けるレンさんに声をかけた。レンさんの手が止まる。 そして。ゆっくりと顔を上げたレンさんとふと目が合って。 どくんっと、心臓が鳴った。 ……え、ええ?な、何是?? 何でこんなに心臓がばくばくいうんだ、私! あれ、頬が何となく熱いような…えっと…え、ええ? 「ナナヤ?」 声を掛けたにも関わらず、何もいわない私を不審に思ったのか、レンさんがさらりと私の名前を呼ぶ。 その途端。更に鼓動が早くなった気が、した。 心臓が痛いくらいに鳴り、頭がくらくらする。 だ…っ、これって私、何か病気!? いやでも記憶にある限りじゃ、こんな症状が出たことは無くて。 ということは無くした記憶の間に何か病気に掛かってたってこと? でもユキはそんなこと言ってなかったし。 ああ、益々訳がわからない! 動揺しまくり、またもやぐるぐる回り出した頭を抱えて、がたんと席を立つ。 「私やっぱり家に…っ」 ―――帰ります! 何故かとっても焦りまくりながら、それでもどうにか発しようとした私の言葉が終わる前に。 「ここが家だ。」 レンさんはきっぱりはっきりと簡潔な答えを返してくれ、た。 や、そうじゃなくて! どうしたら伝わるのかなぁ。 いまいち意思の疎通が出来ていない相手に対して、どういえばいいのか、うんうん頭を押さえながら考える。 と。考え込む私の前で、レンさんがやけに無表情に。 お皿の上にからりとフォークを投げ出した。 がたっと椅子が引かれて。 私の旦那様らしい人が、立ち上がり。 何故か私の足が、床から離れて。 抱えあげられちゃったりなんか、していて。 んんん!?な、何この状態!! あっという間の行動に、抗議する暇さえなかった。 乱暴に寝室に続く扉が開けられて、一人で眠るには大きすぎるベッドの上に投げ出される。 ベッドに、押さえつけられた。 二人分の重量で、木製のそれがぎしっと軋む。 開けられた扉から僅かにもれてくる明かりで、私に圧し掛かっているレンさんが無表情であることだけは、少しわかった。 「忘れた…?その上、家に帰る…?そんなこと―――認めない。」 感情の籠もらない声で、告げられる。 それが、怖かった。冷静そうにみえる、のに。なのに。 どうして、この人が怒っているってわかってしまうんだろう。 「や…っ!ちょっとま…っ、は、離して!!」 だけど。そんな疑問も瞬時に吹っ飛んだ。 何でって。手が…!手が…っ!ど、どこ触って…!? 「ん…んぅ…や、ぃやぁ…」 スカートの裾から入り込み、私の足を這って来る感覚に抗議しようとして、でもそれは叶わなかった。 レンさんの唇が私のそれに重なって、きたから。 それでも私は唇を固く引き結んで必死に抵抗していた。 「…ぁっ!」 でも、足の間に滑り込んできた手に驚いて声を上げた隙に、するりと口の中に入り込んできた熱により、私の抵抗は呆気なく崩れてしまって。 や…っ!や!何、これ…。身体が痺れる。甘くて。頭が溶けそう。 どうして?こんな…全然無理やりで、嫌なはず…っ。 なのに。身体だけは、しっかり触れてくる手に反応して、いた。 私…どうしよう。こんなの…嫌。覚えてないのに! 心が、全然ついていっていないのに!! がりっと。音が―――正確には、私の歯に感触が、した。 口の中にじんわりと広がる鉄の味。…血、の味。でもこれは私のものじゃなくて。 私の上で上半身を起こしながら、レンさんが手の甲で唇を拭っていた。 ―――か、噛み付いちゃっ…た。 私に圧し掛かるレンさんを呆然としながら見つめる。 逃げ出さなきゃ、と思っても身体が上手く動いてくれない。 「………せる。」 レンさんが少し目を細めて、小さく何かを囁いた。 聞き取ることが出来なくて、反射的に私は「…え?」と気の抜けた声を上げる。 「…どんな手段を使っても…思い出させる。」 呟かれた声は低くて。…酷く、怖かった。 それから先―――は、自分の身に何が起こったのか良く分からない。 冷たい手がブラウスの中に入り込んできて私の胸を弄って。 とっくにたくし上げられたスカートからのぞいている足にも、同じように冷たい感触がした、とか。 挙句には、薄い布越しとはいえ…その…足の付け根の間を擦り上げられちゃったりと、か…。 だけど。 私の忍耐はきっぱりはっきりもう限界、だった。 「―――――っ!?―――や、あ!や、お願い…っ、止めて、レン、さん!」 レンさんの指が私の中心に触れた瞬間。叫んだ。 押さえ込まれた手足に力を込めて暴れる。…もちろん、実際にはレンさんの力に敵わなくて、全然動かせなかったんだけど。 目の奥がとても熱くて。瞼の裏が痛くて。気づいてみれば頬が冷たくて。 それは零れ落ちた自分の涙。理解したのは、切なげに目を眇めたレンさんが、私の涙を指で拭った時だった。 「本当に何も…覚えていないんだな…。」 低く感情を抑えた声。でもそこに僅かだけ宿る苦しげな響き。 私を押さえつけながら。酷いことをしているのはどうみてもレンさんの方。 …なのに。なの、に…ちくちくと心が痛む。 自分がとっても悪いことをしているような気がして、罪悪感がむくむくと湧いてくる。 うう、なんだかこれって不条理、だ。 「…頼む…思い出してくれ…。」 私の見下ろしながら、レンさんが小さく呟く。 「……っ!」 どくっとまた心臓が、鳴って。ずきん、と痛んだ。 うわ、また!どうしちゃったんだ、私! この人に―――レンさんに今日会うまでは感じなかった胸の痛み。 これってどういうことなんだろう。それに、この人は―――どうしてこんなに私を求めてくれるんだろう。 さっきは、私のことなんて居ても居なくてもいいみたいだと、思ったんだけど。 でも今は全然違っていて。 どうにも出来ない胸の痛み。 自分がわからなくて、戸惑う。 私の肌に触れている少し冷たい感触にクラクラした。 「……ナナヤ…?」 私が抵抗を止めた所為か、 訝しげな問いかけと共に、レンさんの腕の拘束が少し緩む。 …え、あ…、これってチャンス?今なら、逃げられる? でも、逃げちゃっていいの、私?この人を置いて逃げて…いいの? 迷う。本当なら迷うことなんて無いはずなのに。一目散に逃げ出して良いはずなのに。 ああ、でも…でも!やっぱり今のこの状況は、なんかダメだ! 「ごめ、んなさい!!」 結論を出した私は、緩んだ拘束から抜け出し、レンさんから逃れ、ベッドから身を起こした。 「ナナヤ…ッ」 扉へ駆ける私の背後からレンさんの声。 でも、私は振り返ることなく、ぐちゃぐちゃな気持を抱えたまま無我夢中で家を飛び出していた。 *** 街には、ジャック・オ・ランタンを持ち、様々な仮装をした子供たち。 私はその流れを見つめながら、ふらふらと道を歩く。 結局、まとまらない…わけのわからない気持はそのままで。 何気なく唇に触れると、口付けの感触が蘇ってきたりして。 そして足を止めたときには、人気の無い本当に小さな森の境目辺りに辿り着いていた。 …あれ?ここってもう街外れだ…。 いつの間にこんなところまで来てたんだろう。 でも気づいてみれば、すっかり身体は冷え切っている。 草の上に座り込んで膝を抱えて。 ユキの所に行けばよかったと今更ながらに後悔した。 でも飛び出した時は、もう何も考えられなくて…とにかくあの人の傍から離れたかった、から。 ―――切なげに揺れていた、瞳。自意識過剰…なのかもしれないけど。 とても求められている、と思った。もっと触れ合って、あの人に…レン、さんに笑って欲しいって、思った。 やっぱり私はあの人のことが好きだったのかな。 全然覚えてはいないんだけど。それに、実は私は恋をしたことが、無いんだけど。彼に…恋したのかな。彼のことを好きになったのかな。 でも、誰かを特別に好きになるって…よくわからない。 父さんも母さんもユキも皆、好き、だけど…特別な一人への好き、とはやっぱり違うのかな。 「はぁ…。」 溜息をついて、ぼんやりと街の明かりを見つめる。 少し遠くの方では、群れているランプの明かりも見えた。 ああ、ハロウィンの行列、か。 無邪気に駆け回っているのだろう子供たちの姿を想像すると、こんなところで座り込んでいることがちょっと寂しい。 …戻ろう、かな。 殆ど無意識の内に思って、慌てて頭を振る。 今更、戻れないよ。逃げてきちゃったのに。 どうしよう。 途方にくれながら再びランプの明かりに目を向けて。 …あれって思った。 何故かランプの明かりが一つ。こちらに向けて進んできていた。 え、何?まさか…レンさん、とか? おろおろしている内にも、どんどん明かりは近づいてくる。 だけどそのうち、レンさんでは無いらしいことに気づいた。 男の人ではあるけれど、レンさんより少し線が細い。 どうやら仮装をしているようで、頭の上に二つの三角。 犬…かと思ったけど、これは狼男、かな? 座り込んだままの私のすぐ間近。 やってきたその人がにっこりと笑った。 「こんばんは。」 「え、はい。こ、こんばんは?」 穏やかな、人のよさそうな笑みに油断して、ついうっかり受け答えをしてしまう。 でも今日はハロウィンで、見知らぬ者同士でも挨拶ぐらいは交わしてもおかしくないし。 「トリック・オア・トリート?」 にっこりと爽やか笑顔のまま、その人が言う。 え、トリック・オア・トリート…と言われても。 今何も持っちゃいないってばさ。 「…えっと、ごめんなさい…私、何も持ってなくて…。」 ひらひらっと両手を広げて何も持っていないことを示す。 「うん、それでも構わないんだ。かわりに、しばらく僕と一緒に居て欲しいんだけど?」 「え…?」 一緒に…と言われても。 それはこのまま此処で座り続けるって意味? 「駄目、かな。」 ああ、そんな懇願するような眼で見られても。 それに男の人とこんなところでこんな時間に二人っきりでいるってまずいんじゃないの、か?やっぱり。 「あの、私…私…。えっと…。」 「それとも僕といると好きな人に悪い、かな?」 …好きな…?好きな人って…。そんな人は別に…別に…。 「好きな人なんて…」 ―――いません。そう言う筈だったのに。 あ、れ? 脳裏に浮かんだのは、えらく無表情な顔。 どうしてだろう。あんなに怖い思いをしたはずなのに。 今思い浮かぶのは…好きな人って言われて思い浮かぶのは、あの人のことだけ。 拒絶した時…わかりにくかったけど…だけど確かに傷ついた眼をしたあの人のこと、だけだった。 どうして…どうしてなんだろう。でも、確かめたい。この気持を…確かめたい。 今、会えば何かわかるかもしれない。あの人に、会えば。 思い立ったが吉日とばかりに私はがばっと立ち上がる。 だけど駆け出そうとして、腕をつかまれた。 あ、しまった。そうだこの人が居たんだっけ。 私の腕を掴んでいるのは狼男さん。 変わらない笑顔はある意味表情が読めない、かも。 「…行っちゃうんだ?」 「ごめんなさい…っ!」 謝るところなのかは良く分からなかったけど、何となく申し訳ないような気がしてぺこっと頭を下げた。 「―――損な役回りだね、僕。好きな人なんて居ないって台詞が聞きたかったんだけどな。何も覚えていなくても、君は彼を選ぶんだね。久々に、本気で欲しいと思った子だったんだけどな。」 頭上から声が降ってくる。 ん?何だか随分意味ありげなことを言われている、ような? 「……?それってどういう…?」 頭を上げ、真正面から狼男さんを見据える。 少し眼を伏せて笑んでいるこの人に、私は前に会ったことが…? 「本当ならここで押し倒しちゃいたいところだけどね。―――いいよ、行って。だけど君の記憶は奇跡でもない限り戻ることは無いから。」 「貴方―――何か知って…?」 「さあ?」 …私の中の危険信号が点滅する。そりゃもう真っ赤な上にけたたましく鳴りながら。 絶対に、この人なにか知っている。…知っていると思う、けど。 近づいたらいけない気も、する。 掴まれていた腕をぱっと振り払う。 それは案外すんなり外れて、後にはあははと笑う狼男さんと、強張っているであろう顔でじりじりと後退する私の姿。 「そんなに警戒しなくてもこれで消えるよ。それじゃあ、ね。あ、でも、僕もまだ諦めたわけじゃないから。それだけは覚えておいて?」 「え、え?ちょ…っ!」 困惑する私の前で踵を返した狼男さん。 その姿は来た時と同じようにどんどん遠ざかっていく。 行っちゃった…。一体なんだったんだろう…。 …いやいや、今はそれよりも、戻らないと…! 戻らないと…戻らないと…なんだけど。 なんだか気勢がそがれた、というか、ね? うう、今の狼男さんとの遣り取りで、さっきの勢いがすっかり無くなっちゃったよ。 戻りたいんだけど―――勇気が出ない。 戻ってもいいのかな、と思う。 だって…私はあの人のこと思い出せていない。 会って、自分の気持を確かめて…また、拒絶したちゃったりしたら、傷つけちゃうんだろうか…。 でも。簡単に…その…さっきレンさんにされたみたいな行為を受け入れるっていうのは、絶対無理だし。 ううー。どうすればいいんだろう…。 うんうんうんと、立ったまま頭を抱えて悩んでみる。 もちろん幾ら悩んでも答えは出るはずもなく。 途方にくれて。 いきなり、ぐいっとスカートの裾が引っ張られたのはそんな時だった。 驚いて、ばっと下を向く。 「――――んん?」 私のスカートを握り締めているのは、多分まだ5〜6才の女の子。 その子のすぐ傍には、ジャック・オ・ランタンを手にぶら下げた、やっぱり同じくらいの年頃の男の子がいた。 「えっと?…あ、もしかして迷子になっちゃったのかな?」 座り込んで目線を合わせた私を見て、女の子がふるふると頭を振る。 ありゃ、迷子じゃないのか。それじゃどうしたのかな? 「…あのね、忘れ物、したでしょ?」 首を傾げたままの私に女の子がぼそりと言った。 うーん。無表情だけど、凄く可愛らしい子だなぁ。 なんてことを暢気に思いながら、言われた内容に更に首を傾げる。 「んん?」 忘れ物…はて、忘れ物なんてしたっけ? 「大切な忘れ物。」 「うん、と…?大切な?」 女の子がこくっと頷いて、それきり黙りこむ。 わけがわからなくて、頭の中にクエスチョンマークが飛び交った。 すると、その様子を見兼ねたのか、男の子が焦れたように口を開いた。 「ああ、もう。言葉足りなさすぎ!…あのね、それをね…つまり大切なものを僕たち拾ってきたの。だから、返すね?」 初めの部分は女の子に向けて。 最後の部分は私に向けて、男の子が元気一杯に言う。 「え?」 何?返すって…何を?? 呆気にとられたまま、多分間の抜けた顔をしているであろう私の前で。 ぽん、と男の子の持っていたジャック・オ・ランタンが煙を吐いた。 !?な、何?煙たっ!! 目の前を覆う、白い煙。それがもくもくと私を包み込む。 煙たくて、ごほごほと咳き込みながら煙を払おうとぱたぱた手を振って―――。 …何だろう、これ。 煙の中…っていうのかな。ううん、煙に何か映っている、みたい、な? 涙の滲む眼を凝らしてじっと見つめていると、そこには…レンさんが映っていて。 優しく笑っている、顔。とても懐かしくて、とても温かくて…。 そう…そう、これは私の大切なもの。 どうして忘れていたんだろう。どうして忘れることが出来たんだろう。 レンに、告白された時のこと。初めてのキスもその時だった。 ―――全部、ハロウィンの夜に、はじまったんだ。 「ナナヤ!」 「……あ…。」 薄れていく煙の中、へたり込んでいる私に駆け寄ってくるのは大柄な人影。 レン。 私を捜してくれていたのか…息が乱れている。 私の前まで来て足を止めたレンは、鬱陶しそうに額に掛かる髪を振り払った。 「―――悪かった…思い出してくれなくても、構わない。それならもう一度最初から始めればいい。だから…俺の傍に居てくれ…。」 呆然とする私の頬にそっと触れ、レンが低く囁く。 胸が締め付けられた。貰えた言葉が嬉しくて。忘れていも構わないって。もう一度やり直そうって…そう言ってもらえるたことが嬉しくて。 …ごめんね。ほんの少しの間とはいえ、レンのこと忘れちゃうなんて。 私の前で片膝をついて屈みこんでいるレンの身体に両手を回して、きゅっと抱きつく。一瞬、レンが身体を引こうとしたのを感じたけど、構わずにそのまま抱きついていた。 …あ。でも、さ。そこまで言ってもらって…。 えっと。うぁ…。ど、どうしよう。お、思い出したーなんて、い、言い難い、かも。あああ、でも黙っているわけにもいかないし! たらりと冷や汗を流しつつ、抱きついているレンの背中を軽く叩いてみる。 レンが何だって言うように私を離して、顔を覗き込んできた。 「えっと…レン、さーん。あのー…、その、ね?レ、レン…?とか言ってみたり…?」 誤魔化し笑いを浮かべながら、しどろもどろにレンを呼び捨ててみる。 レンが、僅かに目を瞠って。 「―――まさか、思い出したの、か?」 「…うん。思い出した、みたい。」 あ、ははは。 黙り込んでしまったレンの前で、乾いた笑い声をたてる私。 わぁ、空気が重。 笑い顔のまま凍りつく。 だけど突然、レンはきつく私を抱きしめた。 え、うわ!苦し…っ!え、え!? レンの口元が私の耳に近づく気配。吐息が掛かって、ぞくっとする。 でもそれは嫌、じゃない。とても慣れた感覚。 まるで何かを確かめるみたいに、片方の手が私の背を撫でる。 それに、もう片方の手は髪の中に入り込んできて、くすぐるみたいに私の後頭部に指を這わしていた。 「―――…本当に、思い出したのか…?」 レンが、静かにそっと私の耳元で囁く。 耳元で喋られると少し、くすぐったい。 ちょっと身体をずらしたくて、レンの問いに答える前に身じろぎする。 この状態だとレンの顔が見えないし、と思ったんだけど。 でもすぐにレンの手がその動きを牽制するみたいに、私の顔を上向かせた。 うわ、ちょっと強引、かも?そりゃいつも多少なりとも強引だけど。 もしかして私が逃げるとでも思ってる? 「ちょっと、レン…っ」 強引過ぎるってば、と。文句を言おうとして、でも―――言えなかった。 だって。レンってば、凄く不安そうな顔、してるんだもん。 多分他の人が見たらそんなに普段と変わりないって思うかもしれないけれど…でも、うん。間違いなくレンは不安げだった。 「…レ、レン…?」 身じろぎすることも忘れ、私はレンの腕に掴りながらやや呆然とした。 そのまま、少し開いた唇にレンの唇が重なってくる。 レンの唇は、冷たかった。 どれだけ私のことを、捜してくれたんだろう。 ごめんね…。 心の中で小さく呟いて、レンの首に手を回して抱きついた。 レンの口付けは―――段々と深くなってくる。 申し訳なさも加わり、私は口内に入り込んできたレンの舌に積極的に答えるよう、頑張ろうとして。 唇よりは数段熱いレンの舌に自らのそれを絡めて。 くすぐったいような、ジンと痺れるようなふわふわした感覚。 湿った音が触れ合ったそこから漏れてくる。 その音が耳について。頬が熱くなって。 だから、そのうちにレンの重みが私に圧し掛かってきたことに気づいても、一杯一杯でどうにも出来なかった。 ん…んん!? 重みに耐えかねて、草の上に座り込む。 相変わらず唇は重なったままで、仕方なく両手を回してしがみ付いている広い背中を引っ張って意思表示をしてみたんだけど、全然効果はなし。 しかも唇が離れた時には、レンの脱いだ上着の上に押し倒されていた。 「そ、外だし!」 レンの胸に手を突いて抵抗するも、易々と封じ込められる。 「外だな。」 いやいやいや、そうでなく! 「寒いし!」 「だから熱くなることをするんだろ?」 ええええ!?なんかそれは違う!違うーっ! あ!ああ、そうだ!それにもう一個!さっきから実はとっても気になっていたりしたんだけど! 「あの、女の子と男の子!見なかった!?」 押し倒されて、口付けられて。でもその合間に必死に尋ねる。 そう、あの子達。全然姿が見えなくって。本当に何処行っちゃったんだろう。迷子じゃ無いとは言っていたけど。 私の必死さが伝わったのか、レンがキスを中断して、少し考え込む。 でも答えは「いや?見てないな。」というものだった。 ううーん。やっぱり。 多分私が思い出せたのってあの煙のお陰だと、思うんだけど。 「…ナナヤ、最中に考え込むな。」 不機嫌そうなレンが再び私に口付ける。 え、や…ちょっと! 「ちょっと…待って…っ!え、わぁ…っ!」 ガサガサっと草が擦れあう音。 私の懇願虚しく、レンはすっかりその気だった…。あう。 *** レン&ナナヤの甘ラブをご覧になる場合は→ こちら をクリック(R-16) ご覧いただかなくてもお話の流れ的にまったく支障は無い部分ですので、苦手な方はまるっと飛ばして↓へどうぞv *** 「……うー、レンの…阿呆…」 恨みがましさを若干込め、まだ気だるさの残る体で座り込んだまま私はぼそっと呟く。満足げなレンの静かな笑みが、今ばかりはちょっと悔しい。 でも、何とかレンに乱されたブラウスの前を留め、身支度を整える。 レンが手伝おうかと申し出てくれたけど、丁重にお断りした。 だって、手伝うとか言っておきながら、そのままもう一回…なんてことが過去に数回。私だって学習するってものだ。 どうにか服を着て、私が下敷きにしていたレンの上着についた落ち葉をパタパタと払う。 もう身支度を整えて立ち上がっているレンにその上着を差し出した。 ちょっと笑いながらレンが手を伸ばしてくる。 でもレンは上着を受け取らずに、私の腕を掴んで立ち上がらせてくれた。 しかも、私が手にしていた上着を受け取ったと思ったら、何故かそれを私に着せてくれて。 多分、着替えている途中、すっかり汗の引いた体が冷えてきたせいか、何度かぶるっと身震いしたのに気づかれていたのかも。 「えっと…、ありが、と」 「どう致しまして。じゃあ帰るか」 こくっと頷く私の手を、レンが引いた。 少し冷たい手。手を引かれて歩くなんてちっちゃい子みたいだな、とは思ったんだけど、何だかとても離しがたくて、私は大人しくレンの後を進む。 もう喧騒のピークは過ぎたらしい街中は、大分落ち着いてきている。 その中を歩きながら、改めて今日はハロウィンだったんだなと思い出した。 うーん、本当に今年は何も出来なかったなぁ。 や、何というか今までの人生でしたことの無い経験は出来たんだけど。 「うー、来年こそはちゃんとお菓子を作って、ちゃんとしたハロウィンをしたい。」 情けなく呟く私を見てレンが小さく声を立てて笑う。 「そうだな。」 「うん。後、ね…やっぱりまたこうやって二人で居たい、な。」 最後の方は、ちょっと小さめに。こっそり呟いて。 でもレンはちゃんと聞いていてくれたらしい。 「来年はもしかしたら二人じゃなくなってるかもしれないけどな?」 意味ありげな視線を私に向け、唇の端だけで薄く笑う。 「ん?」 訳がわからずに首を傾げていると、レンがくいっと顎を上げ私のお腹の辺りを示した。 お腹…?お腹……。あ。ああああ!!!そ、そういうこと!? 「あ。そっか…。うん。そういうこともありえる、よね…。」 実は…レンの…そのさっきの余韻…というか。 それが歩いていると偶に足の間を伝ってくる。 一応…綺麗にはしたんだけど…。だから当然赤ちゃんができる、という可能性はありすぎるくらいあるわけで。 「まあ、頑張ればな。」 が、頑張るって何を!? 「もう!頑張らないってば!」 真っ赤になっているだろう私の頬。 両手で押さえると案の定、とても熱くて。 隣ではレンが低く笑っているし。 うう、一人動揺しているのが馬鹿みたい。 夫婦…なんだし。恥ずかしがることも無い、とは思うんだけど。 でもやっぱりいきなりそうすっぱり気分を切り替えて、夫と妻っていうものになることはできないというか。 だから、うん。のんびり私ペースでいいや。 無理してみたところで、私じゃ絶対に上手くいかないと思うし。 むう。それにしても赤ちゃん…赤ちゃん、かぁ。 なんだか実感、ないんだけど。 「……あのさ…赤ちゃん…出来るとしたら…女の子と男の子、どっち、かな?」 あくまで仮定、ではあるけれど、何となく聞いてみたくなった。 「どっちでも。…何なら両方でもいいぞ?」 「両方!?」 レンが笑いながら肩を竦める。 …んんー、でも…。 でも、そうだよ、ね。家族は多いほうが楽しい、し? 私、一人っ子だったから実はちょっと兄弟って憧れだったんだ。 「…うん。家族は多いほうが楽しいか。」 何だか気恥ずかしくて、下を向きながら只管歩く。 レンがそんな私の手を少し強く握った。 「ところでナナヤ」 「ん?何?」 顔を上げると、レンの横顔。 私の方は見てはいなくて、何を聞かれるのかなと思いながら見つめていると、不意にレンが切り出した。 「記憶が無くなった原因について思い当たることは?」 …う。今更そこを突かれるとは。 そりゃ、まあ。思い当たる原因といえば、アレしか無いわけで。 「え…、えっと………多分、なんだけど、ね?その…侯爵様のところで得体の知れない固形物を食べさせられた…から、かなー、なんて」 あははは、と笑う私をレンが呆れ顔で見ている。 あう。不可抗力なのに。そりゃ、自分でもちょっと迂闊だったなぁとは思ってるんだけどもさ。 「―――もう、当分一人で外出するなよ?」 レンにぼそっと言われた。 今回の件ではかなり迷惑をかけちゃったので、反論できず。 「うー、はぁい。」 素直に頷く。 レンの大きな手がくちゃっと私の頭を撫でてきた。 見上げてみれば、レンが私を見下ろしていて。 それがまた…凄く、優しくって。 迂闊にも、とってもドキドキしてしまった。 うっ、夫にこんなにドキドキしちゃう私って…。 これから先、まだまだ長いって言うのに大丈夫なのかなぁ。 胸を押さえながら、慌てて視線を逸らした私の上にレンが屈みこんでくる。 そして。触れるような柔らかな口付けが…降って来た。 ああ、何にせよ思い出せてよかった。 でも、ね。忘れていた時も。 あの胸の痛み。痺れるような感覚。 レンのことを好きな気持は変わってなかった、と思う。 もちろん。面と向ってなんて…言えないけど。 ―――大好き。 〜Fin〜 |
| Back ‖ Next ハロウィン・パーティ INDEX |
TOP ‖ NOVEL |
Copyright (C) 2003-2006 kuno_san2000 All rights reserved. |