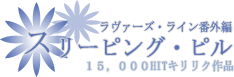 01 |
「鬱陶しい。離れろ。」 ゆうきは額にかかる髪をかき上げながら、一言のもとに言い切った。 それを聞いて、ゆうきの腕にまとわりついていた女が低く笑う。 薄暗い照明の中。 アンティーク調の内装を施された十畳程度の寝室。 二人が今いるのは、ベッドの上である。 ダブルの広々としたそこで、ゆうきはクッションに凭れ、座っていた。 もちろん、その体には何一つ服を身につけてはおらず、下半身にシーツが軽く被さっているのみだ。 ゆうきの隣にいる女も、それは同様だった。 先程まで、このベッドの上で二人が何をしていたかなど、その雰囲気から一目瞭然である。 「本当にあんたって冷たいわよねぇ。」 一糸纏わぬ姿のままの女は、ゆうきの腕から離れサイドテーブルの上にあるシガレットケースに手を伸ばした。 ゆるく巻かれた、茶色の髪。背中の中ほどまで覆うそれが、女の豊かな乳房にふうわりと纏わり附く。 女は、おそらく20代後半。 化粧をしていなくとも、十二分に美人と呼んで差し支えない容貌をしていた。 手に取った煙草に、女がカチリと火をつけた。 「俺がべたべたするの、嫌いだって知ってるだろ。」 女を横目でちらりと眺め、ゆうきは溜息と共になげやりな言葉を吐き出す。 深く煙を吸い込んだのであろう女が、ゆうきに向けてふうっと煙を吹きかけた。 「知ってるわよ?でも、今日で最後なんだもの、いいじゃないの。」 悪びれた様子も無く女が言い放つ。 その言葉で、ゆうきは今日が約束の期限だったことを漸く思い出していた。 横目で女を見たまま無言のゆうきに、女が魅惑するような笑みを浮かべる。 「まあ、楽しかったわよ。ゆうき。」 その表情とは裏腹な、女の皮肉気な口調。 女に調子を合わせ、ゆうきは唇の端を僅かに持ち上げながら「俺、遊ばれたんだ?」と言ってみた。 もちろん、そんなことを本気で思っているわけではない。 もともと、そういう約束だったのだ。 「よっくいうわ。本気になんかならなかったくせに。」 呆れたような女の言葉にゆうきは笑った。 本気にならなかったのは、お互い様だ。 「そっちこそ。」 笑いながら返すゆうき。それを見て、女は煙草を銜えたままごろりと俯けに寝転った。 「あーあ、高校生の癖に、生意気。」 女がつまらなそうに、呟く。 皮肉な笑みを浮かべ、ゆうは横にいる女に顔を向ける。 目に映るのは女の背中。無駄な肉の無いすんなりしたライン。髪の間から覗く細い首。 「その高校生を誘ったのは、あんただろうが。」 先程まで抱いていた体。それを眺めながらこの女に初めて声を掛けられた日をゆうきは思い出す。 女に誘われたのは、一ヶ月前。 見合い結婚するという女は、最後の独身生活を謳歌したいと、街を一人で歩いていたゆうきを誘ってきた。 体だけの付き合い。期間は一ヶ月。 かなりレベルの高い女の誘いに、ゆうきは半ば面白半分でのった。 そして、出会ったその日に女のマンションで、関係を持った。 女と寝るのは、初めてではなかった。 そもそも中学時代からこの手のことで不自由はしていない。 だが、それは恋や愛の感情とは程遠い、体だけの関係。 ゆうきはどんな女を抱いているときでも、どこか冷めた自分がいることを感じていた。 ―――本気に、なれない。 そう、気づいてはいる。だかこればかりはどうしようもない。 感情は、そうそう自分の意思で捻じ曲げることは出来ないものだろう。 何の感慨もなく、ただ女の背中を見ていたゆうきに向って。 「だって、顔と体が好みだったんだもの。」 女はあの日―――ゆうきを誘った日にいった理由と同じ言葉をはいた。 ゆうきが思わず乾いた笑い声を漏す。 そして、今日が約束した期限。 これで女は、ゆうきとの付き合いを切り、貞淑な妻になるというわけである。 ―――馬鹿馬鹿しい。 悠然と煙を燻らす女を見ながら、ゆうきは急速に気分が冷えていくの感じていた。 「オレ、今日はもう帰るから。」 女が吃驚したようにゆうきを見てきたが、それには気を払わずゆうきはさっさとベッドから抜け出す。 ちらりと壁に掛かった時計へと目を向けた。 今日は華の誕生日。 そろそろ、家に帰らなければならない。 夕食も兼ねた華の誕生会は、18時から。今の時刻は17時少し前。 ゆうきが学校帰りに直接ここによってから、既に二時間になろうとしていた。 ―――華ももう、7才か。小学校に上がってから二ヶ月だったかな。 あたりに散らばった制服を身につけながら、ゆうきは今朝あった華の姿を脳裏に思い浮かべていた。 ―――ゆうきちゃんも・・・きてくれる? すがるような瞳で、聞かれた。今日の誕生会。 もちろん、今日華に言われなくとも。 数週間前から自分の母親である美枝にさんざんいわれていたゆうきは、華の家に呼ばれる気でいた。 そのつもりで贈り物も用意してある。 ゆうきの中で、華は可愛く愛らしい妹のような存在。 無邪気に見えて、実はいろいろなことを我慢している華の笑顔は、無条件で守りたいと思うのには充分過ぎるほどだ。 そのためには、誕生会にでることくらいどうということは無い。 ゆうきは最後に残っていたブレザーの袖に腕を通し、床に転がっていた鞄を手に取った。 女の方は一度も見ることなく、寝室のドアに手を駆ける。 「・・・・ねえ。ゆうき、まだ女の隣じゃ、眠れないの?」 ノブを廻そうとしたとき、背後から女が何気ない口調で尋ねてきた。 女に顔を向け、ゆうきが軽く笑う。 「寝られないわけじゃ、ない。ただ、なかなか寝付けないだけ。」 ―――女が傍にいるとなかなか寝付けない。 甘ったるく寄りかかられれば、鬱陶しさが勝り。ずうずうしく甘い言葉を求められればますます気分が冷める。 そして気分が冷めれば。もう傍にいる女が疎ましくなる。 そんな気分のまま寝付けるはずも無く。 それが、さらに翌朝のゆうきの寝起きの悪さに拍車をかける。 しっかりとその悪循環を把握しているゆうきは、極力女の隣で朝を迎えることは避けていた。 これは、最初の頃にこの女にも言ってある。だからゆうきがこの部屋に泊まった事はこの一ヶ月の間一度も無かった。 「ふぅん。」 意味ありげに女が呟く。 「何?」 「別にー?ただ、あんた見たいなタイプが一度女に嵌ると・・・怖いのよねぇ?」 にやりと女が、笑う。 ゆうきの眉間に僅かに皺が寄った。 自分が女に嵌りこむ姿など、ゆうきにはまったく想像できない。 その思いが態度に出たのか、女がさらに笑みを深めた。 「まあ、せいぜい性悪女に引っかからない様に気をつけなさいよ。」 サイドテーブルの上にある灰皿に煙草を押し付け、女がベッドの上で身を起こす。 裸身をまったく隠そうともしない女に、ゆうきは呆れながら「あんたみたいな?」と返していた。 「何言ってるの。私はむちゃくちゃいい女、よ?」 ふふんと笑う女。その強気な態度にゆうきが苦笑する。 確かにいい女ではあった。 細かいことは言わないし、姉御気質とでも言うのかさっぱりとした性格はなかなかに好ましい。 だが、それだけだ。いい女ではあっても、長く関係を続けようとは思わない。 この辺りが潮時。幸い契約の期間は今日で終了である。 「じゃあ。・・・・楽しかったよ。」 カチャリとノブを廻し。ゆうきは最後の言葉を女にかけた。 「ええ、じゃあ。もう会うことも無いと思うけど。楽しかったわ。・・・ゆうき、いい恋愛しなさいよ?」 悪戯めいた女の表情に、ゆうきは軽く肩をすくめ小さく笑う。 「そればっかりはね。一人じゃどうしようもないだろ?」 やれやれと溜息を落とす女に、ゆうきは軽く手をふると、女の部屋を後にした。 明日には、女のこの部屋も引き払われる。 もう二度と来ることの無い部屋のドアを、特に感慨に耽るわけでもなくゆうきは一度振り返り。 無表情に見つめた後。再び歩き出していた。 *** 「ちょっと、ゆうき。」 十七時三十分時過ぎ。ゆうきは自宅の玄関に上がり込んだ所で、リビングから出てきた美枝に呼び止められていた。 「なに?」 自室に行こうとしていたゆうきは、美枝の方へ向きを変えリビングの入口近くへ足を進める。 近くにきたゆうきを見て、美枝の眉間に皺が寄った。 「・・・・あんたね、華ちゃんのところに行く前に、お風呂入りなさい。」 不機嫌な低い声。命令口調の美枝の態度に、ゆうきは一瞬考えた後、自身の腕を顔の前まで持ってきて僅かに匂いを嗅いだ。 「ああ、ひょっとして匂う?」 「匂うわよ。たくっ、そんなに香水のにおいぷんぷんさせて。」 忌々しげに吐き出された美枝の言葉。 移り香―――、自分では気づいていなかったが、かなり強く匂っていたらしい。 今まで美枝は何も言わなかったが、女の影があることにしっかり気づいていたのだろうと、ゆうきは苦笑するしかなかった。 「女と付き合うなとは言わない。でもちゃんと考えて付き合いなさいよ? ある日、見も知らない女があなたの孫ですなんて赤ん坊連れてきたりしたら、あんた勘当だからね。」 「そんなヘマ、しないよ。」 腰に手を当てて仁王立ちする美枝の姿に、ゆうきは皮肉な笑みを漏らしていた。 そんなゆうきをじっと見つめ、美枝が重い溜息をつく。 「・・・・・あんたね、もっといい恋愛、しなさい、よ?」 先程別れて来た女と同じ台詞。 今日二度目のその言葉やや驚きつつも。ゆうきは再び肩をすくめて、小さく笑った。 |
| Back ‖ Next ラヴァーズ・ラインINDEX |
TOP ‖ NOVEL |
Copyright (C) 2003-2006 kuno_san2000 All rights reserved. |