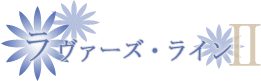 01 |
日中。 昼を少しまわったばかりのこの時間、校内は学食や購買部に行く生徒達でざわめきあっている。 雑談が交わされる教室の中。一つの机を囲んで、華は二人の友人とお弁当を食べていた。 「ねえ、華?あんた、何かあった?」 華の右前に座っている髪をアップにした顔立ちのはっきりした少女、早紀が口元に箸を運びながら、華に尋ねた。 「え?・・・ん、くっ・・・」 華は、突然の質問に思わず口の中にあった茶巾包みを丸呑みしてしまい、激しく咽る。 その様子に、早紀の顔が輝いた。 「あ、やっぱり何かあったんだ!」 華は、ペットボトルのお茶を飲みながら、軽く頭を振る。 「・・・・ううん、何にも?」 まだ、けほけほと軽く咽ながら華は否定した。 「本当に?」 疑わしそうに返してくる早紀に、華は、小さく「うん。」と頷く。 すると、華の左前にいるショートカットの大柄な少女、あゆが華の手を取り、 「華、正直にいってね?嘘は、だめよ?」 と、じっと見つめてきた。 友人二人の攻勢に華が、ややたじろぐ。 「どうして、そんなこと聞くの?」 それでも華は何とか、あゆと早紀の顔を交互に見ながら理由を尋ねてみた。 華の言葉を受けて、二人が顔を見合わせる。 お互い、目線で会話を交わしているようなその姿を見ながら、華はやや首を傾げていた。 不意に早紀が、華へ向き直った。そのまましげしげと華を見る。 居心地の悪さに、華が身じろぎすると、漸く早紀が口を開いた。 「なんかさ。華、色っぽくなったよね。」 「え、ええ!?」 思いもかけなかった事を言われ、華は眼を見張る。 色っぽい・・・、今までの人生で言われたことのなかった単語に、華はかなり動揺していた。 「なんていうか、目線とか動きとか・・・全体に色気がある感じ?」 驚いている華の全体を眺め回している早紀。 「うん、そうそう。だから、なんかあったのかなぁ、て。ねえ?早紀?」 あゆが早紀の援護をする。 華の方を向いたまま、にっこりと微笑んでいるあゆと、吟味するように眇めた眼を華の全身に走らせる早紀。 「そんなことないよー。」 華が顔の前でぶんぶんと両手を振って否定する。 だが、華は内心、二人の追及に冷や汗を流していた。 華が二人の言うとおり、本当に色っぽくなったというなら、その原因は一つしか思いつかない。 ――――ゆうきちゃん・・・とのことかな? ゆうきと華が付き合いだしてから数週間が経とうとしている。 だが、華は、ゆうきとのことをまだ誰にも告げていなかった。 もちろん、今まで気心の知れた友人として付き合ってきた二人に、華はきちんと告げるつもりではいる。 ――――でも、まだ今は・・・。今は、まだ駄目なの。 心の中で謝まりながら、華はそっと溜息を落とした。 華には、二人に告げるより前に話さなければならない人がいる。 ずっと先延ばしにしていたが、今日こそ華は話すつもりだった。 「あの、私ちょっと用があるから。」 素早くお弁当箱を片付け、席を立とうとする華に、二人の疑わしげな視線が向けられる。 「華って、時々・・・秘密主義だよね。」 早紀がもらした呟きに、華の心がちくりと痛んだ。 「早紀、あんまりいじめちゃダメよ。ほら、華、いいからいってらっしゃい。」 心底困った華の姿に、あゆが助け舟を出してくる。 華は、軽く頷くと、今度こそ席を立った。 歩きだそうとする華に「昼休み、あと少しだよ?」と、早紀が声を掛けてきた。 華は、早紀の方へ振り向き、「うん。そんなに遅くならないようにする。」と笑いかけ、教室を後にした。 そして。教室から華の姿が完全に消えた後。神妙に顔を見合わせる少女が二人。 「あれは、絶対なんかあったよね。」 早紀の力を込めた言葉に、あゆが「うん、うん」と頷く。 「・・・・どっちかな?・・・会長だと思う?」 早紀の窺うような調子に、あゆがやや考え込んだ。 「会長じゃ、ないんじゃない?だって、会長が相手じゃ、あそこまで変わらないと思うよ?」 「あ、やっぱり?じゃあ、もう一人の方かぁ・・・・。」 早紀が、腕を組みながら頷く。 早紀とあゆが、笑みを交し合った。 「どっちにしろ、ぜひとも聞き出さなくちゃね。」 「そうよね、もちろんよ。」 二人の少女がこくこくと頷きあう。 ―――気心の知れた友人たちがよもやこのような会話を繰り広げているとは夢にも思わない華なのだった。 「・・・・居ないなー。」 昼休みの賑わいを見せる校内を華は一人歩き回っていた。 捜している人物が一向に見つからないのだ。 そろそろ、昼休みが終わる時間になろうとしている。 華は僅かに視線を彷徨わせると、人気のない屋上へと続く階段の中段辺りに座り込んだ。 ―――もともと、忙しいからなぁ。今日は、もう捕まらないかな・・・。 華は軽く息を吐くと、そのままぼんやりと足元を見つめる。 華にとって、この数週間は信じられないくらい幸福な出来事の連続だった。 ゆうきに、妹以上の存在として、見てもらえるようになったこと。 華がゆうきを起こしにいってもゆうきの隣に女性がいることはなくなったこと。 ゆうきが華に対していままで以上に甘くなったということ。 そして、ゆうきの寝室が模様替えされたという、こと。 最後の出来事を思い浮かべ、華の頬がやや紅潮する。 あれから、何度もゆうきに触れられた身体。 ゆうきに、女として扱ってもらえる自分。 だが、その代償に・・・・華は、大切な人を、失ってしまうかもしれなかった。 それを思うと、華の心がきりきりと痛む。 でも、いまさら、ゆうきとのことを、無かったことにはできない。 一度解放された思いを、華はもういままでのように閉じ込めておくことはできなかった。 「華?」 不意に名前を呼ばれ、華がはっとする。 やや低く、耳に心地よく響くその声。 いつの間にか華の頭上に影が落ちていた。 華が顔を上げる。そこには、華を見下ろしながら柔らかく微笑んでいる、華の大切な幼馴染の姿。 銀縁眼がねを掛けた長身。窓から差し込む光に透け、やや茶色がかった髪が金に見えている。 「奏。」 華がゆっくりと、慣れ親しんだ幼馴染の名を、呼んだ。 「どうした、こんなところで。そろそろ、昼休み終わるぞ?」 「うん。」 「ああ、でも丁度良かった。ちょっと話があったんだ。」 「え?・・・・あの、うん。私も、話したいことが、あったの。」 「そうか。じゃあ・・・。」 奏が言葉を続けようとする。 だが、その時。丁度昼休みを告げる鐘の音が響き渡った。 奏が小さく溜息をついた。 鐘の音を聞き、奏を見つめてくる華に軽く笑いかける。 「今日、一緒に帰ろう。その時に、話すよ。華が話したいことも・・・聞く。構わないだろう?」 「うん・・・。」 華が小さく頷く。それを確認すると、奏は「じゃあ、後で」と軽く華の頭を撫でた後、歩き去っていった。 奏の背中が遠ざかっていく。華は、きつく手を握り締めると、ぱたぱたと階段を降り、奏とは反対方向へと駆け出していた。 |
| Back ‖ Next ラヴァーズ・ラインINDEX |
TOP ‖ NOVEL |
Copyright (C) 2003-2006 kuno_san2000 All rights reserved. |