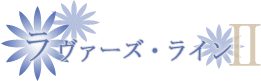 02 |
深夜。日付が変わってからかなりたとうかという時刻。 自宅の扉の前で、ゆうきは鞄から取り出した鍵を取り落としていた。 「う、わっと。」 コンクリートに当たって、チャリンと鍵が音を立てる。 ゆうきは、軽く舌打ちをし身を屈めると、すばやく鍵を拾い上げた。 ―――今日は、ついてないな。 拾い上げた鍵を手の中で軽く揺すりながら、ゆうきは心の中でひとりごちる。 もともと今日は、早く帰れるはずであったのだ。 それが、仕事からの帰りがけにばったりあった大学時代の友人に強制的に引きずられていき、いままで酒の相手をさせられていた。 その友人というのがまた酒豪で、いくら飲ませてもさっぱり酔いつぶれず。 結局ゆうきは相手の気が済むまで愚痴を聞かされ、かつ酒を飲まされてた。 いくら酔って前後不覚になったことはないとはいえ、今日はいささか許容量をオーバーしている。 ―――華に、来ないようメールしといて良かった。 酒気を帯びた溜息をつきながら、ゆうきは再び鍵を握り直し、ロックを解除しようと、した。 ―――開いてる? 廻したキーから返ってきた手ごたえのなさに、僅かにゆうきの眉が顰められる。 今日は、華は来ていない筈である。そもそも、こんなに遅い時刻まで華がいるとは思えなかった。 それに、鍵を開けたままというのも華らしくない。 僅かの間にそこまで考え、ゆうきは用心深く扉に手を掛けた。 すんなりと開く扉。そっと身体を扉の内側に滑り込ませる。 玄関から真っ直ぐ伸びた廊下の突き当たりにあるリビングからは明かりが漏れていた。 ゆうきの視線が、足元に落とされる。 玄関先に、きちんとそろえられた茶色のローファー。 「あ、ゆうきちゃん!」 ひょっこりと、リビングから華が顔を覗かせた。 玄関に立ち尽くしたまま顔を上げたゆうきが、眼を見張る。 「華?」 一瞬、幻かと思い、しげしげと華を凝視してしまう。 だが、そんなゆうきの様子に気づいていないのか、笑顔で華がゆうきの元までやってきた。 「おかえりなさーい。」 玄関の上がり口、ゆうきの真正面で立ち止まり、華がにこやかに出迎えてくれている。 どうやら幻では無いらしいと思いながらも、ゆうきは華をじっと見つめたままだった。 「華、どうして・・・。いや、いま何時だと・・・」 ゆうきの問いかける言葉に、途端に華の笑顔が消えた。 「・・・迷惑、だった?」 ぽつりと呟き、潤んだ眼でゆうきを見上げてくる。 華の変化に、ゆうきの方が戸惑ってしまう。 「迷惑なわけないだろう。じゃ、なくてだな。どうしてこんな時間に?メール、送っただろ?」 「うん。もらった。・・・・でも、ゆうきちゃんに、あいたくなったの。」 華が、ゆうきにきゅうっと抱きついてくる。 それを受け止め、ゆうきはいささか回っていた酔いが、一気に全身に巡っていくのを感じた。 「何か、あったのか?」 柔らかな華の身体を抱きとめながら、ゆうきは理性を総動員し、華に尋ねる。 気を緩めたら、このまま華を抱き上げて寝室へと連れ込んでしまいそうだった。 ゆうきの腕の中で、華がふるふると頭を左右へ動かす。 「はーな、本当に?」 再度、ゆうきがやさしく尋ねれば、今度はこくこくと華が頭を上下に振る。 これは、何かあったなと、直感的にゆうきは感じ取っていた。 「オレには、云えない事か?」 抱きついてきている華の背中を、ゆうきがやさしく撫でながら訊く。 「!?」 華が、ぱっと顔を上げた。驚いた表情でゆうきを見つめている。 「そんなに、オレは頼り甲斐がない?」 苦笑しながらゆうきが囁けば、華が激しく頭を左右に振った。 背中まである華の黒髪がさらさらと音を立て、華の背にかかっているゆうきの手に幾筋か絡まる。 「ちが、ちがうの!そうじゃ、なくてっ。あの、あの、ね。まだ、私の心の整理がついてなくて。でも、ちゃんとゆうきちゃんに、話すから。でも・・・・今は、聞かないで欲しいの・・・・。」 必死にゆうきに対して華が弁明する。最後の方は俯きながら、小さく言葉を落とした。 ―――今はまだ、言わなくても大丈夫か・・・。 華の中でまだ消化し切れていない出来事なのだろうと、ゆうきが華を見下ろしながら軽く溜息をついた。 早くに父親を亡くし、母親も仕事に追われて家を空けることが多かったという環境のせいか、華はある程度自分の中で整理した出来事でないと、他の人に話さないという一面を持っている。 だが、どうしても自分では整理しきれない出来事があれば、ゆうきに助けを求めてくるはずだった。 話したくないというのなら、まだ大丈夫なのだろうと、ゆうきはやや安堵する。 「―――わかった。今は聞かない。でも、待ってるからちゃんとオレに話すこと。いいか?」 「うん。」 ゆうきの腕の中で華が俯きながら、小さく頷いた。 「じゃあ、送っていくから。支度しておいで。」 ゆうきの腕が開かれ、華を解放しようとする。 これ以上触れていれば、本格的に押さえの効かない事態になってしまいそうだった。 だが、華はゆうきから離れようとはせず、ゆうきの胸に顔を押し付けてじっとしたまま動こうとはしない。 「華?」 訝しげに名を呼ぶゆうきの言葉に、華が顔を上げた。 「―――泊まっていっちゃ、ダメ?」 じっとゆうきを見つめたまま、華が小さく呟く。 意味をわかっていっているのかと、ゆうきは確認せずにはいられなかった。 「あのな、今日は、かなり酔ってる。・・・・ただ一緒に眠るなんてまねはできそうにないんだ。」 酔って無くても、たぶん出来ないだろうが、と自嘲的にゆうきが心の中で囁く。 だが、今日は酔っている分、ゆうきは自分の押さえが効かない。 華に無理をさせることになるかと思うと、迂闊に手は出せなかった。 しかも明日(正確にはもう今日、であるが)は、平日。 華は学校がある。そうそうサボらせるわけにもいかないだろうと、ゆうきは思っていた。 「・・・・。」 ゆうきの言葉に、意味を理解したらしい華が頬を染めて黙り込んでしまう。 腕の中に愛しい女を抱きながら、何もしないでいられる自信は、ゆうきには無かった。 「だから、今日は帰ったほうがいい。」 ゆうきが、できるだけやさしく華に告げる。 「・・・・・や。」 だが、華は躊躇しながらも、ゆうきの言葉を拒否、した。 その瞬間、ふつりとゆうきの理性の糸が、切れた。 「・・・じゃあ、覚悟しろよ?」 告げるなり、ゆうきは華の首筋に顔を埋める。跡が残るほどきつく耳の付け根辺りを、吸った。 華の身体が僅かに震える。 「ん・・・ゆうき、ちゃん・・・お酒の匂い、すごい、よ。」 小さな、だが確実に甘さを含んだ華の声が、その唇から漏れた。 ゆうきは玄関に上がりこみ、華を向かい合ったまま抱き上げると「いやか?」と笑いを含んだ声で確認する。 「ううん、平気、だけど。・・・酔っ払いそう。」 おとなしくゆうきに抱き上げられながら、華が呟いた。 ゆうきがおかしそうに喉を鳴らす。 そして「酔ったら、オレが介抱してやるさ。」と、楽しそうに言いながらどんどん歩を進めた。 ゆうきが、寝室の前へと辿り着く。 華を抱えたまま片手で扉を開けると、闇に包まれた寝室が目に入った。 「華。」 ゆうきが甘く華の名を呼ぶ。それに答えるように華がわずかに首を傾けた。 二人の唇が軽く触れ合う。 くすぐったそうに小さく笑う華を眺めながら、ゆうきは再度華に口付けた。 今度は、深く奪うように唇を割り開く。 甘い感触にゆうきの体内は熱くなっていく一方だった。 そのまましばらく華の唇の感触を楽しむ。 唇を離すと、華が潤んだ目と紅潮した頬でゆうきを見つめてきていた。 ゆうきは華に甘く微笑みかける。 そして、小さく息を乱す華を寝室へと連れ込み、ぱたりと扉を閉めた。 |
| Back ‖ Next ラヴァーズ・ラインINDEX |
TOP ‖ NOVEL |
Copyright (C) 2003-2006 kuno_san2000 All rights reserved. |