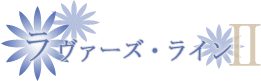 03 |
「ん・・・あ、やあ・・・」 華の甘みを含んだ声が室内に響いていた。 ゆうきのしなやかな身体が華の上で動く。 その度に震える自分の体を、華は止めることが出来ずにいた。 ベッドの軋む音。周りには、乱雑に脱ぎ捨てられた衣服が散らばっていた。 薄っすらと灯るベッドサイドのライトが、二人の姿をぼんやりと映し出している。 切なげに喘ぐ華の白い肌は紅色に染まり、華を組み敷くゆうきの額には汗が流れ落ちていた。 「ゃあ、ゆうき、ちゃん・・・・んっく・・」 何度も何度もゆうきに求められ、追い上げられて、既に華は限界を超えている。 しかし甘い疼きは止まらず、ゆうきに求められれば華は応えてしまう。 華は、自分の中にゆうきを感じられることが嬉しかった。 ゆうきが、甘く掠れた声で華の名を呼ぶ。熱を含んだ目で見つめてくる。 今日のゆうきの愛撫は、いつもよりやや荒々しく、余裕がない。 それでも華が辛そうにすると、気遣うように「大丈夫か?」と声を掛けてくれた。 その度に、華は頷く。ゆうきに触れられるのが、心地いい。 ゆうきの呼吸が荒くなる。それに合わせるように律動も激しさを増す。 華が一際甘い声で、啼いた。 「う、ん・・・あぁ、ゆうき、ちゃんっ」 ゆうきが、切なげに顔を歪めている。 ゆうきの背中に廻した華の腕に力が籠もる。 激しくなるゆうきの動きに華の頭の中が真っ白に、なる。 その瞬間、華奢な身体が痙攣したように跳ねた。 「華・・・・っ」 華が上り詰めたと同時に、華の中にあるゆうきの欲望が解放されるのを感じた。 ゆうきが、すばやく華から自身を引き抜く。 「ん、く・・・」 敏感になった華の体は、ゆうきのその動きにさえ反応を返した。 ゆうきが額にかかった髪を掻き揚げながら甘く笑い、華が頬を染める。 華は、ゆうきの僅かな動きにすら感じる自分の体が不思議でならなかった。 ―――私、どうしちゃったんだろう。すごく、やらしい子みたい? 荒い息をつきながら、華は白い胸を上下させるつつ不安げにゆうきを見上げる。 「ん?どうかしたか?」 華の視線に気づいたのか、ゆうきが華の額に軽くキスを落としながら尋ねてきた。 だが、ゆうきに思っていたことを聞ける筈も無く。 華はますます頬を染めながら、ゆうきから視線をそらしてしまう。 「はーな?」 ゆうきの手が華の頬をやんわりと、包みこんできた。 華が再び視線を戻した先には、ゆうきの極上の笑顔。 わずかに息を呑む華。ゆうきに、逆らえなくなる。 まだ、ゆうきに淡い恋心を抱いていたあの頃。女の子としてみてもらえることを夢見ていた、頃。 いつでも華は、ゆうきの態度に一喜一憂しつつも、様々なことを聞いてもらっていたことを思い出す。 ほんの些細なことから、母親の居ない家に独りきりでいることの寂しさ、まで。 あの頃、華は全てをゆうきに曝け出していた。 だが、ゆうきにとって自分が妹以外の何者でもないと知ったとき、華はゆうきに全てを打ち明けることが出来なくなった。 あれから数年。その間、華がゆうきに告げずにいた出来事も、ある。 そう、華が知らないゆうきの生活があったように。 「華?」 不意に真摯な声で名を呼ばれ、華がはっとする。 間近にゆうきの顔が、あった。 ―――もう一度、あの頃のように、素直になりたい。 華の頬を包み込んでいるゆうきの手の上に、華の華奢な手がそっと重なった。 華には、まだゆうきに告げられないことがある。 だからこそ、これ以上はゆうきに何かを隠したくは無かった。 ゆうきを見つめ、華は思い切って口を開く。 「ゆうきちゃんに、触れてもらうのが・・・すごく気持ちいい。私、やらしい子かな。」 華の頬が朱色に染まる。自分の言葉の恥ずかしさに、華はこのまま消え入りたい思いだった。 華の言葉に、何度か瞬きするゆうき。じっとゆうきの反応を待つ華。 しばらくした後。ゆうきが堪り兼ねた様に声を立てて笑い出した。 華が笑われたことにますます頬を染めながら「ゆうきちゃん!」と、抗議の声を上げる。 すると、ゆうきは笑いを残したまま、華の唇に軽く触れるだけのキスをしてきた。 「いや、悪かった。・・・・別に、やらしくないよ。まあ、オレは華が気持ちよくなってくれて嬉しいけど。」 「―――嬉しい、の?」 苦笑しているゆうきに、華は不思議な思いで聞き返していた。 「ん?こういうことはどっちかだけ気持ちよくてもダメだろ。」 ゆうきのやさしい瞳が、華を見下ろしている。 「ゆうきちゃんも・・・ちゃんと気持ちいい?」 華は、慣れない自分が相手でゆうきが満足しているのか疑問だった。 だが、そんな華の疑問を払拭するように、誘うような甘い笑みをゆうきが漏らすと、華の耳元に口を寄せ、低く艶めいた声で「ものすごく。」と、囁いてきた。 しかも、それに合わせて、ゆうきの手が華の体のラインに沿って這わされる。 くすぐったいような、ぞわりと肌の震える感触。華は慌ててゆうきの手を押さえた。 「―――でも、今日は・・・もういい。」 このまま黙っていれば再び愛撫を再開させそうなゆうきの様子に、流石に華が音を上げる。 もうそろそろ朝日が昇ろうかという時刻である。 華の言葉に、ゆうきが諦めたような表情で「今日は、な。」といいつつ、華の身体から手を離した。 やや含みのあるゆうきの言い方に、華が苦笑する。 「ゆうきちゃん、やらしい。」 華が悪戯っぽくゆうきの顔を見ながら囁いた。ゆうきと華、二人が同時に笑いだす。 そして、ベッドの中でじゃれ合っている内に、ゆうきの腕が華の身体をすっぽりと包み込んでいた。 ―――無くしたくない、この幸せを。ゆうきちゃんと一緒に居られるこの幸せを。でも、ちゃんと全部言うから、ゆうきちゃんに。でも、今は。今は、まだこのまま――― 華は、心の中でそっと思いながら、ゆうきの背に腕を廻す。 そして、自身の不安を解消するかのように、華はきつくきつく、ゆうきに抱きついていた。 ゆうきが目覚めると、既に華の姿は無かった。カーテン越しに差し込んでくる光が強い。 おそらく、既に昼が近いのであろうことが知れる。 ちらりとゆうきが壁に掛かった時計に目を向けると、案の定時刻は12時五分前になろうとしていた。 まだ、半分以上眠っている頭のまま、ゆうきはベッドの中で何度か寝返りを打つ。 どうやら華は、朝のうちに帰ってしまったらしい。 ゆうきは華の感触が残る腕を持ち上げ、ベッドサイドに置いてあるテーブルの引き出しから煙草のケースとライターを取り出した。 ケースの中から一本煙草を抜き取ると火を点け、箱とライターをテーブルの上に無造作に投げ出す。 煙を深く吸い込み、吐き出した。 夕べはかなり華に無理をさせた。 おそらく学校に行ったのだろうが、身体は大丈夫だったのだろうかとゆうきが苦笑する。 ―――それに、あまり寝かせてやらなかったしな。授業中に居眠りしてなきゃいいが。 等と考えつつも、ゆうきはまさか華が帰っているとは思わずに目覚めた為、華が居ないことにだいぶ落胆していた。 そのせいだけでもないだろうが、どうにも起きる気にならない。 どのみち今日、仕事は休みの上に、特に用事も無く、ゆうきが無理に起きる理由も無い。 ゆうきは、内装デザイン系の会社に勤めている。 そのため、クライアントとの打ち合わせが週末になることもあり、休みはだいたい平日に取る事にしていた。 ―――そういえば、あいつ。橡(くぬぎ)・・・今日、仕事じゃなかったのか? ふと、昨日ゆうきを無理やり酒盛りに付き合わせた大学時代の悪友の顔が思い浮かんだ。 ゆうきと対等に酒の飲める酒豪。見た目はどちらかというと優男。 人懐っこい笑顔と話術を武器に営業職についてはいるが、その実、ゆうきの友人の中でもかなりの変わり者である。 昨日は大分腹に据えかねた出来事があったと見え、ゆうきはめずらしく橡の愚痴に付き合わされたわけだが、どうやら橡と会ったのは偶然ではなく、橡がゆうきを待っていたからではないかと思っている。 ピンポーン。 チャイムが、鳴った。 「ああ?誰だ?」 紫煙を燻らせながら不審気にゆうきが呟く。 今日は、特に知人が訪ねてくるような予定は無かったはずである。 何かの集金かとも思ったが、動くのが億劫で、ゆうきはそのまま居留守を決め込むことした。 ピン、ポーン。 再び、チャイムが鳴る。だが、二三度鳴らせば、気が済んで帰るだろうと、ゆうきは暢気に煙を燻らせていた。 しかし――――――。 ピンポン、ピンポン、ピンポン、ピン、ポーン、ピンポン、ピン・・・・・ポン、ピンポーン。 ふざけたリズムで鳴らされる、チャイム音。 ゆうきの目が、不機嫌に眇められる。 悪戯かとも思ったが、いままでこのマンションでこの手の悪戯は無かったと、ゆうきはベッドの上にのっそりと起き上がった。 ピンポン、ピンポン、ピンポン、ピンポン。 今度は、一定のリズムで押されているらしいチャイム。 軽く舌打ちすると、ゆうきは煙草を咥えたまま大股で玄関へと向けて歩き出した。 「よっ、瀬守(せもり)。なんだ、まだ寝てたのか?」 ゆうきは、思わずドアを開けたことを後悔した。 しかし、せめてカメラで確認してからにすべきだったと思っても、すべて後の祭りである。 「ああ?・・・なんでいるんだよ、橡(くぬぎ)」 開けた扉の前にいる、コンビニのマークが入ったビニール袋を手に提げジーンズにシャツを羽織っただけという、実にラフな格好をした優男にゆうきは冷ややかな視線を向けた。 「うわ、お前相変わらず冷たい奴だよなぁ。昨日は一緒に酒を酌み交わしあった仲じゃんか。」 優男、ゆうきの大学時代の悪友である橡が大げさに驚いた振りをする。 「てか、迷惑だから帰れ。お前、今日仕事じゃないのか?」 「今日は、オレお休みよ。お前と休みが合うの珍しいから、遊びに来てやったんだぞ。ちょっとは歓迎しろよー。」 にやにやと笑いながら、橡が袋を持っていないほうの手で扉を掴む。 どうやら本格的に家に上がりこむ気らしいと、ゆうきは諦めの溜息をついた。 「・・・・今日、休みだなんて昨日お前に言うんじゃなかった。」 軽く舌打ちしつつ言った言葉は、しかし橡にはまったく堪えていない。 あいかわらずにやにやとしながら、ビニール袋をガサガサと持ち上げる。 「ま、とりあえず、上がらせてくれよ。ほらほら、手土産持参だぞ〜。」 ビニール袋の中に入っているものを確認し、思わずゆうきはげんなりとした。 薄く透けて見えるそれは、缶ビールと酒の肴。 「・・・迎え酒かよ。たくっ、しょうがねーなー。」 「んじゃ、ま。お邪魔しまーす。」 「勝手にしてくれ。」 投げやりにゆうきは言い捨てると、橡が玄関に上がりこむのを溜息をつきつつ眺めていた。 |
| Back ‖ Next ラヴァーズ・ラインINDEX |
TOP ‖ NOVEL |
Copyright (C) 2003-2006 kuno_san2000 All rights reserved. |