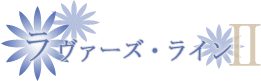 04 |
雪が、降っていた。三月の底冷えする曇天の空から。 その中で、華は聞きなれた声に呼び止められた。卒業式の終わった後、校舎から出てきたところで。 それは、いつも見知っている幼馴染の姿。雪に霞んで、周囲のざわめきに溶け込んで。 それでも、華を呼ぶその声は、はっきり聞こえた。 辺りには、卒業生や在校生、保護者たち。華の母親・澄香は、仕事の都合により来ては居なかった。 その代わり、華の卒業式にやってきてたのは、二つ年上の幼馴染。 「奏。きてくれて、ありがと。」 華が、傘も差さずに雪の降る中で佇んでいる奏へ、笑いながら傘を差し出した。 僅かに笑みを浮かべ、奏が少し俯く。 「澄香さん、これなくて残念だったな。」 華から視線を逸らしたまま、ぽつりと奏が言った。 「うん、でもお仕事だもん。仕方ないよ。」 小さく白い息を吐きながら、華が答える。 父親が亡くなる前から、澄香は働いていた。 体の弱かった父親に代わって、事実上、比呂平家の家計を支えていたのは母親の澄香だったのだ。 その為、華は学校の行事に両親が来ないことには慣れていた。 だが、やはり寂しくは、ある。 楽しげに両親と会話する友人たちを見ているのは・・・ほんの少し、辛かった。 ―――そういえば、寂しいって、いったことがあったけ。ゆうきちゃんに。 ふと思い出し、華が僅かに微笑んだ。 「・・・ゆうきも、来なかったな。」 まるで、考えていたことを見透かされたような奏の言葉に、やや華が目を見張る。 「・・・うん。急に、お仕事が入ったんだって。」 華が、寂しいとゆうきに云った後から、ゆうきは都合がつくと、華の学校行事に顔を出してくれる。 今日の卒業式にも、一昨日まで、ゆうきは行くからと華に言っていてくれた。 しかし昨日になって急にゆうきが請け負っていたプロジェクトのクライアントからクレームが付き、行けなくなったと連絡があったのだ。 ―――今回は誰もきてくれないのかぁ。 そう思っていた華だったのだが、何故か今朝会った時、急に奏が来るといいだしたのである。 やや驚いた華だったが、たぶん華が独りで寂しい思いをするだろうと気を使ってくれたのだと思っていた。 いつの間にか、華の傍に居てくれる奏は、華にとって本当の兄のようだった。 「でも、奏がきてくれたもん。ほら、寒いから早く帰ろ?」 にっこりと笑って、華は奏を促した。そのまま、歩き出そうとする。 しかし、華の傘を持っていないほうの腕が、掴まれた。 驚いて振り向くとそこには、真剣な色を浮かべた奏の顔。 「華・・・、お前に、言いたいことがあるんだ。」 奏の緊張が、華にも伝わってきた。 何度か瞬きをした後、華も真剣な面持ちで、奏が先を続けるのを待つ。 「――――オレは。」 じっと奏の顔を見ている華の様子に、僅かに奏が言いよどんでいる。 「――――オレは、な。華―――――――」 はらはらと舞い落ちる雪が、すべての音を吸い込んでしまったように華には感じられた。 「――――・・・な、はぁな、・・・・華ってば!」 少し高めな少女の声。呼ばれた名前と共に、華の体が揺すられる。 「っ!」 がばりと、華が伏せていた机から顔を上げた。 見知った顔が、呆れたように華を眺めている。 「あ、やっと起きた。」 「え?早紀?」 華の机の前に屈みこんで、華を見つめている早紀。 状況をつかめずにぼんやりとしている華の前で「もう、ちっとも起きないんだから」と呟きながら早紀が立ち上がった。 「華、大丈夫?今日、ほとんど寝てたでしょ?」 華の顔にかかった黒髪を軽く払いのけながら、早紀が華にとって衝撃的な事実を告げてくる。 「・・・・私、寝てた?」 呆然としたまま華が聞き返すと、早紀が大げさに溜息をついた。 「寝てた。ま、あんたは普段が真面目だからね。先生も見逃してくれたみたいだけど。・・・でも、このところおかしいよ?居眠りはするし、この間は無断欠席。」 依然、呆然としたままどこか焦点の合わない目をした華の顔を早紀が覗き込んでくる。 ―――夢?・・・ううん、違う。夢じゃ、ない。 早紀の顔を見ながら、それでも華は先程の夢の情景が頭から離れなかった。 あれは、確かに華の過去にあった出来事。そして、ゆうきに告げられなかった、出来事。 華が俯きながら、両手で顔を覆う。そのままの格好で小さくぐもった声を漏らした。 「―――うん。私、どうか、してるよ、ね?」 いままで早紀が聞いたことが無いほど自嘲気味な華の声。 驚いたように早紀が華を見つめる。僅かに口を噤んだ後、早紀の手が華の頭に伸ばされた。 トンッ、と軽い音をさせ、早紀が華の頭を軽くはたく。 華が顔を上げると、早紀が・・・苦笑していた。 「馬鹿ねー、何を落ち込んでるのか知らないけど、華らしくない。ほら、もう授業も終わったし。帰ろ、帰ろ。」 さばさばと早紀が告げ、さっさと自分の席に戻ると鞄を手に戻ってくる。 漸く華が辺りを見回せば、教室の中に残っているのはもう華と早紀だけだった。 あゆは部活の為、ホームルームが終わった時点で部室に行ってしまっていたのだ。 「ほら、華。いこ。」 早紀は、座ったままの華へ声を掛けると教室の入り口に向けて歩き出していた。 華が慌てて鞄を掴み、早紀の後を追う。 追いついた華が早紀の隣に並ぶと「今日は、例の幼馴染のとこ寄ってくの?」と、早紀が尋ねてきた。 人気の無くなった廊下を歩きながら、「うん。コーヒー置きに行くだけだけど。」と、華が頷く。 今日は母親である澄香がが出張から帰ってくる為、あまりゆうきのところに長居は出来なかった。 それでなくても、ゆうきと付き合いだした事は、まだ母親にも告げていない。 今の状態で、何度がゆうきの元に泊まりにいってしまっていることが、華には心苦しかった。 ゆうきに思いが通じる前は、ゆうきの元に遊びにはいっても泊まっていったことは、無かったのだ。 華のことを信用しているからこそ家を空けることができると澄香が云っていたことを思い出し、華は申し訳ない気持ちでいっぱいになる。 ゆうきとのことを後悔しているわけでは、もちろんない。 だが、このままずるずるとゆうきに甘やかされて、依存していくことも華の心は拒否している。 ゆうきと対等になるにはまだまだ時間がかかることは、華にも判っていた。 ―――それでも、いつかはゆうきちゃんの隣に並んでも見劣りしないような女性に、なりたい。 真剣に考え込んでいる華の横顔を、早紀が心配気に見つめていた。 「あんまり、無理しないのよ?」 早紀が、そっと呟いた。華が、早紀に笑いかける。 「ん、ありがと。」 その後、二人は他愛の無い雑談をしながら、のんびりと静かな廊下を歩いて行った。 華が鞄から取り出した鍵で502号室の扉を開けると、そこには何故か見慣れない靴が一足。 「?」 華が玄関の扉を開けたままの姿で、僅かに首を傾げる。 ゆうきが持っていた靴だったろうかと記憶を辿っていくが、華にはやはり見覚えが無かった。 奇麗に手入れのされた革靴。 おそらくブランド物であろうそれは、だがゆうきの好みでは無いような気が華にはした。 ―――あ、ひょっとして、お客様? ようやく思い至ったその考え。 肯定するかのように、華の耳にリビングからのゆうきの声が聞こえてきた。 「橡っ、携帯鳴ってるぞっ!」 何故か、聞いたことのあるような名前に、華がようやく顔を上げる。 その途端。 ――――ガチャッ。 玄関からリビングへと伸びる廊下の途中にある手洗いの扉が、開いた。 華がそちらを向くと、そこには見慣れない男性がドアノブを握ったまま華の方へ驚いたような顔を向けている。 おそらく橡と呼ばれた人物だろうとは思っていても、咄嗟に云うことを思いつかず華は黙り込んでしまった。 ドアノブを握ったまま、何かを考え込んでいるかのように橡の方も黙り込んでいる。 華と橡、何故かお互いに、お互いをみたことがあるような気がしていたのだ。 「あ。君――――」 ようやく橡が口を開きかける。華が、瞬きした。 「あ!橡さん!?」 「橡、お前携帯鳴ってるって・・・・・華?」 「え?華ちゃん?」 三人三様に、上げられた声。 リビングの扉から、ゆうきが片手に携帯を持って顔を覗かせていた。 |
| Back ‖ Next ラヴァーズ・ラインINDEX |
TOP ‖ NOVEL |
Copyright (C) 2003-2006 kuno_san2000 All rights reserved. |