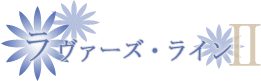 06 |
橡が押しかけてきた日の翌日。 仕事から帰宅したゆうきはいつものようにリビングに入ると、点滅を繰り返している電話の留守番モードを解除した。 『メッセージは、全部で5件あります。』 件数を告げるメッセージが流れる。 ゆうきはそれを聞きながら、電話の下にあるキャビネットを開けブランデーとグラスを取り出しソファへと足を向けた。 テーブルの上に瓶とグラスを置き、ソファに身を沈めると、軽くネクタイを緩めて溜息を落とす。 仕事関係が3件、勧誘が一件。 わずかにノイズの混じったメッセージが次々と再生されていく中、ゆうきは目を閉じて聞き流していた。 そして、最後の・・・一件。 『ゆうき?帰ってきたら、連絡よこしなさい。あたなね、たまには家にも帰ってきなさいよ?それから、あんまり華ちゃんに迷惑かけちゃ、だめよ!わかった?じゃあ、ね。』 電話から聞こえて来た、やや低めな女性の声。ゆうきの母親である美枝のものだった。 録音内容が以上であることを告げるメッセージが流れ、留守録の再生が終了する。 ―――ひょっとして、何か気づかれたかな? ゆうきは目を開けてソファから上体を起こし、テーブルの上にのせたブランデーをグラスに注ぐと、一気に煽った。 ゆうきの母親である美枝は、華の母親である澄香の長年の友人であるのだ。 華の様子に変化があれば―――おそらく見逃さないであろうと、ゆうきが苦笑した。 華とのことは特に隠す気もないので、何か問われればありのままを話すつもりでは、いる。 ただ、ゆうきが気がかりなのは――――昨日、橡が言っていたこと。 『抱き合ってた。』 ありえないとは、思う。だが、何故かゆうきは嫌な予感がしている。 ―――華が奏と、か。・・・・まさか、な。 再びグラスにブランデーを注ぎ勢い良く喉に流し込むと、ゆうきはグラスを置き立ち上がった。 スーツの上着をソファに脱ぎ捨て、バスルームへ向う。 既に時刻は深夜である。 昨日、橡はやはり帰らず。ゆうきはだいぶ遅くまでつき合わされたのだ。 それも、やれ華に過保護にし過ぎだの、華も年頃なんだからゆうきの世話ばかりさせるなだの、やけにゆうきに絡んでくる橡に、である。 我慢の限界も超えようかという時、ようやく橡が寝入ったから良かったものの、でなければ蹴り飛ばして玄関から放りだしてやるとなかば本気でゆうきは思っていた。 ゆうきにとって橡のいっていることは、余計なお世話以外の何者でもないのであるから、当然といえば当然である。 華は、ゆうきの思いを受け入れた。ゆうきは華を―――愛している。 たぶん、愛という言葉以上に強いゆうきの思いは、それでも、愛しているという言葉でしか伝えられない。 いい歳をして、華に溺れている自分を、ゆうきは自覚せずにはいられなかった。 ゆうきは服をすべて脱ぎ捨てバスルームに入ると、シャワーの熱い湯を浴びる。 思った以上に仕事が長引いた上、昨夜の酒盛りも手伝って、かなり疲れていた。 知らずに溜息が漏れる。 ―――明日、仕事が早く終わったら寄ってみるか。 立ち込める湯気の中、ゆうきは額にかかる髪をかきあげながら、静かに目を閉じた。 偶然は、時に思わぬ厄災を齎すもの。 そして、ゆうきは翌日。その偶然により、最悪の場面を目撃することと、なる。 *** そう。偶然。だが、最悪の偶然は重なり。 ゆうきは、今。信じられない光景を目にしていた。 比呂平家の門前。外灯が灯る中、路上で重なり合う二つの影。 華と奏。―――抱き合っている二人。 華の華奢な手が奏の背中に廻され、奏の腕が華の腰を支えている。 ゆうきは、闇の中立ち尽くしながら、信じられないものを見る思いだった。 そもそも、昨夜、母親からの電話が無ければ、おそらくゆうきは家に寄ろうとは思わなかった。 だが予定よりも仕事が早く片付き、昨日考えていた通り、ゆうきは実家に寄っていくことにしたのである。 仕事場から車で約30分。仕事場を出る前に家に連絡を入れ、戻る旨を伝えてあった。 瀬守家には、駐車スペースが二台分あるが、そのどちらも両親の車により占拠されている。 その為、実家に戻る場合ゆうきは近くにあるパーキングスペースへと車を止めに行っていた。 そこから瀬守家までは徒歩3〜4分。 三軒並んだ住宅。比呂平家を真ん中に、右に瀬守、左に叶。 丁度曲がり角に立つ瀬守家の角を曲がって家の門がある路地に入ろうとしていた所だった。 ふと、ゆうきの足が止まった。 住宅街ということもあり、いつもは人気の無い路地。 そこに外灯の明かりが齎す長い人影が、写っていた。 そちらに目を向ければ、影の主は、制服姿の高校生二人。 外灯の明かりのみでは、表情までよく読み取れなかったが、華の家の門前にいたのはゆうきの良く知る姿。 華と、奏。 ゆうきが気づいたこの時点では、まだ二人の間には僅かに距離が残っていた。 だが、ゆうきが足を止めている間に、何事かを小さくささやきあった二人の距離は急激に縮まり。 奏の腕が、華の体に廻されたのだ。 華の小柄な体が奏の腕の中に収まり。 ゆうきの居る位置からは、華の背中と華を大切そうに抱きしめている奏の姿のみが―――見えていた。 立ち尽くしているゆうきには、まったく気づいていないのであろう二人。 しばらくそのままじっと抱き合った状態でいたのだが、奏の頭が僅かに下がった。 華の体をそっとに離し―――片手で、華の顎を軽く、持ち上げる。 恋人同士のように寄り添う二人。 ゆうきには、華の表情を窺うことはできない。 だが、華が抵抗しているようには到底見えなかった。 そのまま、二人の唇が・・・・重なり合った。 はっきりと唇が重なったのが見えたわけではないが、ゆうきは直感的にそう感じていた。 一瞬にして、ゆうきの頭に血が上る。 考える間もなく、ゆうきは二人の傍に大股で近づいていき――――。 華の肩を掴み奏から引き剥がすと、ゆうきは奏の頬を殴りつけていた。 奏の決して小柄ではないはずの体が、壁にたたきつけられる。 華の口から小さな悲鳴が漏れた。 華が急いで奏に駆け寄る。 再び倒れこんでいる奏へと手を伸ばしかけたゆうきを、華の制止の声が押し留めた。 「ゆうきちゃん、やめてぇ!お願い、だめ!」 奏の前に座り込み、両腕で抱きしめながら奏を庇う華を、愕然とした面持ちでゆうきが見つめる。 「お願い・・・・私が、いけないの。だから、奏を、責めないで。」 華の顔が青ざめているのが、薄暗い中でもはっきりと判った。 「華?・・・・お前、奏が・・・」 ―――好き、なのか? ゆうきが、言葉を飲み込む。行き場の無い怒りに、拳をきつく握り締めた。 「ゆうき、ちゃん。」 華が、悲しそうにゆうきの名を――――呼んだ。 やっと手に入れた、愛しい少女。 それが、こんな形で失われようとしていることが、ゆうきにとっては信じられない。 確かに、数週間前に華はゆうきの求愛を受け入れた。 多少強引にだったとはいえ、その身体を開いてもくれた。 その後も、何度も抱いている。 恥じらいながらもゆうきに答えようとする華が、愛しかった。 それが、何故・・・。 ゆうきの頭に疑問がよぎる。 華が、二人の男と同時に付き合ったりできるほど、したたかな娘でないことはわかっている。 そんなことは、ありえない。 ならば。ゆうきを受け入れた後に、奏に告白され・・・。 華は、奏を――――選ぶのか。 ゆうきにとって受け入れがたい結論。 いまさら、手放せない。 手放せるわけが、ない。 一度手にしてしまえば、華のゆうきを見つめてくる瞳も仕草も甘さを含むようになり。 ゆうきは、それらをすべて独占していたのだ。 だたの幼馴染になど、戻れるわけがなかった。 泣き出しそうな顔でゆうきを見つめている華。 ゆうきの視線が、華の唇へと向けられる。 奏と触れ合った、そこ。 正直、華の唇を無理やり割り開き、奏の感触などすべて消し去ってしまいたかった。 だが、華を傷つけたくは、ない。 しかし、このままここにいれば、何をするかわからない。 華の顔を見ていれば、抑止できなくなる。 ゆうきは、華から視線をそらし、軽く息を吐くと、自分を落ち着けた。 華は、じっとゆうきを見つめている。顔を背けていても、ゆうきは華の視線を感じていた。 ゆうきの目の端に映る華が、震える唇を僅かに開く。 「ゆうきちゃ―――・・・」 「華を、ゆうきに渡すつもりはありません。」 しかし華の言葉は、奏の声により遮られた。 路上に座り込み、壁に凭れながら。奏は立ち尽くしているゆうきにきつい視線を向けてくる。 顔を背けたままのゆうきの眉間に皺が刻まれた。 華が泣き出しそうな顔で奏を見つめている。 「かな、で・・・」 小さく囁くような華の声。 奏は華が何か言おうとしているのを目線で制すと、ゆうきに挑戦的に言い放った。 「もう一度、言います。華を、渡すつもりはありません。貴方は、華のことを何もわかっていない。」 何もわかっていない、奏のその一言。 ゆうきは怒りで目の前が真っ赤に染まる思いだった。 ゆっくりと真正面から、奏を見据える。 ゆうきの口元に、凄みのある笑みが浮かんだ。 「お前は、わかっているとでも?」 冷たくはき捨てるゆうきに対し、奏は真剣な、真っ直ぐな眼を向けて来る。 「少なくとも、ゆうきよりは。」 答える奏の唇から、一筋の血が流れ落ちていた。 それに気づいた華が、震える手で制服からハンカチを取り出し、奏に向けて差し出す。 だが、奏はそれを受け取らず、差し出された手を掴むと自分の胸に華の華奢な体を抱きこんでしまった。 華が僅かに息を呑む気配が、した。 「・・・奏、華を―――離せ。」 奏を見下ろしながら、ゆうきが低く怒りを抑えた声で命令する。 だが、奏の腕は・・・緩まなかった。 しかも、華はやや強張った顔をしながらも、奏の腕の中におとなしく収まっている。 抵抗しないということは、すなわち奏を受け入れていると、いうこと。 ゆうきが、愕然とする。 まだ、信じられなかった。 だが、ゆうきの目の前では、確かに二人の高校生が抱き合っている。 それは、確かにしっくりくる光景では、あった。 華が、ゆうきに向けて辛そうに口を開きかける。 咄嗟にゆうきは「くそっ」と小さく呟き、二人に背を向けていた。 華の口から、別れの言葉など・・・聞きたくなかった。 そんなことをされれば、自分が何をするかわからない。 「そう、か。・・・判った。・・・華・・・しばらく、顔を見せないでくれ。」 苦しげにゆうきが呟く。それが、ゆうきにとって最大限の譲歩だった。 華の黒い瞳が、ゆうきを見つめているのであろう気配を感じる。 だが、ゆうきは一度も二人を振り返ることなく、再び来た道を引き返していった。 おさまることのない怒りに支配されながら。 そして、次に華にあったとき、自分が何をしてしまうかを・・・漠然と感じながら。 |
| Back ‖ Next ラヴァーズ・ラインINDEX |
TOP ‖ NOVEL |
Copyright (C) 2003-2006 kuno_san2000 All rights reserved. |