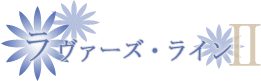 07 |
何が、起きているのか。 華は―――去っていくゆうきの背中を見つめながら呆然としていた。 突然現れたゆうきが奏を殴り飛ばし、奏がゆうきに―――華を渡すつもりは無いと告げて。 そして、ゆうきは華の顔を見たくない、と。 「痛っ。」 奏の低い呻き声が、華の耳に届いた。 はっと奏の方へと目を向ける。 奏の形の良い唇から、依然として血が流れ落ちていた。 たぶん唇と、口の中をきったのであろう奏は、すでに腫れつつある頬に顔を顰めている。 奏の胸に両手をつき、華は捕らわれていた体を奏から引き離した。 無言のまま、そっと手にしたハンカチで奏の唇を拭う。 「―――華。」 華の頬に奏がそっと手をかける。 その仕草は、とてもやさしくて。華は溢れ出そうになった涙を留めようと、俯きながらきつく目を瞑った。 瞼の下が、じんとする。その感覚が華を現実に引き戻す。 ゆうきは、華を見ることもなく去っていった。 もう駄目なのだと、華は絶望感に身を震わせる。 やっと振り向いてもらえた―――何よりも大切な人を傷つけた、そのことがたまらなく悲しかった。 ―――私がしたこと、は・・・・ただの自己満足だ。・・・ゆうきちゃんを・・・傷つけて。 堪え切れなかった涙が、華の頬を伝う。 ―――本当の意味で奏に応えることなんて・・・できっこないのに。 華の脳裏に先ほどのゆうきの顔がよぎる。 信じられないというように華と奏を見つめていたゆうきのその顔は、華がいままで見たことがないほど―――苦しげだった。 「―――華。」 奏が再び華を呼ぶ。 だが、華は顔をあげることが出来なかった。 一度堰を切った涙は華の瞳から次々に溢れ出てくる。 華が泣いているとき、いつも傍に居てくれたのはゆうき。 ゆうきの手が、華を抱きとめ、慰めてくれる。 いつのまにかそれに慣れて、華は最早どう一人で泣き止めばいいのかわからなかった。 声を殺して泣き続ける華の頭を奏が引き寄せる。 そして、華の耳元で―――そっと呟いた。「華・・・・頼む。オレを――――オレを、選んでくれ。」と。 華は、自分の身体がはっきりと強張るのを感じた。 咄嗟に奏の腕から逃れようと、身をよじる。しかし、奏の腕は華の抵抗などやすやすと封じ込めてしまう。 華は奏に捕らわれながら、左右に激しく頭を振った。 「やっ・・・・ごめ、ごめ・・・なさ・・・奏・・・・ごめ・・・」 それは、その願いだけは・・・・華にはどうしても聞き入れることが、出来ない。 いつからかなんてわからない。でも華は―――ゆうきだけを、求めている。 はじめは、子供っぽい独占欲だったのかもしれないと、思う。 それがいつの間にか、信じられないくらいに華の心を占めるようになり。 しかし、一旦ゆうきに拒絶されて、その思いは行き場をなくし。 今、ようやく解放することのできた華の気持ちは―――もう、ゆうき以外に向うことはなかった。 だから、華はただ奏に謝ることしか、できない。 ごめんなさい、と泣きじゃくりながら何度も何度も華は繰り返す。 そんな華を、奏の腕がきつく抱きしめた。 「―――やっと見せてくれたな、泣き出す顔。でも、その原因は―――オレ、なんだな。」 華を捉えていた奏の腕が緩んだのは、そう小さく囁かれた瞬間だった。 不意に自由になった身体。 華は止まらない涙を拭うこともなく、諦めたような笑みを浮かべる奏を呆然と見つめる。 「いつからだろうな、華がオレの前で泣きださなくなったのは。」 ぽつりとさびしそうに落とされた奏の言葉。 華は何のことかわからず「え?」と奏に返した。 「この間、久しぶりに華が泣いているところ、見た。ゆうきに・・・襲われてたとき。」 奏が苦笑している。 ゆうきに襲われていたとき。それは、まだ華の思いが通じる前。 酔って帰ってきたゆうきに華を押し倒されていたところを奏が助けてくれたことだと、華は思い至る。 確かにあの時、華は泣いていたが、奏の前で泣き始めたわけではなかった。 ―――私、奏の前で・・・泣き出したこと――――なかった? 自覚の無い華には、はっきりわからない。 だが、奏がいっているのであれば間違いないのだろうと、華はいままでのことを思い出してみる。 そして、思い返して見れば―――華が泣いているとき傍にいたのはゆうき。 それも、ゆうきは華の泣いているところにやってきたわけではなくて・・・・。 華が泣き始めるとき、いつも傍にいた。 ―――私、ゆうきちゃんの前でだけ、涙・・・我慢、できなくて。いつも、慰めてくれてて。 華は今初めて自覚した事実に愕然とする。 「ごめ・・ん、・・・奏。」 奏のさびしそうな瞳を見つめて、途切れがちに華が小さく謝った。 ゆうきに思いを受け入れてもらう前、華はできるだけ奏とゆうきの二人に同じように接していたつもりだった。 そう、妹として。それが、華のポジションだと思っていたから。 それが、無意識のうちに―――。そう思うと華は今この場に居た堪れなかった。 しかし、逃げ出すことはできない。 華は今度こそ決着をつけなければならないと、両手で目元と頬の涙をきつく拭い、しっかりと奏を見据えた。 華が意を決して口を開く。 「奏、私―――・・・ゆうきちゃんが、好き。」 華の言葉に、奏の顔が伏せらせる。 華から視線をそらしてしまった奏に、それでも華は真剣に言葉を紡ぐ。 「ゆうきちゃんに、妹でしかないって、対象外だっていわれて。悲しくて、苦しくて。でも、やっぱり諦めることなんてできなかった。妹でもいいから、傍にいたくて、馬鹿みたいに妹を・・・演じてた。だから。だから、奏にも同じ思いをさせてたのかなって、あの日、思った。」 奏に向き合おうとしている華に「してなかった・・・・といえば嘘になるな」と俯いたままの奏が答える。 ずきんと胸の痛みを覚えながら、華はそれでも先を続けた。 「うん。そうだよ、ね。でも、そう思っても私は、奏の気持ちに応えることはできなくて。あの日、奏がくれた言葉に私がいったこと――――覚えてる?」 「覚えてるよ。結構、堪えたから。」 奏が、小さく笑った。溜息をつきながら顔を挙げ、背中をすぐ後ろにある壁へと凭せ掛ける。 あの日。華の中学卒業の日。 はらはらと舞い落ちる雪の中、華は霞む風景に鮮やかに浮かび上がる奏の姿を見つめていた。 華の差し掛けた傘の下。華に告げられた奏の心。 「華が―――好きだ。幼馴染としてじゃなく。女として華が、好きだよ。」 奏の決意を含んだはっきりとした声。 しかしその内容を、華はしばらく理解することができなかった。 「――――え?何・・・かな、で?」 華を見て、奏がやさしく笑う。どくんと華の心臓が、跳ねる。 奏のいった言葉の意味を理解したその時。華は押しつぶされそうな罪悪感を感じていた。 華は、ゆうきに振り向いてもらえることはない。でも、ゆうきをあきらめることは出来ない。 ―――奏に応えられない。 奏に自分と同じ思いをさせるのかと思うと、それが酷く苦しくて。でも、大切な幼馴染だからこそ、嘘をつくわけにはいかなくて。 だから、華は正直にすべてを奏に話した。 ゆうきが、好きなこと。でも、決して振り向いてもらえることはないこと。 それでも華は――――ゆうき以外、選べないこと。 奏は華のその告白をじっと聴いていた。 華が話し終えたとき、降りしきる雪は勢いを増していたが、それでも奏は何も言わずただ華見つめていた。 奏に掴まれた腕の先にある指先が悴んでじんじんするのを華がぼんやりと感じる。 「それでも、構わないっていったら?華が、ゆうきを好きでも構わないからオレを選んでくれって―――。」 華は奏のその言葉に、目を見張った。 心に違う人を住まわせたまま、奏を選ぶ。そんなことは、出来るはずも無かったから。 奏は大切な幼馴染。だからこそ、そんな悲しいことはしたくなかった。 華は、はっきりと頭を左右に振った。すなわち否、と。奏の思いは受け入れられない。 でも、同時に華の思いがゆうきに受け入れられるはずも、ない。 そう思っていた。だから華は、奏に告げたのだ。 「ゆうきちゃんとは、ずっとただの幼馴染。だから、奏とも・・・・幼馴染で・・・いさせて。」と。 それが華にとっての精一杯だった。奏が―――――悲しそうに顔を伏せ、そして華の腕を静かに放した。 それが、是。奏は、華の出した答えを受け入れてくれた――――そう、思っていた。 だから、華はそれ以降も、今までどおりに振舞った。奏に対しても、ゆうきに対しても。 だが、華の言葉は―――――・・・ ゆうきとはただの幼馴染であるという関係は―――・・・破られてしまった。 華、ゆうき、かなで。三人の均衡は崩れ、奏の思いだけが今取り残されている。 華が、奏にゆうきと付き合うと、思いを受け入れてもらったと告げた時。 信じられないというように奏に見つめられた華は、あっという間に路地裏に引き入れられいきなり抱きしめられていた。 驚きにより抵抗できなかった華はその時、奏の思いは―――華を思っていてくれた気持ちは―――変わっていなかったのだと。 傷む心と共に、感じたのだった。 「あの時、言った言葉は、私の本心。でも、今、私は――――・・・」 壁に凭れたままじっとしている奏。華が、言い淀む。 奏が、嘆息した。 「ゆうきとただの幼馴染じゃ、なくなった、か?」 言葉を引き継いだ奏の寂しげな様子に、華が言葉に詰まる。 「華が今、オレの願いを聞いてくれるのは――――贖罪、だろ?オレの気持ちには、応えられないことへの・・・」 奏が、寂しそうに―――――笑った。 華が、辛そうに、苦しそうに奏を見つめている。 その様子に、奏は自分の考えが的を射ていたことを確信した。 華の中にある、自分に対する罪悪感。 いままでも、奏は漠然と感じていた。華が申し訳なさそうに奏を見つめていることがあることを。 だから―――奏はそれを利用した。 華に告げられる前から、華がゆうきのものになったなんてことは、とっくに気づいていた。 雰囲気の変わった華が、女になったのだと気づかないほど奏は鈍くは無いし、その程度のことを見抜けないほど華への思いは軽いものではなかった。 先に行動を起こしたのは、奏。でも、華が選んだのは、ゆうき。 華の気持ちにも気づかず、女を連れ込んでいたゆうきを、それでも華は選んだ。 だが、奏は今でもゆうきが許せない。 女の居たゆうきのマンションから、初めて華が戻ってきたとき―――・・・どれほど辛そうな顔をしていたか。 それだけでも、奏はゆうきを殴りつけたい衝動に駆られる。 しかし、華はそんなゆうきを選ぶと、いう。 奏ではなく、ゆうきを。 奏は華を苦しめたいわけではなかった。 物心ついたときから、大切に大切に見守ってきた少女。 誰かに傷つけられないように、誰かに泣かされないように。 なのに、華の視線の先にはいつの間にかゆうきが、いた。 自分は華にとって兄でしかない、奏はその事実に直面したとき、ゆうきをどれ程羨んだかしれない。 ゆうきが行動を起こす前に―――華を手に入れたかった。 だからあの日、奏は華に思いを告げた。 拒絶さえるだろうとは、わかっていた。それでも告げることで何かは変わるかもしれない、そう思った。 ―――でも、結局変わらなかったな。 自嘲を込めて、奏は目を瞑る。 「華。」 愛しい少女の名を、呼んだ。 華が、僅かに息を飲む気配を感じる。 ―――もう、これ以上苦しめても仕方ない。そんなことを望んだわけじゃ、ない。 奏は決意し、ゆっくりと目を開いた。 凭れかかっていた壁から上体を起こし、悲しそうな華の顔をまっすぐに、見る。 奏は、華を安心させようと―――幼馴染としての、いつもの笑顔を、浮かべた。 華が驚いたように目を見開く。 「華、行って、ゆうきの誤解を解いておいで。」 大切な、華。だから、もう手放そう、そう奏は決意していた。 「かな、で・・・」 華の漆黒の瞳から大粒の涙が零れ落ちる。 奏はそっと、華をおびえさせないように手を伸ばした。 頬を流れるそれをやさしく拭き取る。 「もう、いいんだよ、華。困らせて、ゴメン。さあ、行って?」 悲しませたくないから、奏はこの強すぎる思いを封じる。 すぐに忘れることはできない。 でも、いつかはまた、華の兄として華を助けてやりたい。 その為にも、奏は華をゆうきの元へ向わせる。華を諦めること。それが今、奏にできるただ一つのことだった。 ぼんやりと灯る明かりの下、奏は長年の思いに決別しようとしていた。 奏が華の頬に触れていた手を、引く。 華が困惑したように奏を見返してくる。躊躇している、と奏は感じた。 もう一度華の背中を押すために、奏は口を開く。 「今行かないなら、俺を選んだことに、なるんだよ?それでも、構わない?」 華の体が、びくりと震えた。 奏は苦笑すると、再び手を伸ばし、今度は引き寄せるのではなく。 自分から遠ざけるために、華の薄い肩をぐいっと押した。 華の目から、ぽたぽたと涙が零れ落ちている。 「奏、ごめんなさい。」 小さく呟き。華が、立ち上がった。 座り込む奏を見下ろしながら「ありがとう」というと華は身を翻し、やや躊躇った後、ぱたぱたと駆け出した。 その後ろ姿を奏は見送る。 とうとう手放してしまった愛しい少女の遠ざかっていく姿。 華が視界から消えると、奏は目を瞑った。 「わかってた。わかってたさ。手に・・・入るはずが無い。・・・でも、最後の悪あがきくらいは、認めてくれる、だろ?」 壁にもたれた奏の頬に一筋、涙が流れ落ちた。 奏と華の間に引かれた、幼馴染という境界線。 それをこれ以上踏み荒らすことは――――奏には、できなかった。 *** 華は走っていた。いつも通いなれた道を必死で。 ゆうきのマンションへと向うその距離が、とても長く感じる。 途中、何度か人にぶつかり。その度に華は謝りながら。 それでも立ち止まらずに。 息が、切れる。漸くマンションの影が視界に収まったとき、華はやっと走る速度を緩めていた。 ―――鍵、置いてきちゃった――――。 そのことに華が気づいたのは、既にゆうきの部屋の前に到着したときだった。 鞄は、家の門前に置きっぱなしである。奏に抱きしめられたときに、華の手から鞄は滑り落ちていた。 鍵が閉まっていたら。そう考えて、華はドアノブに掛ける手を伸ばせずにいた。 果たしてチャイムを押してゆうきが出てきてくれるか、そう思うと胸が痛くなる。 「でも、ここで。ここで、がんばらなきゃっ」 自分に勇気を与えるため、華は合えて口に出してみた。 少し、がんばれる気がした。ゆっくりとドアノブに手を掛ける。 ガチャンッ。 それは、抵抗なく回った。廻したまま、華の動きが止まる。 もう、一歩。華は激しくなる動悸を感じながら手を、引く。 扉が―――開いた。 華は一つ深呼吸をすると、勇気を振り絞り、玄関へと足を踏み入れた。 玄関から伸びる廊下にはぼんやりと灯るランプ。 突き当たりにあるリビングに灯りは無かった。 華は、慣れた感覚を頼りに薄暗い廊下を進んでいく。 そして、突き当たったリビングへの扉をそっと開けた。 開かれたカーテンから、月明かりが差し込んでいる。 その中に、ゆうきは、いた。 リビングの中心に据えられたソファ。 そこに月明かりを背に、一人煙草を燻らせているゆうきの姿。 華がきていることになどとっくに気づいていたのであろうゆうきは、しかし華を見ようとはしない。 その様子に、華はただただ立ち尽くすしか・・・できなかった。 許してもらえないかも、しれない。 華はそう思っていたが、完全にいないような扱いを受けるのは、かなり辛かった。 どう声をかけていいのかすらわからずに、制服のスカートを握り締めながら華はリビングの入口で俯く。 どれだけたったのか。華には果てしなく長く感じた時間。 だが、実際にはそれ程時間はたっていなかったのかもしれない。 ゆうきが不意に煙草を灰皿に押し付け、火を消した。 煙草を吸っているゆうきがを見るのは初めてだと、華はこのとき漸く気づいた。 吸っているのは知っていた。でも、ゆうきは華の目の前では決して吸うことは無かったのだ、いままでは。 そんなどうでもいいことを考えながら、華は目頭が熱くなるのを感じる。 今泣くのは卑怯だ、その意識だけが華の涙を留めていた。 「しばらく、顔を見せるなって言っただろう。」 溜息をつきながら、ゆうきが低く呟く。 相変わらず自分を見ようとはしないゆうきの態度に、華の眼に涙が滲む。 きつく唇をかみ締め、華は泣き出しそうになる自分をなんとかこらえた。 顔も見たくないほど―――自分はゆうきに拒絶されている、その事実が華の心を刺し貫く。 きりきりと痛む胸を抱えながら、華は自分の足元だけを見つめていた。 弁明する言葉は、喉に張り付いたまま―――いくら華が努力しても、言葉として発することができない。 何度か口を開きかけ、その度に閉じる。それを幾度が繰り返したとき―――― ふと、華に降りかかっていた月明かりが、翳った。 「―――馬鹿だな、華。せっかく逃がしてやろうとしてたのに。」 抑揚の無い声が、華の上から振ってくる。 「え?」 気づくと。ゆうきが目の前に、いた。 無表情に華を見つめているゆうきが、華に向けて手を伸ばしてくる。 瞬きしながらゆうきの動きを追っていた華は――――――ゆうきに腕を引かれ。 何がなんだかわからないうちに、背中からソファへと沈み込んでいた。 |
| Back ‖ Next ラヴァーズ・ラインINDEX |
TOP ‖ NOVEL |
Copyright (C) 2003-2006 kuno_san2000 All rights reserved. |