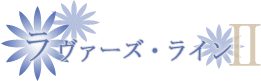 08 |
「ゆ・・・きちゃ・・、な、に?」 ゆうきの手により、肩を押さえつけられ。 起き上がることもできない華は、ゆうきを見上げながら小さく呟いていた。 月明かりを背に浴びてゆうきの表情は陰になっている。 はっきりとはしなかったが、じっとゆうきに見られていることを華は肌で感じた。 抵抗せず、ゆうきの下にいる華の体に、ゆうきの手が―――触れてくる。 「――――っ」 華が小さく息をのんだ。 ゆうきが何をしようとしているのか――――華は理解する。 ―――ど、どうし・・・て?怒ってる、から? ゆうきの手が華の足にかかり、すっと撫で上げた。 ぞくりと華の肌が粟立つ。 そのままスカートの裾から入り込んでくる熱い手の感触に、華は漸く制止の声を上げた。 「まって・・・ゆうきちゃ・・・」 しかし、口を開いた途端。ゆうきが華の上にキスを落とし、舌を絡め取られた。 「ん・・・ん・・・」 華の喉が動く。苦しさに僅かに身をよじるが、ゆうきの身体が圧し掛かっており華は顔を背けることしかできなかった。 はずされた唇の端から華は苦しげに息を吸い込む。 ゆうきが、酷く怒っていることを華は感じていた。 胸がきりきりと痛む。 何故、ゆうきが華を抱こうとしているのはわからなかったが、これが最後になるのかもしれない―――漠然と華は思っていた。 ゆうきの愛撫が華を翻弄する。 決して乱暴なことはせず、ゆうきは華をどんどん追い上げていく。 体の中が、熱くなってくる。意識せずに、華の口から甘い声が漏れていた。 華のその変化を感じ取ったのか、ゆうきの指が華の中に差し入れられる。 「あっ・・・や、だ」 自分の変化に気づかれたことが恥ずかしくて、華はゆうきの手を捕まえようと腕を伸ばした。 「いや、じゃないだろ?華。」 低く押さえたゆうきの声。 華はゆうきの射竦めるような視線とともに、伸ばした腕を掴まれていた。 *** 「ん・・・あぁ、ん、く。」 華の口から甘い声が漏れている。 あれから何度も抱いた。 例え心が拒んでいても、ゆうきは華を陥落させる術をすでに手中にしていた。 「ゆ、ぅき・・・ちゃ・・・」 「華・・・・」 切なくゆうきを見上げてくる、華。 何も知らなかった華を咲かせ、いままた強引に摘み取ろうとしている。 ―――それでも、はなしたく、ない。 華の体が潤っていることを確かめ、ゆうきは決意した。 スーツのズボンに手を掛け、ボタンをはずしジッパーを下ろす。 「華―――――。」 そのまま華の中心へとゆうきは自身の高ぶりを押し当てた。 「!?」 華の驚愕が、ゆうきにも伝わってきた。 だが、ゆうきに止めるつもりはなかった。 「ん・・・・ん・・・。」 華の中に進入を開始すると、華の口から小さく喘ぎが漏れる。 そのまま華の中を進んでいく。 「ん、ゆ・・・き、ちゃ・・・」 途切れ途切れに華がゆうきの名を呼ぶ。 遮るものの無い熱い感触。華を直に感じる。 もうゆうきに――――華を手離すつもりはなかった。 華がやってこなければ手放そうと思っていた。 しかし、華はゆうきの元へやってきた。 もう放さない。奏にも誰にも、渡さない。 たとえ、どんな手段を使っても―――――――。 ゆうきは、避妊――――していなかった。 華の最奥へとたどりつき。ゆうきは、そこで一旦動きを止めた。 「どうして―――お前じゃないと、駄目なんだろう。」 ぽつりと落としたゆうきの言葉に、華の目が見開かれる。 こんな馬鹿げたことをしてまで、華をつなぎとめようとしている。 自嘲的にゆうきが笑う。 怖くないはずが、ないだろうとも思う。 この行為そのものが、いつでも華にとってリスクを含んでいる。 ましてや今は・・・・、そのリスクを逆手にとり、ゆうきは華をつなぎとめようとしているのだ。 華の体が、震えている。 そうわかっていても、止められない。どうしようも無いほど、愛している。 そして愛されていると――――思っていた。 だからこそ、華が奏を選んだことがゆうきには、まだ信じられない。 だが事実、華は奏を拒まなかった。 もし、奏が先に華に思いを告げていたのなら―――華は俺を受け入なかったのだろうか? ふとゆうきは尋ねてみたい衝動に駆られ「―――ひとつだけ、聞いてもいいか?」と華に向けて囁いていた。 華がゆうきをしばらく見つめた後、小さく頷く。 「もし、奏がオレより先に思いを伝えていたら――――その時、奏を選んだ?こうやって、奏に抱かれた?」 華の体が、びくりと震えた。小さく息を呑んだ気配を感じる。 ゆうきに組み敷かれながら、華が激しく左右に頭を振っていた。 「――――っ!ちが、うから!ゆうきちゃん、だからっ。ゆうきちゃんしか、選べなかったから。―――だから、私、奏・・・傷つけて・・・選べなかった・・・から。」 始めは激昂していた声が、次第に小さくなっていく。 最後は、消え入るように呟かれ、華は口を噤んでしまった。 「――――華?」 華の言葉に、ゆうきが違和感を感じる。 すべて過去形で言われている、そうゆうきが気づいたのは、すぐだった。 「華、お前――――いつ、奏に?」 ―――告白された?言外にゆうきは告げ、華の様子を見守る。 この間、橡が言っていた日、華と奏が抱き合っていた時であれば過去形で話されるわけが無い。 やや言い淀む華の髪をそっと撫で「華?」とゆうきが問いかけた。 華がゆうきから視線を逸らす。 「―――――中学の・・・卒業式の日。」 ゆうきは呟かれた華の言葉に、絶句した。 華の今にも泣き出しそうな顔。 思ってもいなかったことをいわれ、ゆうきが動揺する。 「どういう―――」 ことなんだ、といいかけ、ゆうきは華の中から身を引こうとした。 「んっ、あ・・・や、ゆうき、ちゃんっ」 が、華が小さく声を上げ、ゆうきの腕に縋り。ゆうきを引き止めた。 「華――――。」 「や、だ。ゆうきちゃん、離れちゃ、やぁ・・・」 離れたらもうゆうきが華に触れないとでも思っているのか、華はゆうきの片腕に両手を廻して放さない。 ゆうきはそんな華の体温を腕に感じながら、ここ数日の華の様子と行動、それらをすべて思い返していた。 ―――奏を、選べなかった? 先ほどの華の言葉が蘇る。奏と抱き合っていた、奏とキスをして、奏を受け入れて。 では何故いま華はここにいるのか。 華が奏を選んでいたなら。奏は決してゆうきのもとへ華をよこしたりは、しない。 熱くなっていた頭が、ゆっくりと冷えてくるのをゆうきは感じた。 ゆうきの下では、華が小さく震えている。 愛おしさが、ゆうきを支配する。 「・・・これが、最後なら・・・最後まで・・・して、欲し・・」 ぱたりと、ソファの上に華の涙が零れ落ちた。 ―――・・・最後だと、思ってたのか・・・。 華が抵抗しないのを不思議に思ってはいたが、まさかそう考えていたとは思わなかったゆうきが、軽く溜息をつく。 「馬鹿だな、華・・・本当に。」 掴まれていない方の手で、流れ落ちている華の涙をゆうきはそっと拭った。 華が「――――どうせ、馬鹿、だも・・・・」といいながら、ぼろぼろ泣き出している。 「最後まで、するけどな。これが、最後じゃないから。」 「え?」 ゆうきを見上げている華の頬を流れる涙。顔を近づけ、ゆうきはそれを舐め取る。 びっくりしたような華の表情に、ゆうきがかすかに笑みを漏らした。 ゆうきには、最後にするつもりなどもともとない。 それどころか、華を縛り付けるために行為に及んでいるのである。 だが、さっきの華の言葉。中学の卒業式で、奏に告白されたということ。 それがどうやら今回の元凶らしいと、ゆうきは華を見つめながら再び考えていた。 まだ、すべてがわかったわけではない。 しかし、華の性格と、奏の長年の思い。それに奏の思いを知っていた華が、ゆうきと付き合いだしたこと。 それらを組み合わせていけば――――今回の華の行動の意味が、ゆうきにはわかった気が――――した。 「ゆうき、ちゃん?」 華が不安そうにゆうきを見つめている。 ゆうきは華の中から引きかけていた体を、再び深く沈めた。 「ん・・・あぁ・・・。」 華が甘く啼く。 ゆうきがその声に、煽られる。 「最後まで・・・・して、いいか?」 このまま止めるつもりは無かったが、ゆうきは華の耳元でそっとたずねる。 瞳を潤ませた華が、小さく頷いた。 絶頂の一歩手前、ゆうきは華の中から自身を引き抜く。 華の絶頂を迎えた甘い声と姿に――――ゆうきも達していた。 ソファの上で華が荒い息をついている。 ゆうきが身を起こすと、華が不安げにゆうきの姿を目で追ってくる。 「すぐ、戻るから」と華の頭を軽く撫でてやり、ゆうきはバスルームへと向かい、すぐに温水で濡らしたタオルを持ってリビングに戻った。 ソファに座って、華がブラウスの前を両手で押さえている。先ほどゆうきがボタンの幾つかを飛ばしてしまったのだ。 ソファの傍には乱雑に脱ぎ捨てられたスーツの上着、床には華の下着が散らばっている。 じっと座り込んでいる華の傍に自らも腰掛けると、ゆうきは華の首筋にそっとタオルを当てた。 華が小さく身じろぎする。ゆうきの手から逃れようとするかのように、ソファから立ち上がろうとした。 だが、ゆうきはそれを許さず、華の腰へ手を廻し、再びソファに座らせる。 「ごめ・・・・なさ・・・。」 華が俯きながら、小さく言った。 その儚げな姿に、ゆうきが眼を細める。 頭に血が上り、逆上して・・・・華を怖がらせた。 冷静に考えれば、何かあるとわかったはずだ。 数日前、急に華がゆうきの顔が見たいと、やってきている。 ―――あの時は、まだいえないといっていたが。 思えばあれは橡が華と奏を見たと云っていた日だと、ゆうきは華に気づかれないように溜息をついた。 「華、ちゃんとこっち、見て?」 華の顎に手を掛け顔を上げさせると、ゆうきは華を安心させようと小さく笑いかける。 華が不安そうに瞳を揺らしながら、それでも目を逸らすことなくゆうきを見つめ返す。 ゆうきが華に、やさしくたずねた。 「奏にスキだって、いわれたんだな?中学の卒業式に。」 「―――うん。」 やや躊躇った後。こくりと、華が頷く。 「断ったんだろう?」 ゆうきは、間を置かずに次の質問を口に乗せた。 これにも華は「うん。」といいながらこくりと頷く。 「オレと、こういう関係になったっていった?」 「―――ゆうきちゃんの、彼女になったって。」 さすがに抱かれたとはいえないだろうな、と思いながらゆうきは苦笑した。 ―――だが、多分奏にはわかっていたはずだ。華が、女になったことが。 近しい関係にある者が、近頃の華を見れば。おそらくその変化は一目瞭然である。 ゆうきの中で、先ほどの予想が確信に変わっていく。 小さく息を吐き出しながら、ゆうきは再び華の首筋にタオルを這わせた。 華の体が少し強張る。だが、今度は拒絶されなかった。 「で、抱きしめられたのか?」 華の胸元へとタオルを滑らせながら、ゆうきは自分の予想を確かめるべく質問を続ける。 「え?・・・どうして、知ってるの?」 華が数回瞬きした。 その様子に、ゆうきは苦笑しながら「橡が、見たんだと。」と情報源を明かす。 華は、「橡さん?」と小さく呟きながらも、納得したようだった。 「で、華はそれを拒まなかったわけだな。」 「―――う、ん。」 申し訳なさそうな華。ゆうきは、タオルを華のブラウスの中に差し入れる。 「華、手・・・どけて?」ブラウスの前を押さえている華の手をやさしく握り、ゆうきは華の手を下ろさせた。 下着をまだつけていない華の胸が顕になる。 華の頬が朱色に染まる。だが、華がゆうきの動きを妨げることなかった。 「今回もか?奏に、いわれた?だからキスした?」 丹念に華の体を清めながら、ゆうきの質問は核心に迫っていく。 「――――――。」 華が、黙り込んだ。―――――それが、答えだった。 ゆうきは自分の予想が正しかったことを確信する。 奏は、華の中にある罪悪感を利用したのだとやや呆れ気味に溜息を落とした。 ゆうきの予想は、正に的を射たものだったのだ。 ―――奏の奴、つけ込みやがって。 ゆうきは、やっぱりもう一発殴っておくべきだったと、物騒なことを思いながらも顔には出さ無かった。 これ以上華に怖い思いはさせたくない。それでなくとも先ほど強引に押し倒してしまったのだ。 その上、高校生の華に対して避妊するつもりも無かった。 最終的にそれは思いとどまったとはいえ、華に怖い思いをさせたことに変わりはない。 ゆうきの中にあった押さえようの無い激情は、今はもう大分解きほぐされていた。 *** ゆうきのたずねてくる質問に答えている間、華はゆうきの怒りが静まっていくのを感じていた。冷静に華の言葉を聞き、華にやさしく尋ねてくる。 すれ違っていた心。それが徐々に合わさっていくような感覚。 黙り込んでいる華の体を、ゆうきはタオルで拭っている。 華はゆうきに身を任せながら、ひたすたじっとしていた。 何も着けていない胸をゆうきに見られている。 羞恥から、華は全身が燃えるように熱い。 ふとゆうきの手が止まった。手元に向いていたゆうきの視線が華を捉える。 華はゆうきの真剣な面持ちに、こくりと喉を鳴らした。 「奏の要求が、あれ以上になってたらどうしてた?」 責めるような口調では、なかった。ただ静かに、ゆうきが華に尋ねた。 「―――あれ以上?」 意味がわからず、華が小さく首を傾げる。ゆうきが小さく笑う。 「抱かれてた?」 「――――っ!?そ、そんなこと、できな・・・」 云われた言葉の内容に、華がふるふると頭を左右に振りながら否定した。 奏に抱かれる、そんなことは考えられなかった。 今までもこれからも、奏は大切な幼馴染。触れるだけのキス、それが限界。 「だろう?」 華の頭をゆうきがやさしく撫でる。華の瞳から、涙が零れ落ちた。 改めて自分が奏にしたことの酷さを、華は思い知る。 中途半端にしか応えられないのなら、はじめから拒むべきだった。 幼馴染としての奏を失うことが、やっぱり怖くて。だから、奏の願いを受け入れて。 でも、それは――――・・・ 「――――うん。・・・うん、私が・・・馬鹿だったと、思う。ゆうきちゃんに妹としか思われてない、それと同じ思いを奏もしてたんだって思って。なのに、奏を選べなくて。私、結局また奏を・・・傷つけて・・・。」 両手で顔を覆いながら、華は今までの心情をゆうきに告白する。 ゆうきが華を引き寄せ、華はその胸の中に抱きとめられた。 「――――罪悪感で、応えるのは――――どっちも辛かったろ?奏も―――華も。」 華の耳元でやさしく囁かれるゆうきの言葉。 華はゆうきに抱きつきながら、堰を切ったように泣き出していた―――――。 *** 「ん・・・・・ん、く・・・、ふ・・・・・う・・・」 華の震える背中を、ゆうきの手がそっと撫でる。 泣きじゃくる華の髪に顔を埋め、ゆうきはそのまま華が落ち着くまで抱きしめていた。 「華、大丈夫か?」 華の泣き声が徐々に小さくなってきた頃合を見計らって、ゆうきはそっと声を掛けた。腕の中にいる華が、小さく頷く。 そして、ようやく華が顔を上げた。赤くなった瞳が痛々しい。 「もう、隠し事は・・・・無しにしような。」 華の頬を撫でながら、ゆうきが苦笑した。 すれ違いで華を失うのかもしれないと思うのは、もう御免だった。 こんなことになるとわかっていれば、数日前華の様子がおかしかった時に、多少強引にでもなんでも聞き出しておけばよかったと、後悔している。 華がやや躊躇った後、「うん、もう隠し事、しない。」と、こくりと頷いた。 ゆうきが華の頭をくしゃくしゃと撫でる。 びっくりしたような華の顔を見ながら「じゃあ、早速。華、ほかに隠していること、ないか?」と笑いつつ華に尋ねた。 「え?・・・・ええっと、思いつくかぎりでは、ない・・・と思う。」 ほんの少しだけ自信なさ気にいう華。 「そうか。じゃあ、思いついたらどんな些細なことでもいいからちゃんと言うこと。」 ゆうきが念押しすると、華が神妙な様子で頷いた。と、何故か僅かに首をかしげ、ゆうきを見上げてくる。 何か聞きたそうな華に、ゆうきは笑みを浮かべながら「どうした?」と促した。 「あの、ね。ゆうきちゃん、は?」 「オレ?」 ちょっと驚きながら、ゆうきが云うと、華がこくりと頷く。 なるほど、確かに隠し事という点では、華よりゆうきの方が多いかもしれない。 いままでの自身の行状を思い出し、ゆうきが苦笑する。 とりあえず、華に関する隠し事――――。ゆうきには、思い当たることが一つあった。 「そうだな。――――華、初めてキスしたのは?」 「え?ええ?・・・・えっ、と。この間、酔ってたゆうきちゃん、と。」 何のことかわからないのであろう華が、何度か瞬きする。 ―――そうだよな、多分華が覚えてるのはそれが最初。 だが、実は。華のファーストキスは、もっと前である。 「それ、間違ってるから。」 軽くゆうきが、いう。華が「え?・・・どうして?」と首を傾げる。 覚えていないのだから、当然であろう。 「華が10歳の時・・・寝込みを襲った。」 華の眼が見開かれる。 「!?――――ほ、本当、に?」 「ごめんな?」 にやっと笑いながらゆうきが云うと、華は顔を真っ赤にして黙り込んでしまった。 「ゆうきちゃん、ひどい。私、覚えてない。」 しばらくしてむっつりといわれた華の言葉に小さく笑いながら、ゆうきは再び手にしたタオルで華の体を拭き始めた。 胸のラインから、くびれた腰。 恥ずかしそうにしながらも、華はおとなしくゆうきに身を任せている。 そのまま、ゆうきが華の体を拭いていく。 だが、そのうち華の内腿あたりに到達すると、華が身じろぎして足をきつく閉じてしまった。 ゆうきが「ほら、華。ふけないだろ?」と笑いながら言うと、スカートを際どい所まで捲り上げられた格好で、華が困ったように見返してくる。 「はーな?」 笑いながらゆうきが声を掛けると、華はふるふると左右に首を振った。 構わずゆうきは、華の腿に手を掛ける。 「や、ダメっ、やだ!」 真っ赤になりながら、華の華奢な手がゆうきの手を押さえる。 しかし、ゆうきは華の変化に気づいてた。 先程からゆうきの動きにあわせるように、華が声を噛み殺していたのだ。 もっとも、そうなるように華の弱い部分にわざとゆうきが触れていたことに、華は気づいていない。 「続き、もう一度ここで?それとも、ベッドいくか?」 潤んだ眼を向けてくる華の腿に手をかけたまま、ゆうきは甘い笑顔で尋ねる。 華は恥ずかしそうに俯きながら「――――ベッド。」と小さく囁いた。 「かしこまりました。お姫様。」 ゆうきは軽く云いながら、華を抱き上げた。 |
| Back ‖ Next ラヴァーズ・ラインINDEX |
TOP ‖ NOVEL |
Copyright (C) 2003-2006 kuno_san2000 All rights reserved. |