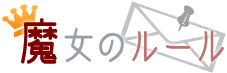 ルール01.魔法が効かないことに、私こと桜侑那が愕然とすること ならびに、柊一路の特異性について考察すること 26 |
「……えっ、な……っ、冷た!?」 ばしゃばしゃと脳天に叩きつけてくる、冷たいもの。 それが無数の水滴なのだとわかって、打っ魂消た。 なんで水? つーか、これシャワー!? ますます、なんで!? シャワーがあるってことはここはお風呂で、私はどうやらユニットバスの中にいるらしい。 しかも。しかも、だ。柊一路が、いる。 つまり。私は柊一路の腕に取り囲われ、頭上からは冷水シャワーを浴びるという珍奇な状況に何故か身をおいていた。 「……ちょっ、先輩! 冷たい、しかも苦しいですって!」 容赦なく顔に掛かる水に呼吸が苦しくなり、叫ぶ。いささか水を飲み込んで、咽こんだ。 「――正気か?」 ぐいっと顎を持ち上げられたが、水流が強くて目が開けられない。 「正気ですよ、なんですかこれ!」 口の中に流れる込む冷水を出来るだけ無視して、水音に負けないよう声を張り上げる。 きゅこっと蛇口を捻る音がして、水が止まった。 「――正気か」 確認するように言われたが、私としては、寧ろ貴様が正気か!? と問いただしたい。 ぶるぶると頭をふって目をあげる。見下ろしている柊一路も、しとどに濡れている。前髪の先から滑り落ちた水滴が、ぽたっと私の瞼にあたってはじけた。 「馬鹿魔女」 ひどく不機嫌そうに、かつ尊大に柊一路が言い放った。 「え、は? いやなんですかこの状況……って、ま……っ」 私が言い終わる前に、再びきゅこッと軽快な音がした。 また冷水!? 身構えた私の頭上から、けれど今度はぬるま湯が降ってきた。 徐々に水温が上がってくる。 おおお、温かい。生き返る――って私、服が全てびっちょびちょ。いや、もちろん脱いでるよりは断然いいんだけど。 「じゃあナ」 温かさについつい人心地つきそうになった私にくるりと背を向け、柊一路が湯船の縁を跨いだ。 ええええ、この事態の説明はなし、なわけ!? 反射的に。がしっと、柊一路の腕にしがみついていた。 「何?」 「いや何って……私が言いたんですが、それ」 「いいから温まるまで出てくるナ」 「温まるまでって……先輩は?」 どうみても、私と同じくらい柊一路だって全身濡れ鼠だ。 事実、つかんだ腕は服越しにもひんやりとしている。 虚をつかれたように、柊一路が黙り込んだ。 「――俺と一緒に入りたいワケ?」 呆れたように言われ、自分の言葉の足りなさを呪いたくなった。 「何言ってるんですか馬鹿ですか。違いますよ、先輩が先に温まって下さいってことです」 かっと頬が熱くなったのは、絶対シャワーが熱い所為だ。 つかんだ腕に力を込め、その場に一路を引き止めて湯船から出ようとする。 足元が浮かび上がったと思ったら、あっという間にベージュ色の陶製バスの底に、何故か座り込んでいた。 一旦持ち上げられ、荷物のように置きなおされたのだのだと気づいた時には、すでにバスルームのドアが開いていた。 「先輩っ」 「大人しく言うこと聞けヨ? ぐだぐだいってると――」 「言ってると?」 「俺と一緒に仲良くバスタイム」 機嫌の悪そうな口調と表情に真実味がありすぎて――逆らえなかった。 だって目がマジっぽい。なんで怒ってるんだこの男は。 「人間、素直さは美徳ダナ」 アンタはその美徳を何処に捨ててきた柊一路。 もういい、アンタが風邪引いたってしるもんか。私が看病する義理なんてこれっぽっちも、爪の先ほどありゃしないのよ! 嗚呼、だけど悲しいかな。私に弱みがある以上、そんな事になった場合、まず間違いなく呼び出されることは火を見るよりも明らかなのよおおおっ! さっさと温まって、さっさと出よう。それが最良の策だった。 ぷりぷりと怒りもあらわに、すっくと立ち上がる。 顔に張り付く髪の毛を乱雑に後ろへと押しやり、無言でシャワーの温度を上げた。 湯気の立ち上る室内。柊一路が完全に出て行くのを待って、肌に張り付いた服を苦労して脱ぐ。 ありえない、よねぇ。 男の人、しかも彼氏――カッコ仮、だけど――の部屋で、お風呂って、もっとドキドキするんじゃないの? それがどうしたことか、ドキドキはしたけど、緊張からじゃなく、むしろビックリしたからって、どんなもんなのよ。 タイルの壁に右手をついて、がっくりと肩を落としたりしてみる。 それでも絶え間なく降りかかってくる温水に、幾分か気分が和らいだ。柊一路の腕の冷たさを、ふっと思い出す。 ――そうだった。早く、出なきゃ。 頭のてっぺんから流れ落ちる温水をたどり、両手を体の縁に沿って滑らせる。 頬のラインから首、そこから腕を交差させ、鎖骨、肩――え? 閉じていた目を、ばっと見開く。 え、ええええ? だって、なに、どうして。そりゃあ、すこしは力が回復してる、けど。ありえない、でしょ。 呆然と見つめる肌に、ぱしゃぱしゃとお湯がはねる。 ……火傷したはず、なのに。ほとんど、治りかけて、る? 多少えぐれていたはずの皮膚は、やや黒ずんでいるものの、つるりとしていた。 そういえば水もお湯もぜんぜん染みなかった。貼られたはずのガーゼも、してない。 あたりを見回したけど、それらしいものは落ちてない。 ってことは、ここに放り込まれる前にはもう、治ってた? ためしに、指先に少しだけ力を集中してみる。集まりかけた不可視の力は、凝縮しきる前に飛び散り、霧散した。 やっぱり、駄目。散っちゃった。まだ、回復しているわけじゃあ、ないん、だ。 じっと、手のひらをみつめる。 不可思議にことばかり、だ。そもそも、私はどうしてここに放り込まれたんだろう。 シャワーを止めた。水のはねる音が消え、室内に静けさが満ちる。 たしか、柊一路に今日の出来事を話していた、はず。それは覚えている。 その後、なにかを聞かれた気がする。……けど、何を? これは、まさか、そういうことなの? とんでいるのは――私の記憶ってこと、か。 力まかせにシャワーカーテンを引き開けると、篭っていた蒸気が少し和らいだ。 壁にかかっていたバスタオルを体に強く巻きつけ、曇ガラスのはめ込まれたドアをこれまた力いっぱい開け放つ。 蝶番がけっこうな軋み方をし、アルミの桟が震える。ええい、嫌味のひとつやふたつは覚悟の上だ。 まだ水気を含んだ素足で、短い廊下を踏みしめる。 「柊先輩!」 最初に目がいったのは無人のローソファーだった。 ……あれ? 左右を何度か見直す。もともとそう広い場所でもない。 全体を見尽くしてしまうのに、そう時間がかかるはずもなかった。 ……柊一路は? ようやく、事態に気がついた。 いな、いないとかあああ! どこいった、あの男っ、まだ悪魔がいるっていうのに、フラフラ出歩くとか、ありえないでしょおおおおっ! お、落ち着くんだわたし。そう、こんなときこそ文明の利器! 電話だ、電話! ソファの傍に置かれた自分の鞄から、シャキーンと効果音がしそうな勢いで取り出したる携帯電話。 押し付けられた柊一路の番号を、ありがたいと思う日がこようとは。 ぺたりと床に座って、電話帳から柊一路の番号を呼び出す。 何度目かでコール音が途切れ、通話に切り替わった。もしもし、と呼びかけるも、電話の向こうは僅かにノイズの混じった、無反応。 「……あの、柊先輩? ですよ、ね?」 掛け間違ってないよな、と恐る恐るたずねてみる。 『なに』 いつもより五倍増し位の無愛想声だった。 でも出てくれてよかった。とりあえず無事なようだ。 「なに、じゃありませんよ。いまどこですか? ふらふらしないで家にいてください」 『なんで』 な、なんでって! そりゃ危ないからにきまってるじゃないの! 「とにかく、危ないですから」 『アンタと居ても危ないことにはかわりないダロ』 「そりゃ、そうですけど……でもいざとなったら守りますから」 『どうやって』 「術具を使って結界を張ることくらいは出来ますし、いざとなれば盾になることもできます」 とりあえず自分が怪我をする分には、自分で直せるから問題ない。 万全とはどうしたっていい難いけど、今はこの程度の対策が精一杯だ。 ふぅっとこれ見よがしのため息が、電話越しだって言うのにはっきり伝わってきた。 『その部屋、今日は好きに使っていいヨ。着替えは適当に漁ればいいし、スペアの鍵は机の上だカラ』 「え……ちょっ、先輩?」 ぷつっと通話の切れた音だけが耳に残る。 ちょ……っと待て、勝手に切るなあああ! 間髪いれずリダイヤルした。つながらない。もう一度。やっぱり駄目。 その後も、二三度リダイヤルしてみたが、最後にはとうとう電源が切られているか電波の届かない場所にっていうお決まりの文句が流れてきて、あきらめるよりなかった。 電話を持った手が、腿の上にぱたりと落ちる。 悪魔を撃退するような、とんでもクマを持っていた柊一路のことだ。多分、無策で出て行ったわけじゃないだろう。 ――私は、信用されてない、か。 やっぱり、頼りないよね。そりゃそうだ。 魔女としての力が無い今の私は、柊一路にとって、無用の長物であるに違いない。 ぶるっと寒気がした。気がつけば、濡れたままの髪が、冷え切っていた。 |
| Back ‖ Next 魔女のルール INDEX |
TOP ‖ NOVEL |
|
Copyright (C) 2003-2011 kuno_san2000 All rights reserved. |