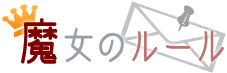 ルール01.魔法が効かないことに、私こと桜侑那が愕然とすること ならびに、柊一路の特異性について考察すること 31 |
隙間無く地面を覆った落ち葉や草に、足をとられる。 積み重なった葉っぱで思いっきり滑り、慌ててそばの木にしがみつくなんて失態をすでに二度、やらかしていた。 ――走りにくいったら! 黒猫の後を追いながら来たときは、さすがに全力疾走なんて真似はしてなかった。 けど、いまは違う。そりゃあもう、違う。 息は切れるし、喉も横っ腹も痛むし、両手のひらは木の幹でひっかけて傷だらけ。 それでも。 あんな後悔をするよりは全然マシ。柊一路が傷つく姿を見るのは、どうしてだか嫌なんだから、仕方ない。 だから。 こんなに必死になっちゃってるのは、柊一路のためなんかじゃない。間違いなく、自分のため、だ。 「……っ」 三度目の、見事な横滑り。 華麗な体捌き、なんてものが出来るはずも無く、無様に傍の木立にしがみついてしまった。 できるだけ魔力を消耗しないように体力頼みの捜索を決行してみたけど、きっついな、これ。 過酷な道のりに、魔法使っちゃおうかなー、なんて甘美な誘惑がむくむく膨れ上がってくる。 「……はー……」 ぐったりうつむいた自分の口からこぼれるのは、あきらめのため息。……わかってる、わかってます。 この先何があるかわからないから、安易な誘惑にふらふらと乗るわけにゃあ行かないってことくらい。 ぐっと唇を噛み締める。甘い考えを断ち切るため、ぶるっと頭を振る。 それに、私があの館に入り込んだ空間の裂け目は、もうすぐだったはず。 黒猫を追って入り込んだ学校裏の雑木林。ここに足を向けたのは、考えあぐねた結果の、半ば勘。 だけど、曲がりなりにも魔女の勘、だ。手がかりが無い以上、賭けてみるしかない。 「……?」 なに、あれ? ふと目に留まったのは、この場にはそぐわない、さくら色。 ぐっと目元に力を入れる。 こんもりした塊。ふかふかしてそうな質感は、毛糸のようにみえる。 記憶を手繰るまでも無く、極々最近、目にしたものだ。 黒猫を追って入り込んだ屋敷の中で見た、手編みのカーディガン。 どうしてこんなところに……。 罠? 近づいていった途端、ロープで逆さづり――なんてオチはご免被りたいところだ。 つま先で地面を探りながら、そろりと近づく。一歩、二歩……何かが起きる気配はなし、と。 落ちているのは破れたカーディガンで間違いない。 遠目じゃ気づかなかったけど、黒いすすのようなものが所々についている。 まあ、この際、汚れはいいんだけど。これさぁ、明らかになにか入ってるよねぇ。 カーディガンだけにしちゃ、もこもこしすぎてる。 ――ええいっ、ここまできて罠ってこともないでしょ。 逆に意表をついてくれる! ってな心境で、さくら色の小さな袖口をがばっとひっぱりあげた。 「……黒猫?」 落ち葉に半ば埋もれるように、黒猫がぐったりしていた。 ひざまずき、顔を覗き込むと、焦げ臭い匂いが鼻を突く。 ちりちりと縮こまった髭は垂れ下がり、いつもは生意気そうに閃いている瞳はぎゅっと閉じられている。 呼吸は――大丈夫。胸のあたりが上下している。 「黒猫っ」 強めに呼びかけてみる。下手にゆすると容態を悪化させるかもしれない。 ぴくっと髭が動く。片目だけがゆっくりと開いた。 「……ひよっこか……、すまん、はじき出された」 漸うというありさまで黒猫はのっそりと身じろぎし、頭を上げた。 「はじき出されたって……あの館?」 「ああ」 そんな馬鹿な。あの館は、多分この黒猫を使役している、いわばご主人様の持ち物だ。 そうであるなら、使い魔にとってはホームグラウンド。もっとも力を発揮できる場であるはずなのに。 「なにがあったの」 「不覚だった。結界が……あの悪魔を弾かなかったんだよ。よく考えりゃあ当たり前だったんだけど、な……。契約の効力を甘く見すぎた俺のミスだ」 結界が、悪魔を弾かなかった? 結界よりもアイツの力が勝ったって事? まるで納得がいかない。そりゃあ、あの悪魔が万全の状態だったっていうならわかる。 けど、だいぶ力はそいだはず。おそらく今の回復具合は五割以下だろう。 現に、送り返しそこなった後のアイツには、最初に正体を現したときの圧迫感がなくなっていた。 あの結界が、その程度で破れるとは思えない。それに、契約の効力って……。 「どういうこと?」 「……言えねぇ」 げほっと黒猫が咳き込む。白い牙から、鈍い赤銅色がぽたりと地面に落ちた。 この期に及んで言えないってアンタねぇ、と言い掛けていた文句が引っ込む。 ちっ、さすがにここまで弱っている相手を責められるほど鬼じゃあない。 ああもう、折角ここまで体力勝負で来たってのに。 意外に小さな身体を持ち上げ、胸に抱え込んだ。シャツにじわりと血がしみこんでくる感覚にぞわりと肌があわ立つ。 「……おい、無駄に力を使ってんじゃねぇよボケ」 悪態はついても、黒猫はぐったりとおとなしい。私を拒絶するだけの体力も残って無いくせに、強がってんじゃないっつーの。 「うるさい黙れ」 更にきゅっと抱きしめる。腕の中で苦しげな呻き声。 ごほっと咳き込んだ体が小刻みに震えてる。 「ばっかだな、お前はよ」 けけっと笑う声に力が無い。まるりと全部、強がりだ。 まったく、さっさと元気になってくれなきゃ文句も言いづらくっていけないわ。 意識を黒猫に集中させ、口の中で治癒の呪文を唱える。 触れている箇所の温みが増すにつれ、黒猫が淡い光に包まれていく。 全体を青い炎にも似た強い光が覆い尽くした後は、徐々に薄れ最後には溶けるように消えうせた。 腕の中では、乱れていた呼吸と鼓動が、規則正しさを取り戻していた。 ふうっと安堵の息をつく。少し力が抜けたその僅かな隙に、黒猫がするりと逃げ出した。 「あ、ちょっと」 慌てて引き止めるも、小さな背中はすでに私の目線上、数歩先だ。 「もう治った」 くるりと振り向きざま、ちりんと鳴った鈴の音が黒猫の声にかぶる。 このアホ猫。んなわけあるかっつーの! 血は止まっているけど、完治率は精々半分、だ。いまの私じゃあ、一回の治癒呪文でこれが精一杯。だから、せめてもう一回は。 「あのね、まだ途中」 「お前、最初の目的を忘れてねぇか」 呆れたような、いや、多分間違いなく呆れている声だった。 言葉に詰まる。私の当初の目的――それは、柊一路、だ。 はああっと息を吐く。 ……傷口は、ふさがってる。血も、止まってる。立ち上がって歩いている。 確かに、この辺が落としどころだ。 これ以上あれこれ言っても無駄だろうし、なにより助けにいかなきゃならないバカが、まだ一人いる。 無事……だろうか。 湧き上がるいやな不安感。錐で突かれたように胸が痛む。 膝をついた近くにあったカーディガンをすこし持ち上げ、そっと撫でる。手のひらに黒ずんだ赤がかすれた後を残す。 上着に染みた――血、だ。 すうっと身体が冷たくなった。 「魔女、入り口をつなげる。いけるか」 「誰に言ってるの。いけるに決まってるでしょう」 必ず、柊一路を助ける。 鈍い赤に染まった手のひらを見つめる。決意を込めてぎゅっと握り締めた。 大丈夫、あんな憎まれっ子がそう簡単にくたばるわけが、ない。 自分を納得させ、ふと視線を戻す。黒猫が、じっとこちらを見ていた。 「なに?」 「お前、それがどういう気持ちか知ってるか?」 は? どういうも何も……。 「みすみす見殺しには出来ないっていう人道的気持ちだけど?」 ああ私ってば、なんて模範的一般人。魔女だけど。 ちょっぴり悦に入る私の前で、黒猫がきょとんとしていた。なに、その間抜け面は。 「ぶはっ、うはははは、マジかお前! 成長してねえええぇ」 「は?」 笑われる意味がわからない。大げさかもしれないけど、仮にも私は命の恩人。 その本人を前にこの態度ってどうよ。成長してない? ずいぶんと聞き捨てならないことを言ってくれる。 ……ふ、ずいぃぃぶんっと、元気そうねぇ。まったく喜ばしいわ、こんちきしょう。 「傷口が開いても今度は自力で何とかしなさいよね」 笑いすぎてぜいぜいしながら髭を揺らしている黒猫に、冷ややかな一言を投げつける。 ああうん、いやいや、なんていいながら、黒猫が目元をこすった。 笑いすぎて涙まで出てきたらしい。 「なんかまあ――安心した。お前やっぱり……の孫だわ」 「――え?」 いま、なんて? 「よし、開くぞ」 「ちょっと、まって、いま私のこと、誰の孫って」 「餞別だ。持ってけ」 どこから出したものやら、黒猫がひょいっと何かを放り投げた。 ひらひらと頼りなく舞った白いものを、慌てて両手で受け止める。 瞬間、ぬるりとした圧力に包まれた。 空間がねじれる。本来繋がるはずの無い場所から場所へ。 眼を閉じる。いまの私に、ねっとりと交じり合う色の混沌は悪酔いの元にしかならない。 仕方が無いとはいえ、他人の開いた入り口を通るのは、やっぱり愉快なものじゃあ、ない。 何度かの深呼吸。そして。 唐突に。すべての違和感が消えうせた。 ひんやりとして、埃臭い空気。 まぶたを持ち上げると、薄暗い廊下が続いていた。 「無事越えられたみたい、ね」 ほっと肩の力を抜く。罠の気配はなさそうだ。 が、私が入り込んだことはもう相手には気づかれてる、はず。 寧ろ何の障害も無く入り込めたことが妙だった。 まあでも、とりあえずは差し迫った危機はない、か。 「……餞別、ねぇ」 最後に黒猫が投げて寄こしたものを、首をかしげて見つめる。 両手で挟んでいたものは、二つ折りにされた少し厚手の紙だ。 ずいぶん年季が入っているのか、角はだいぶ傷んでいるし、紙自体がやや黄ばんでいる。 ぴらりと開くと、少し色のあせた写真だとわかった。 満開の花が色とりどりに咲き乱れる庭で、小さな子供が二人。 ひとりは――多分、私。 もう一人は、栗色の髪をした色の白い――女の、子? 「……い……っ」 ずきん、と頭が痛んだ。こみ上げる不快感に思わずうずくまる。 な、んなの、これは! うううう、気持ち悪い、吐きそう! 「あらいやだ、あの黒猫ったら。ルール違反ギリギリじゃないの、写真なんて」 陽気な、それでいて不穏な気配をはらんだ声が頭上から降ってきた。 無理やり顔を上げると、あの悪魔が目の前に、いた。 「……あん、たっ」 ぎりっと睨みつける。顎に触れてきた繊細な指先が、私をさらにぐっと上向かせた。 押さえがたい吐き気に、喉が鳴る。 「苦しい? 思い出そうとするからよ。全部忘れてしまえばいいのに」 ガラス玉のような目。口元にうっすらと浮かぶ笑み。 嫌悪感だけがふつふつと募る。 「人に指図されるなんてまっぴらだわ。ましてや悪魔の思惑通りに踊らされるなんて反吐が出る」 「ふふ、強気ねぇ。じゃあ、少し遊んじゃおうかしら」 悪魔の遊びなんて、厭な予感しかしないっつーの。 立ち上がって飛び退こうとした私の二の腕を、悪魔がつかんだ。 足を踏ん張ったにも関わらず、引き寄せる力の強さには敵わなかった。 くそっ、見た目は絶対私の方が力強そうなのに! 「大丈夫、痛いことなんてしないから」 そんな胡散臭い言葉、信じられるかあああぁ! 振り払おうと、力いっぱい腕を動かした。あっさり解放され、反動で体勢が崩れる。 気づいたら、床に倒れこんでいた。その私の上に、悪魔がのしかかってくる。 ……これって、押し倒されてる? いやいやいや、そんな馬鹿な。 愕然としているうちに、柔らかなものが唇に押し付けられた。 ……ちょっ、ちょおおおおおっ!? ちゅ、ちゅー? ちゅーされて!? 「ん、ん……っ、んんんっ」 は、はな……離せぇぇぇ! 身体の芯まで凍えるような唇の冷たさに、鳥肌が立つ。 「この姿が厭? じゃあ、オスの姿になってあげましょうか?」 耳元でささやかれ、更なる寒気に襲われた。 お、おす? そういうことじゃない! いや、寧ろ男になられたほうが問題がある気がする! ま、魔法、意識を集中して、とにかく意識を――ぬあああ! 集中なんてできるかああぁ! じゃあ、呪文、ええっと、とにかくこいつを振り払える呪ならなんでもいい。 「呪文は無しよ?」 薄い手のひらが私の口を覆い、声がくぐもった。 先読みされた悔しさと、自分の迂闊さに腹が立つ。 更に。冷たい手が服の裾から差し入れられ、喉の奥に悲鳴が引っかかる。 ちょ、ちょおおおおお、マジか、マジなのかこいつ! うう、これはやりたくないんだけど、間違いなく、手段を選り好みしていられる状況じゃない。 ささくれ立った廊下の板に手のひらを思いっきり擦りつけた。 指先に鋭い痛みが走る。床に触れた指先を動かし、埃の上に円と幾つかの文字を描く。 細かい棘に切り裂かれた皮膚からは多分、血が出ている、はず。 血と埃で彩られているであろう魔方陣の上に手を翳す。 指先を中心に、ちょっとした爆発くらいの炎が上がった。圧し掛かっている身体を払いのけるように腕を振る。 うっとおしい重みの無くなった身体を起こすと、小さな火花が私の周囲でぱちぱちと弾け散った。 「どこにいるの」 板張りの床に転がって咳き込んでいる意外に小さな背中に、ゆっくり尋ねる。 「何が?」 まだ余裕を見せる声音に、問答無用で力をたたきつけた。 細い足の間近で、床材が爆ぜる。 「怖いわねぇ。キスされて怒っちゃった? 操を立てるほどの男でもないと思うけど」 「ずいぶん古風な言い方をするのね。そんなんじゃないわ」 腰に片手をあて吐き捨てる。そもそも操を立てるとか、意味がわからん。 どうして私が柊一路に対してそんなことしなきゃならないのさ。 「彼氏なのに?」 あでやかな笑顔で切り返され、冷や汗が出た。 ――しまった。柊一路は一応、彼氏。対外的には立てなきゃ不味い関係だ。 「ふぅん……。なぁんだ、まだつけいる隙は充分なんだ?」 くすくすと忍び笑い。 肩越しにこちらを見つめてくる表情は、なんでって思うくらいうれしそうだ。 予備動作なく、彼女が立ち上がっていた。 ぎょっとする間もなく、至近距離に小ぶりな顔が迫ってきて、けど、動けなかった。 「……柊一路は、どこにいるの」 「さあ。捜し出してみれば?」 まさに悪魔の笑み、だ。三日月形に細められた目が、鈍い赤色に染まっている。 ひび割れた部分がそのまま残る肌は、薄暗い灯りの下、ずいぶんと白く見える。まるで、人形を相手にしているみたいだ。 「そうね、じゃあ、もう少し面白い趣向を用意してあげる」 ふと悪戯を思いついた子供のように、彼女の表情がぱっと華やいだ。 ……だからさ、悪魔の面白い趣向なんて、いやな予感しかしないっつーの。 「いえいえお構いなく。そろそろ彼氏と一緒に帰らせてもらいますから」 「彼氏? もしかして柊センパイのことかしら?」 「ええ、もちろん。他に誰がいるっていうの。彼は私の大切な彼氏よ」 あああああ、自分で言ってて鳥肌立ってきちゃった。 いや間違ってはいない、間違ってはいないんだけど。違和感が半端ないだけで。 「そう。……柊センパイをあきらめてくれるなら、このまま貴方を無事に帰してあげるんだけどな」 「ありえない取引ね」 あー……、埒が明かない。 素直に柊一路を返してくれるはずがことはわかりきってる。実に無駄な駆け引き、だ。 「なら、私から奪ってみせなくちゃね」 ふふ、と彼女は実に楽しそうだ。 いいわねぇ、人生充実してそうで。この場合、人生って言って良いものかすんごく謎だけど。 ――ふん、上等。こっちだって手ぶらで帰るつもりなんてさらさらない。きっちり奪ってやろうじゃないのさ。 私の決意を感じ取ったのか、悪魔は音を立てることなく一歩、後退した。 後ろで手を組んでくるりと一回転。プリーツのスカートがふわりと浮き上がる。 「それじゃあね、お姫様。がんばって王子様を見つけて」 ちょっとまてこのやろうなんて文句を言う間もなく。 見事なまでに彼女の姿は掻き消えた。 張り詰めていた緊張の糸が少しだけ緩む。どっとため息が出た。 いつの間にかきつく握りこんでいた両手をゆっくりと開く。 血に染まった右手、左手には端が皺になってしまった写真。 右の手のひらがジンジンする。少し熱を持ってるみたいだ。 それでなくとも、木の幹に引っ掛けて傷だらけだったからなぁ。 うううう痛い、泣けてくる。泣かないけどさ。 ……うあああ、しかも。女の子にとはいえ、ちゅーされた。 どいつもこいつも乙女の唇をなんだと思っていやがるのか。 柊一路にもぽんぽんされてるから今更な感はたっぷりなんだけど、なんだかすっごく不愉快だ。 そもそも、アレを女の子って呼んでいいものか、激しく疑問ではあるんだけどさ。 生理的に受け付けないというか、ムカムカするって言うか、悔しいって言うか……ああ、ぐっちゃぐちゃだな、私。 ……よし、忘れよう。さっきのはちゅーにカウントしません。うん、忘れた。 いまはそんなことより、柊一路を捜さなくちゃ。 ――『面白い趣向』、か。 正真正銘の悪魔がみせる思い付きなんて、悪い冗談以外のなにものでもないっての。 |
| Back ‖ Next 魔女のルール INDEX |
TOP ‖ NOVEL |
|
Copyright (C) 2013 kuno_san2000 All rights reserved. |