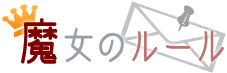 ルール01.魔法が効かないことに、私こと桜侑那が愕然とすること ならびに、柊一路の特異性について考察すること 35 |
おばあちゃんの特訓から逃避……もとい、手先の器用さを鍛えるべく、咲き誇る花をおすそ分けしてもらい花冠を作成するという遠大な目的を果たし終わって、私は黄昏館の庭を鼻歌交じりに歩いていた。 「……うにゃ?」 きょうのはうまくできた、と花冠の仕上がりに浮かれながら生垣の傍を通りがかったところで、ぴたりと足を止めた。微かだが、何かが聞こえた気がしたのだ。 耳を澄ますと、途切れ途切れだが、それはかぼそい鳴き声のようで。 弱弱しさから、すっかり迷子になった子猫の鳴き声だと思い込み、迷わず生垣に突進した。 わずかな隙間から向こう側にずぼっと顔を出したとき、そこに震える子猫がいると確信して。 「こねこさー……ん?」 生垣の向こうに居たのは、こねこさんではなかった。 「ええー……ええーと?」 ずるりと生垣から抜け出す。やや離れた草の上に、膝を抱えて座り込んでいる子供がいた。 自分よりも幾らか年かさに見える子に、四つんばいで、ずりずりとにじり寄る。 いきなり近づいたらご近所の野良猫のようにさっと逃げてしまいそうな気がした。 手が届く距離に近づいても、膝頭に伏せられている顔はよく見えない。 でも襟足あたりで切りそろえられた薄茶色の髪が、日差しにキラキラ光ってとても綺麗だった。 ほー……と、感嘆のため息がこぼれた。 そぅっと慎重に手を伸ばす。指先がさらりとした髪に触れた。 途端、弾かれたようにその子が顔をあげ、ものすごくビックリ、した。 「……誰? いや、どこから……」 同じように驚いているらしいその子から問われて、はっとする。 ……しまった。 どうやら茨の生垣を通り抜けるため、無意識に防御魔法を使っていたらしい。 なんの気配もなく唐突にあわられた子供。それがその時の私だった。 うん、とってもまずい。ど、どうしよう! おばあちゃんにしかられる……っ! 「あ、あのね? わたし、ええっと……」 すっかりうろたえまくっている頭に、うまい言い訳はまるで浮かんでこない。 苦し紛れに生垣を指し示すが、ますます不審そうに眉をしかめられる始末だ。 それも当然で、茨で覆われた棘だらけの囲いから無傷で出てこられるはずはなく、私は服にかぎ裂きのひとつすらない。 引きつった笑みのまま固まっていると、しばらく考え込んでいたその子は、ちらりと少し先を見遣って「ああ」とひとつうなずいた。 「あそこから入ったの?」 「へ?」 示された場所をみると、そこにはちょうど私ひとりくらいなら通り抜けられそうな生垣の切れ目があった。 うおおぉ、ラッキーっ! ここぞとばかりにぶんぶん肯く。あんまり強く頭を振りすぎて、くらくらした。 「ふうん、なんだ」 詰まらなそうにそっぽを向いてしまったその子が、なんだかがっかりしているように思えた。 ものすごいトリックとかあったほうがよかったのかなぁ……。 うーん、あ、もしかしてファンタジーっぽいほうが? 「……ええっと、もしかしてまほうをつかって、とかのほうがよかった?」 「はあ?」 私に向けられた暗い瞳には、嫌悪、軽蔑、そんなものが混じっていた。 ……そ、そこまで? うう、ちょっとこわいこなのかな? 「……ええと、わたしがまじょとかのほうが、よかったのかなぁ……なんて」 ぼそぼそ言ってみたら、不機嫌そう眉をしかめられ、更には背中を向けられてしまった。 「魔女なんて、だいっ嫌いだ」 忌々しげに吐き捨てられた一言に、ぎゅっと胸が苦しくなる。 まるで自分のすべてを拒絶されたようで悲しかった。 「きらい……? なん、で?」 「関係ないだろ」 俯いたままこちらを見もせずに投げつけられる言葉が、とげのように突き刺さる。 「かんけい、ある。だって――まじょはやさしいよ! やさしくて、かっこよくて、すごいまほうだってつかえて! その……こわいこともあるけど、こわいのはちょっとだけだもんっ」 「――アンタ、頭悪いだろ。……あっちいけよ、いまは魔女の話なんて、聞きたくない。それに本物の魔法が使える魔女なんて、いるわけない」 馬鹿にしたように吐き捨てられ、かっと頭に血が上った。 「そんなこと、ない!」 そんなことないんだから! 憤りにまかせ立ち上がる。天に向けて両手を高く掲げて見せる。 思いっきり息を吸い込んで、頭の中から余計なものをはじき出す。 そうして、ぐっと背中を反らせて澄み渡る空を見上げ――。 「ア……うにゃっ」 あまりにもそっくり返りすぎて、呪文の最初を口にしたところで見事に後ろへすっころんだ。ころりん、とそれは見事に。 認めたくはないが、幼少期の私は、なんというか……ちょっと残念というか、いま一歩というか……うん、そんなお子様だった。 「……あううう、いた、いたい……」 ひっくり返された亀のようにもがいたあげく唸りながら頭を押さえてちょっと身を起こすと、呆気にとられていると思わしき視線とかち合った。 ああああそういえば、おばあちゃんにも、おまえはもうすこしおちつきがほしいねぇっていわれた。しかもきのう。どうしてそれをわすれちゃってたんだろう。 この日は、ちょっと力を入れすぎちゃって鍋が爆発して、それをどうにかしようと更に呪文を使ったら火柱がたっちゃって。 すぐにおばあちゃんが消してくれたけど、あれはちょっとした噴火みたいだった。 そのままお昼ご飯も食べずに逃げ出してきて。 ……おひる、おばあちゃんのクランベリージャムサンドだったのに……。 甘酸っぱいジャムの味を思い浮かべたところで、ぐーっと盛大にお腹が鳴った。 「あ」 しん、と気詰まりな空気がただよう。 「……ふっ」 たまりかねたように吹き出したと思しき声。そのあとに続く、豪快なあははという大笑いに、慌ててがばっと起き上がり、なぜか正座してしまった。 笑い声の主は、さっきまでの剣はどこへやら、お腹を押さえ、頬を赤くして、目尻に涙まで浮かべている。よほどツボに入ったらしい。 「……お、面白……お、おなか……鳴るし、転がるし……っ」 「だ、だって、おひるたべてないんだもん……っ、ころがっちゃったのは……その……もう! がんばってるのにっ」 うううう、と唸ると、更に笑われてしまった。 でも不思議と嫌な気分にならなかったのは、たぶん馬鹿にしているような気配がなかったからだと思う。 本当に楽しそうで、うれしそうで。 最後にはなんだか全部どうでもよくなって、結局、私も笑い出してしまって。けど、ふと気づいた。 ……め、あかい。 その瞼は、いま赤く腫れたとはとても思えなかった。そして、私はさっき聞こえた声の正体に気づいた。 とても不思議だった。いままで知っている同い年くらいの子は、すごく一生懸命に泣く。それこそ全身全霊をかけて、見て、気づいて、と、いっぱいに泣く。 けれど、この子の泣き方はずっと静かで、でも、ずっと悲しかった。 おばあちゃんは、悲しかったらいっぱい泣いていいって、言ってた。子供の頃にうんと笑って泣いて、そうしたら強い人になれるのよって。 「あのね!」 「え?」 まだ笑っているその子の肩をがしっとつかんだ。自分でもわからない不思議な気持ちに突き動かされる。 「わたし、ゆうな。あなたは? おなまえ、なんていうの?」 勢い込んでたずねた私の形相は、ちょっと鬼気迫っていた。 「……ちろ……」 気圧されたように、その子が小さく呟く。 「チロちゃん?」 「え? ちが……」 「ん? なぁに?」 くりっと首を傾げる。もう一度、チロちゃんがふっと吹き出した。 ん? なにかおかしなことが? 「――いい」 肩を震わせて、でもチロちゃんは笑い声をこらえようとしている。 さっきみたいに思いっきり笑って良いのに。 でもとにかく、お互いに名前を知るのは友達の第一歩。 あんな泣き方、いやだ。だってすごく悲しくて寂しい。だから、絶対にこの子と友達になる。 幼い決意は、単純で実直。それだけに純粋で、迷いがなかった。 チロちゃんが座る地面には、古木から散り落ちた真っ白な花びらが幾枚も折り重なっている。柔らかそうな薄茶色の髪は風に揺れて、やっぱりとても綺麗だ。 「チロちゃんはおひめさまみたいだねぇ。そうだ、これ、あげる」 午前中いっぱいを使ってようやく作り上げた、真っ白な花冠を得意げに差し出す。 大きな目を見開いて私を見上げるチロちゃんは、黄昏館をくるむうららかな日差しに照らされて、まさにどこをどう切り取ってもお姫様だった。 花冠を差し出したまま、つい、うっとり見とれてしまった。 ……ううーん、やっぱりチロちゃん……にてる、かも。 何度も何度も、それこそ厚手の紙が擦り切れるくらい見返した絵本の主人公――深夜十二時に魔法が解けてしまった心優しい女の子。 「……シンデレラにそっくり」 「――っ」 チロちゃんが、なぜか驚愕したように顔を引きつらせる。 あれ? どうして? 女の子なら一度はシンデレラには憧れるかもねえって、確かにおばあちゃんは言っていた。 だから私にとって、それは間違いなく褒め言葉だったのだ。 「あのね、わたしのもってるえほんの」 「似てない……っ」 もしかしてなにか違う話と間違われているのかも、とシンデレラの内容を説明しようとしたところで、きつく否定され、身がすくんだ。 「ごめんなさい」 しょんぼり謝ると、チロちゃんははっとしたように片手で口元を覆って、ふいっと顔をそむけた。 「……こっちこそ、ごめん」 「ううん、いやなら、もうぜったいにいわない」 ぶんぶんと首を横に振る。ほっと息をついたチロちゃんが、躊躇いがちにこちらへ手を差し伸べた。 「それ、もらっていい?」 「あ、うん、どうぞ!」 受け取られた花冠は、光を弾くさらさらとした茶色の髪に、とてもよく似合っていた。 |
| Back ‖ Next 魔女のルール INDEX |
TOP ‖ NOVEL |
|
Copyright (C) 2014 kuno_san2000 All rights reserved. |