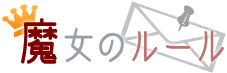 ルール01.魔法が効かないことに、私こと桜侑那が愕然とすること ならびに、柊一路の特異性について考察すること 36 |
真っ青な青空、それにきらきら陽気。これぞまさしく絶好のピクニック日和。 「きょうは、ランチをもってきたのだー」 ここ最近のお気に入り、とあるメーカーからマスコットキャラとして売り出し中の料理上手なテディベア、くまきっちんの口調を真似て、薄紙に包まれたクランベリーサンドをバスケットからつかみ出し、チロちゃんに差し出した。 「はい、どうぞー」 「ええと……ありがとう」 「どーいたしましてー」 自分の分も取り出して、薄紙を半分まで向いた後、ぱくりとかぶりつく。 黄昏館で初めてチロちゃんと会ってから、すでに何度か、こうして一緒に時間を過ごしていた。 けど、きちんと約束があるわけじゃない。 最初の日、別れ際に明日も会えるか尋ねたら、困ったように眉根を寄せて、わからない、と言われた。でも諦め切れなくて、毎日ここにくるから、と、遠くなる背中に声をかけた。 二日後。チロちゃんがもう一度来てくれた時には、本当にうれしくてつい奇声を上げてしまった。それをまた楽しそうに笑われてしまったけど、全然かまわなかった。 「……美味しい」 白パンを一口食べたチロちゃんが、思わずというように呟いた。 どうやらチロちゃんは甘いものがあまりお好みではない様子で、その一口にいくまでの迷いをみていた私は、ふふふとほくそ笑んだ。 おばあちゃん特製クランベリーサンドは、文句なく絶品だ。 甘すぎずすっぱすぎずという絶妙な均衡を保ったジャムに、自家製のもっちり白パン。 どちらも私の大好物だから、ぜひともチロちゃんに食べてほしくて、今朝、おばあちゃんにねだってバスケットに詰めてもらったのだ。 いつもは、私が先に黄昏館に着き、お昼過ぎにチロちゃんが姿を見せるのだけど、この前の金曜日だけは黄昏館の前庭にしつらえられたベンチで本を読んでいるチロちゃんが笑顔で私を迎えてくれた。 もしかして今日も、とわずかな期待を込めて、お昼前にバスケットを抱え、黄昏館の門をくぐったのだが、それが見事にドンピシャリ。いつもの場所にチロちゃんがいるのを見つけた時には、チロちゃんが軽くひくくらいの勢いで突進してしまった。 大荷物の私に、ちょっとびっくりしたように目を瞠って、でも笑顔で手招きしてくれて。 進められるまま、チロちゃんの隣にうきうきと腰を落ち着けたのが、さっきのこと。 「おばあちゃんのつくるものは、どれもすごくおいしいのだよー」 「ゆうなは、おばあちゃん大好きなんだね」 「うん、すきー。でもたまにすごくこわいー」 「ゆうなが悪いことしたとき?」 「……あう……」 ずばっと言い当てられ、ぐうの音もでない。 最初の頃よりずいぶん柔らかな空気を纏うチロちゃんは、それでもちょっと辛口だ。 「ときにー、チロちゃんよ、ティーはいかがかねー」 「うん、いただきます。で、気になってたんだけど、それどうしたの?」 水筒付属のプラスチック製カップにたっぷり注いだ温かな紅茶を差し出すと、受け取ったチロちゃんがちょっと首を傾げた。 「それ?」 「しゃべりかた」 「んふふふー、わたしはくまきっちんなのだー。おりょうりじょうずで、ちからもち。からだはおっきくとも、きもちはやさしいナイスガイ!」 得意満面でくまきっちんを褒め称える。 ついでにポシェットにつけてあるくまきっちんのマスコットを手にして、どれだけ良いクマなのかを力説したのだけ、ど。 チロちゃんは、ふうん、とつぶやいてなぜかそっぽを向いてしまった。 あれれ? ごきげんななめ? 「ゆうなはそういうのがいいんだ?」 「そういうの?」 どういうの? んん? と、じっと答えを待っていたら、突然くしゃくしゃと頭を撫でられた。 更にばっさばっさと豪快に髪の毛をかきまわされる。目をぱちくりしてびっくりしているうちに、これまた唐突におさまった。 「お昼、ごちそうさま」 「う? ううん? あ、どういたしまして!」 つまり、あたまぐりぐりは、ありがとうってことだったのかな? それにしてはちょっとちからがつよかったきがするけど。 でも、それだけおばあちゃんのサンドイッチが美味しかったってことだよね、と納得して。 そうしたら、うれしくて頬がゆるゆるニヤニヤになった。 「またもってくるね」 「うん……次はくまきっちんじゃなく、ゆうなで持ってきてくれたらもっと嬉しいかな」 くまきっちんじゃなく、わたしで? ……は! もしかしてごきげんななめだったのは、くまきっちんのせい? 「くまきっちん、だめ? いや? うー、そっかぁ、ざんねん」 みどりちゃんもかなちゃんもこわいっていうんだよねぇ、くまきっちんのこと。めつきがハンターっていわれたけど、よくわんかんない……。 友達に恐れられるくまきっちんを敬愛してやまなかった当時の私は、チロちゃんにも受け入れてもらえず、がっくり落ち込んだ。 「くまきっちんみたいなおにいちゃん、ほしいんだけどなぁ」 「……お兄ちゃん?」 「うん、そばにいたらあったかそうだし、いいよね」 ぐっとこぶしを握りしめ力説したら、チロちゃんが吹き出した。 おおおお? なぜ? わたしおかしいなことひとつもいってない。 「……ほんっと、ゆうなって……普通、お兄ちゃんを防寒具にはしないでしょ」 ぼうかんぐってなんだっけ? でも笑いすぎて涙をにじませているチロちゃんに尋ねるのはなんだか悔しい。 「そ、それだけじゃないよ? あのふかふかのからだにさわらせてもらいたい!」 「熊の毛って意外に固いらしいから、あまり触り心地はよくないかもね」 さらりと告げられた意外な事実に目を瞠る。 「え? かたいの? そうなんだ……」 あのふかふかに顔を埋めたら気持ちよさそうだなーとかちょっと夢見ていただけに、結構な衝撃だった。しょんぼり肩を落としていると、チロちゃんが困ったように笑ってぽんぽんと頭を撫でてくれた。 「ごめん、意地悪だった。あのね、ゆうな、ちょっと後ろを向いてくれる?」 「んん? うん?」 意地悪なことなんてされたかな? と不可解に思いながらも、いわれるまま、くるりと後ろを向く。 首まわりを覆っていた髪が、チロちゃんの手により右肩に寄せられる。 くすぐったくて首をすくめた間に、顔の横をチロちゃんの両腕が掠めた。 私の目の前で合わさった手が開かれる。しゃらりと音をさせ、細い銀の鎖が手品のようにあらわれた。 そのままするりと私の首にまわされ、止め具が掛けられる。鎖に吊るされた小さな燻銀の小鳥が、胸元でかわいらしくゆれた。 「わあ、かわいー」 「父さんからのお土産。あげる」 「えっ、もらえない。だって、おとうさんからチロちゃんへのおみやげなのに」 「ゆうなにあげたくて、私が父さんに買ってきてくれるようお願いしたものだから。ちゃんとあげるための物って父さんにも伝えてある」 ええ? わたしのため? 驚いて振り向くと、銀の鎖がしゃりんときれいな音を立てた。 「うん、よく似合ってる」 うう、そんな風に嬉しそうな顔されたら、もらえないなんて、言えない。 それに、わたしのために、ていうことが――とってもうれしい。 「ありがとう……っ、たいせつにする」 精一杯の感謝を込めた御礼を、チロちゃんは少し頬を染め、はにかみながら受けてくれた。 ――あ、まただ、むねのあたりがきゅうきゅうする。 なんだろう? いままでこんなことなかったけどなぁ。 戸惑いながら、ぎゅっと小鳥を握りしめる。お腹のあたりがほわりと温かくなった。 ――あれ? 「……これ、おまもりなんだね」 しかも、本当にまじないがかかってる。ちゃんと人の手で一つ一つ、正しい手順で作られてるに違いなかった。 手のひらをそっと開いて、銀色の小鳥を見下ろす。 「うん、そう。幸運を連れてくる小鳥って言われてる」 答えてくれながら、チロちゃんは少し不思議そうにこちらを見ていた。 「チロちゃんのパパは、いいひとだね」 まじないは、人の手から人の手に渡っていく間に変質することがあるって、前におばあちゃんが言ってた。 チロちゃんのお父さんからチロちゃんに渡された小鳥には、まじないの効き目を増やす力しか働いていない。 そこに、捻じ曲げられた歪さはなかった。 「……ゆうなは時々、すごく大人びた顔になる」 「え?」 小鳥から目をあげると、すっと立ち上がったチロちゃんの背中が目の前にあった。 「私の父さんは、いい人かと言われればたぶん、いい人。でも自分の気持ちに正直すぎるから、一つ所にとどまることができない。誰かの傍にずっといることができない。――誰にも、捕まえられないの」 ゆっくりとチロちゃんが歩き出す。その細い背中が遠ざかっていく。なぜか、たまらなく不安だった。 このままどこかに行ってしまうような気がして。帰ってこないような気がして。 「わたしは……わたしは、チロちゃんといるよっ」 「……ゆうな」 足を止めて、振り向いてくれた。それだけでほっと息がこぼれる。 「チロちゃんがすきだもの……っ」 あれ? わたし、なにいって……。 咄嗟に飛び出た言葉にびっくりして、慌てて口を押える。 そろりと目線を上げると、驚いたように目を見開いたチロちゃんの頬が、きれいな桜色に染まっていた。 「……私も、ゆうなが好き」 躊躇いがちに呟かれた小さな返答に、いつもよりひどく胸がきゅうっとした。 こみ上げてくる熱に突き動かされるままベンチから立ち上がり、両腕を広げてチロちゃんにがばっと抱きつく。 「え……っ、わ、ちょ……っ、ゆう」 突進した勢いはチロちゃんに全部かぶさり、結果、芝生の上にばたりと二人で倒れこんだ。 私を庇おうとしたチロちゃんは、草まみれだ。 「わわ、ご、ごめ」 慌てて飛びのこうとしたら、そのままぎゅっと両手で抱き込まれ、柔らかな草の上を何度か二人で転がった。 うにゃあああ、と悲鳴を上げて目を回す草まみれの私を見下ろして、「お返し」と笑ったチロちゃんは、確かに意地悪だった。 |
| Back ‖ Next 魔女のルール INDEX |
TOP ‖ NOVEL |
|
Copyright (C) 2014 kuno_san2000 All rights reserved. |