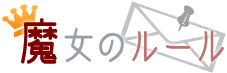 ルール01.魔法が効かないことに、私こと桜侑那が愕然とすること ならびに、柊一路の特異性について考察すること 37 |
薄暗闇の中、ゆらゆらと影をたてながら揺れる真っ赤な炎は頬に熱く。 暖炉にくべられた薪が爆ぜる音は耳に心地よく。 木製の床に敷かれた丸いラグの上で膝を抱え、小さな私が、ぼんやりと暖炉の中を見つめている。 貴重な書物や呪具が納められた館の中は、人よりもそれらに快適な温度と湿度を保たれていた。 だから、そろそろ温かくなろうという季節でも、人の居住区には熱源が必要だった。 でも、私はこの空気がとても好きで――そう、ためらいなく懐かしいと感じられるほどに、この空間を、匂いを、感触を覚えている。知っている。 「おばあちゃん」 幼い私が声をかけると、編み物をしていたおばあちゃんは手を止めて、優しげな笑みを返してくれた。 着られるのを楽しみにしている薄いさくら色のカーディガンは、そろそろ仕上がりが近い。 「あのね、わたし、おともだちができたの」 「あらまあ、よかったこと」 「すごく綺麗な子なの」 「女の子かい?」 「うん」 「そう、仲良くおしね」 嬉々として話す私の頭を温かな手が撫でる。 「でもユウナ、気をつけなればいけないよ」 「気をつける?」 「おや、もう忘れてしまったのかい? この先、お前が心を許しても、その子と口づけを交わしてはいけないってことだ」 「え、でもチロちゃんは女の子だよ?」 ふふっとおばあちゃんが謎めいた笑みを浮かべる。 おばあちゃんの膝を占拠している黒猫のブロッシュが、ちらりと私を見てどこか呆れたようにあくびをひとつ。 ああ、黒猫。そう……そう、か。人を小馬鹿にしてくれたあの黒猫は、ブロッシュは、おばあちゃんの使い魔、だ。 きれいさっぱり忘れてしまっていた。その理由も、いまの私ならわかる。 ブロッシュが……選定者に指名されてしまったから。 いまにして思えば、この時、おばあちゃんは既に知っていたのだ、チロちゃんの秘密を。 そのうえで私に自由を与えたのだと思う。そう、選択する、自由を。 魔女の力を扱うための訓練をはじめた時、おばあちゃんに言われた。 ――まず教えておくことがある、と。 「魔女にはね、この世でたったひとり魔法の聞かない相手がいるんだ」 信じられなかった。魔女、というからには、つまりおばあちゃんの魔法が効かないナニモノかがいるということだ。 納得できない。私にとっておばあちゃんは絶対無敵の人なのに。 「魔法が、効かないの?」 「そう。あのね侑那、女性になる前の口付けには特別な意味があるんだよ」 ぴしりと背筋が伸びる緊張感に、こくりと咽喉が鳴る。じっと続きを待っていると、おばあちゃんの口元がふと和らいだ。 「女の子になる前に涙を与えて口付けを交わすとね」 取って置きの秘密を打ち明けるように、秘めやかに密やかに静かな声が染みてくる。 「うん」 「その人が生涯の主になってしまうのさ」 よく、意味がわからなかった。そもそもにして、あるじ、という言葉の意味からしてこのときの私には危うかった。 けど、どうやらその主とやらが出来るのは、魔女にとってあまりよいことではない、というのはおばあちゃんの口調から察した。 「おんなのこになるまえって?」 考えあぐねた末、とりあえず最初に浮かんだ疑問から解決することにした。 「初潮を迎える前ってことだよ。まだ、侑那にはわからないかしらねぇ」 首をかしげてきょとんとする私は、おばあちゃんの懸念どおり、さっぱり理解できていなかった。 ――「しょちょう」とやらのまえに、なきながら「くちづけ」とやらをすると、そのひとが「あるじ」とやらになる。 でっかいはてなマークに占拠された顔をしかめて、うん、ううーん? と呻っていると、まあいいよ、そのうちわかるさ、と頭を撫でられた。 「けれど、忘れてはいけないよ? 大事なことだから。いいかい? 涙が効力を持つのは最初の一人だけなんだ」 髪を揺らしながらうんうんと頷く。 「だからね、私のかわいい侑那、お気をつけ――男の子にその唇を許してはいけないよ」 「くちびる? どうして?」 「あらま、そうか、口付けの意味がわかってないね?」 「あう……」 「お互いの唇を合わせることを口付けっていうんだよ」 「ふうん? 男の子だと駄目なの? 女の子はいいの?」 「異性でなければ、涙の効力はないからね」 つまり、「なきながら」「おとこのこ」と「くちびるをあわせる」と、そのひとが「あるじ」とやらになる。 そして、「あるじ」には、「まほうがきかない」。 小さいなりに、わからないなりに、わかったつもりになっていた。 けど、やっぱりわかってはいなかったのだ。魔法が効かないって事が、どういう意味をもつのかってこと。 *** 青空の下、おばあちゃんの作ってくれた薄手のカーディガンを着て、くるりと一回転する。 元の位置に戻って両手を広げると、チロちゃんがふんわりと笑ってた。 「かわいいね」 「おばあちゃんがつくってくれたの。このさくらいろはわたしがえらんだんだよ」 えへへと笑みを返すと、よく似合ってると更にお褒めの言葉を頂戴し、私は有頂天だった。 昨日の夕方、もらったばかりのカーディガンは、さらりと軽く、なんだか体もふわふわするようで。 当社比二倍くらいの勢いでチロちゃんを連れまわして遊び倒した結果、夕暮れが迫る頃にはベンチで軽く船を漕いでいた。 「ゆうな、もう時間だよ、帰ろう?」 軽く肩を揺すられ、苦笑交じりの声を夢うつつに聞き、こくりと頷く。瞼を擦ってよろよろ立ち上がると、右手をそっとつかまれた。 「んん?」 「大丈夫? 送っていこうか?」 気遣いの篭った申し出に、けれど、うん、と頷くことはできなかった。 いつでもチロちゃんは決まった時間に帰っていく。はっきり訊いたわけじゃないけど、多分、門限があるのだろうと、なんとなくわかっていた。 「んーん、だいじょうぶ」 ふるふると左右に首をふる。 「本当に?」 見上げてくる黒曜石の瞳にじっと見つめられ、言葉に詰まった。 夕日に照らされた頬が熱い。でも、なぜか陽の当っていない頬も熱い。 握られていた右手をぱっと持ち上げ、斜めがけにしたポシェットにぶら下げていたくまきっちんをわしっと掴んで、高々と掲げた。 「だ、だいじょう! ほら、わたしにはこのくまきっちんが!」 言い終わるよりも早く、チロちゃんの瞳が眇められた。 「……ふうん、そっか」 あ、あれ? ごきげんなな……、はっ、しまった! やっぱりチロちゃんはくまきっちんがいやなのか! 一緒にお昼を食べた次の日。 くまきっちんマスコットを家においてきたら、チロちゃんから「くまきっちん、好きなんでしょう? はずしちゃったの?」と不思議そうに言われた。 だから、私の口真似だけが嫌だったのかな? と、その次の日にはくまきっちんマスコット復活! となったんだけ、ど。 そっかぁ、すきじゃない、のかぁ。あうう、くまきっちんファン、なかなかいないなぁ……。 「あ、あのね……」 もごもご口ごもっている間に、チロちゃんがさっと立ち上がった。 私のほうを向いて少し身をかがめると、額が触れ合うくらいに顔が近づく。 「にゃっ」 焦点の合わない近さに、素っ頓狂な叫びをあげたまま、硬直した。 「お、きてる、ちゃんとおきてるよぅ」 必死に言い募ったわたしの鼻先に、チロちゃんの忍び笑い。吐息のくすぐったさにむずがると、すっと温かみが遠のいた。 「うん、目は覚めたみたいね。ちゃんとまっすぐ帰ること、いい?」 「いつもとおってるみちだもん。だいじょうぶだよ」 ぷっと頬を膨らませ、チロちゃんに背中を向ける。後ろからくしゃっと頭を撫でられ、たちまちほっぺは萎んだ。 タタっと少しだけ走って、くりっと後ろを振り向く。ばいばいっと手を振ったけど、逆光でチロちゃんの顔はよく見えなかった。 「気をつけて、知らない人について行っちゃ駄目だよ」 はーい、と返事はしたけど、正直、このときの私はまったく自分を心配してなかった。 ――たとえなにがあっても、魔法を使えばどうにかなると思っていたから。 |
| Back ‖ Next 魔女のルール INDEX |
TOP ‖ NOVEL |
|
Copyright (C) 2014 kuno_san2000 All rights reserved. |