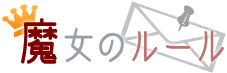 ルール01.魔法が効かないことに、私こと桜侑那が愕然とすること ならびに、柊一路の特異性について考察すること 39 |
そうして過ぎていった日々は。 楽しかった、幸せだった。ずっとこのまま過ごせるのだと、ただ単純に思い込んでいた。 けれど現実は追いついてくる。自宅に帰る日が、刻一刻と迫っていた。 考えないように、考えないように。意識の底に押し込めても時間は止まらない。 そうして、自宅に帰るまであと二日を残すばかりになった金曜日。 この日、私たちに起こった出来事が――すべての、元凶。 「元気がないね」 ベンチに座ってぼんやり足元を眺める私を、心配顔のチロちゃんが覗き込んでいた。 「え、そんなことない、よ」 「ごまかさないで。何かあった?」 慌てて手を振って笑顔を作ったけれど、チロちゃんにはばっちり見透かされてしまった。 無理やり作った笑みがくしゃりと崩れ、再び俯いて、ぎゅっとスカートを握り締める。 「……あとすこしで、おうちにかえらないといけないの。わたし、いま、おばあちゃんのおうちにとめてもらってるだけ、だから……」 チロちゃんがどこに住んでいるのか、知らない。黄昏館という接点がなくなってしまえば、今度はいつ会えるのかわからない。 「――ゆうなの家、どこにあるのか訊いてもいい?」 ぽんぽんと頭を撫でられ、温かな感触にずずっと洟をすする。 覚えたばかりの住所をたどたどしく伝えると、チロちゃんがふっと息を吐いた。 「ここからそんなに遠くないね」 「え」 とおくない? そうなの? でも、家から駅までそれなりに歩いたし、電車にも乗ったし、着いた駅からもまた歩いている。 そう言うと、ここは駅と駅の中間くらいで、駅から来ると、かえって遠回りになるんだよ、と教えてくれた。 「おかあさん、どうしてあるいてこなかったのかなぁ?」 「うーん、多分だけど、歩いてくる道を覚えちゃうと、ゆうなが一人で遊びに来ちゃうと思ったんじゃない?」 「……うぐ」 納得できすぎて、反論は一切出来なかった。多分というより間違いなくそれが理由だ。心当たりがありすぎる。 でも、そんなにとおくないのかぁ……。よし、だったら。 「ひとりで歩いてくるのは駄目だからね?」 先手を打って釘を刺されてしまった。 ええええーっと叫ぶと、チロちゃんが、やっぱり、と呟いてため息を落とした。 「だって、だって」 「駄目なものは駄目です」 きっぱりとした拒絶に、がっくりと肩を落とす。希望がみえた後だっただけに、しょんぼり感も倍増だった。 「……私が、迎えにいくから」 「え?」 「だめ? 土曜日か日曜日、もちろんゆうながよければ、だけど」 ぶんぶんと頭を縦にふる。そんなのいいに決まってる。 ここで少し、欲がでた。 「あ、あのね……っ、うちにあそびにきてっていうのは、だめ、かな?」 微かな困惑と逡巡が、チロちゃんの瞳に浮かんだ。 やっぱりだめかな、だめだよね……と思いつつも、少しの希望を捨て切れなくて。息をつめてぎゅっと手を握り締めた。 「……ゆうなのご家族が、ご迷惑でなければ……」 「ごめいわくでなければ?」 意気込む私。ためらうチロちゃん。 じっと期待を込めて見上げる視線に根負けしたのであろうチロちゃんは、微苦笑して「お邪魔してもいい?」と小さく呟いた。 「クッキーとジャム、いっぱいあるからね!」 にへっと全開の笑顔を向けると、チロちゃんがビックリしたように目を瞠った。 父さんも母さんも、きっと迷惑だなんていわない。ばっちり確信があった。 母さんは、チロちゃんのはにかみ笑顔を見れば陥落間違いなしだし、母さんが良しといったことに父さんは否やを言わない。 ちっちゃい子供って、意外に親の力関係を把握してるんだよね、うん。 クッキー作りとおばあちゃんからジャムをゲットする算段をめぐらす。 そうだ、チロちゃんはココアすき? と、うきうき横をみて、ぴたりと動きが止まった。 「……チロちゃん?」 すっかり立場が逆転していた。 浮上しすぎて浮かれきった私と、うつむいてなにかをじっと考えている様子のチロちゃん。 ええええ? わたしなにかやらかした!? はっ、もしかしてココアか!? ココアがだめだったのか!? あ、それとも、もしかしてクッキー? クッキーかな? 「――ゆうな、話がある」 「う、うん?」 「あのね、私――いや、ぼ」 言いかけたちろちゃんの言葉が途切れた。 ぱっと後ろを振り向いたその背中がひどく緊張しているように見えて、声をかけることができない。 「……ゆうな、ごめん、少しあっちに行って隠れてて。なにがあっても出てきちゃダメ」 「え? どうして」 「いいから。かくれんぼだと思って、ね?」 「う、ん?」 有無を言わせぬ雰囲気に、不承不承たちあがり、後ろを振り返りながら少し離れた茂みの中に隠れた。 枝と葉っぱの間に出来た隙間から、身をかがめてそっとチロちゃんの方向をうかがう。 レンガ敷きの小道から、かつかつと甲高い靴音。 なにかを考える間もなく、細い足から伸びた赤いハイヒールがすぐにあらわれた。 驚きながら視線をあげると、黒いストッキングに包まれた足のうえには、ぴっちりした黒のロングスカート。 やっぱり細身の上半身はレースがゆれる白いブラウスに覆われ、やや茶色味を帯びた長い髪がゆるく背中に流されている。 化粧の施された細面の中では細く整えられた眉毛が顰められ、黒い瞳は暗い炎を宿していた。 怖い、と感じたその瞬間。 ぱんっと乾いた破裂音が響き渡った。 「私がお教室に行く日はずいぶん楽しそうだと思ったら、あなたはこんなところでなにをしているの!」 ヒステリックな叫び声。反射的にびくっと身がすくむ。 え、なに? なにがあったの……? 目の前で起きた出来事が上手く理解できない。瞬きすら出来ずに見つめる先では、チロちゃんが左頬を押さえている。 ……チロちゃんが、ぶたれたんだ。 どうして? なんで? このひと、だれ? 半分以上、恐慌状態に陥っていた。 けれど、たたかれた張本人のチロちゃんは、俯いたままで。その目には、まったく感情が浮かんでいない。 どうして? どうして? どうして? ――コンナトコロデナニヲシテイルノ。 耳の中で先ほどの言葉がよみがえった。 あの人が怒っているのは、チロちゃんがここにいた所為。だったら叱られるべきはチロちゃんだけじゃない。 一緒にいた私も、だ。 茂みから飛び出そうとした、その時。 うつむいたチロちゃんの目が私をみた。強い光の閃くその瞳が、でてくるな、と告げていた。 ――なにがあっても出てきちゃダメ。 ああ、そうだ。チロちゃんはでてくるな、と。でも。だって。どうしたらいいのかわからない。 「この間も夜遅くに出歩いて……っ」 「――ごめんなさい」 淡々とした謝罪。それがさらに女の人の感情を逆なでたのか、再び腕が振り上げられた。ひゅっと風を切る音。 がつっとチロちゃんの頭に拳が当たった。 「……ひっ」 喉の奥に悲鳴が絡みつく。 あんな、あんなのひどい。だってチロちゃん、なにもしてないのに。あやまってるのに。 子供の私でもわかった。あれは理不尽な暴力なのだ、と。 チロちゃんが腕におっていた痣がどうやってつけられたものなのかも、多分、この時に漠然とわかってしまった。 「いつもいつもふらふらと遊び歩いて……っ、そんなところまであの人にそっくり……っ」 チロちゃんの細い体が、よろめいて、草地の上に倒れ込む。 その姿は淡々とすべてを受け止めていて……違う、あきらめてる。 「チロちゃん……っ」 もうだめだった。けど、飛びだそうしたその時、まるで引き止めるように、カーディガンが木立にひっかかった。 焦りに任せ思いっきり引っ張る。ずるっと裾が解け、大きくほつれてしまったけれど、構ってなんていられなかった。 「やめてっ」 両手を広げ、女の人とチロちゃんの間に立ちふさがる。背後で、チロちゃんが息を飲む気配。 間違いなく、チロちゃんは私に出てきてほしくはなかったはずだ。でも完全に血の上りきった頭の中は、チロちゃんを助けなきゃ、ただそれだけ、で。 「なに……あなた」 女の人が困惑気味に目をさまよわせる。 見知らぬ幼女が飛び出してきたのだから戸惑って当然なのだが、このときの私には、彼女の様子に後ろめたさしか見えなかった。 この人は、わるいことをしているってわかっている。それなのに。 「どうしてチロちゃんをぶつの」 心の中がどろりとしたものに満ちた。まるで黒い闇に飲まれたように気持ちが抑えられない。 感じたことのない、暗く重い真っ黒な澱に飲み込まれる。 「……っ、なんなのよ! ああ、そう、あなたね? あなたが唆したのね!?」 まっかな紅で彩られた、わけのわからないことをわめきたてる口。神経質そうに振り回される指先には、ラメで輝く赤のマニキュア。 物語に出てくる悪い魔女のようだな、と思った。 ――ああ、そっか。まじょだ。チロちゃんがきらいだといったまじょは――このひとだ。 なぁんだ、だったらこのひとをチロちゃんのそばからけしてしまえばいい。だって、わたしにはできるんだもの。 足元から渦巻き状の風が立ち上る。そう、これをもとにすれば、とってもかんたん。 鋭く、早く。切り裂く刃を――。 足元で風が逆巻く。ほつれたカーディガンの裾がはためく。その時、私が知らずに作り上げようとしてたのは、かまいたちだった。 体の前に持ち上げた右手が風を纏め上げると、小さな白い渦ができていた。木の葉を巻き上げるそれに、意思を込める。 「きえちゃえばいい」 「ゆうな……っ、だめ」 後ろからまわされた腕に引き止められた。集めた風が霧散する。 更にぎゅっと抱きしめられた反動で、足元がよろける。けど、懸命な腕はどこか頼りなげでますます苛立ちが募った。 「だって、この人が……っ」 チロちゃんをくるしめてるんじゃないか! 胸に湧き上がってくるのは、燃え上がる火のような灼熱だ。 いままで一度も感じたことのないこれがなんなのかは、わからない。 でも、ほんの欠片だけ残る冷静な自分が、怯えている。この先に踏み出してはダメだって、踏みとどまらせようとしている。 それでも奔流のようにうねる激情は止められなかった。 「はなしてっ」 「いやだっ」 「どうして? なんで、こんなひとをかばうの……っ」 いらいらと首をめぐらせる。途端、強い力と意志こもった綺麗なまなざしに、囚われた。 「違う! ゆうなに人を傷つけさせたくないからだっ」 叫ばれた言葉の真摯さに、全身の力が抜けた。 力の残滓のように舞い上がっていた髪がふわりと落ち、ちろちゃんの腕に降りかかる。 「チロちゃ……」 「ごめん、こんなことに巻き込んで、ごめん」 背後から私の肩に顔をうずめるチロちゃんは、かすかにふるえていた。 チロちゃんが謝ることなんて、なにひとつないのに。 ぎゅっと唇をかみしめる。どうすることもできないもどかしさが腹立たしかった。 「……ば、ばけ、も」 震える声に、しまった、と思うが、時すでに遅し、だ。 私の前方でがたがと震える彼女は、心底おびえた目で私を見ている。 ざっと血の気が引いた。私が青ざめる番だった。 |
| Back ‖ Next 魔女のルール INDEX |
TOP ‖ NOVEL |
|
Copyright (C) 2014 kuno_san2000 All rights reserved. |