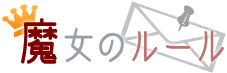 ルール01.魔法が効かないことに、私こと桜侑那が愕然とすること ならびに、柊一路の特異性について考察すること 40 |
「あ、あの……」 「なんなの? なんなのよ!? どうして、どうして、どうして、わたしばっかりこんな目に合うの……っ」 見開かれた双眸は、焦点が定まっていない。小さなカバンから引き出されたものに悲鳴を飲み込んだ。 銀色に輝くナイフが細い指に握られている。穏やかな日差しの中、それはひどく場違いで、それだけにひどく狂気をはらんでいた。 あからさまに向けられる殺意に身がすくむ。 逃げなきゃいけない、と思えば思うほど、一歩も動けなかった。恐怖に息が上がる。 低く構えられたナイフが迫ってくる。 「ゆうな……っ」 立ちすくむ私の前に、細い背中が立ちふさがった。 すべての音が、消えて。ふと気づいたときには、狂気を纏っていた女の人がナイフを構えたまま、よろよろと後ずさっていた。 「あ、あ、あああ」 驚愕を全身に張り付かせ、壊れてしまったように上擦った声をあげながら震えている。 ――どうなったの? ぼんやりしたまま、頬を流れ落ちた一滴のしずくを手のひらでぬぐう。見下ろした自分の手にぎょっとした。 あか、い。 「チロちゃん……っ」 すっくと立ちはだからる背中の前に回り込む。視界が真っ赤に染まった。 いつも涼しげで綺麗な黒色の双眸。その片側――右目を、チロちゃん自身の手が押さえつけている。手の甲は流れ出た血にまみれていた。 「……や……あああっ!」 悲鳴をあげているのが自分だってことにすら気が付かなかった。身を二つに折るようにして座り込んだチロちゃんに手を伸ばし、顔に触れる。治さなきゃ、とそれだけを一心に願った。 けれど、傷は塞がらなかった。血は止まらなかった。どれだけ必死に呪文を唱えても、なにひとつ起こりはしなかった。なぜ、という疑問さえ浮かばないほど混乱し、あっという間に視界が滲んだ。 「なんで、とまらないの……おねがいだから、とまって。いやだよ、こんなの、だめ……」 「ゆうな、大丈夫だから。落ち着いて……」 しゃくりあげる私の頬をチロちゃんがそっと撫でる。 涙で歪むその先には、真っ青な顔、震える唇。痛くないがはずがない。気が遠のくほどの痛みに違いないのに。 「わたしはだいじょうぶなのに……チロちゃんがきずつくこと、ない、のに」 「ごめんね、でもゆうなに傷ついてほしく、なかった」 「チロちゃん……」 「君がくれたものを、少しでも、返したかった」 「お、おはなくらいしか、あげてない」 「それもだけど、それ以外も、いっぱいもらった、から」 ぼろぼろ零れる滴が、チロちゃんの顔を濡らしていく。涙の流れ落ちたところだけ、鮮血が薄れていく。 「もう、ずっと別の誰かに、なりたかった。……でも侑那には、やっぱり……僕を、知ってほしい。ごめんね……お姫様じゃ、なくて」 「え……え?」 「女の子じゃない、よ」 たぶん、笑おうとしたのだと思う。チロちゃんの唇の端が、わずかにひきつれた。 間抜けな私は、この時初めて、これまでチロちゃんが女の子のように振る舞おうとしていたのだと、ようやく気が付いた。 チロちゃんは一度も自分を女の子だなんて言ったことはなかった。勝手に勘違いしていたのは、私だ。 「……そんなの、いい……っ、チロちゃんなら、おんなのこでもおとこのこでも……だいすき……っ」 本心だった。女の子でも男の子でも構わない。驚きはしたけれど、チロちゃんが好きで大切な気持ちに変わりはなかった。 ――ああ、でも。 ただ一つ、愕然とするに十分な事実がそこにはあった。 ――わたしのまほうは、もうチロちゃんにきかない。 涙と共に口づけをあげてしまった。チロちゃんは、私の主になってしまったから。 「……ありがとう、ゆうなが望んでくれるなら、もう、このままの、自分でいい、かな」 途切れ途切れに呟いた後、静かに目を閉じたチロちゃんは、空気に滲んで、溶けてしまいそうなほど儚かった。 細い体に両手を回してぎゅっと抱きつく。薄い桜色のカーディガンが見る見るうちに赤く染まった。 こんなことしか出来ない自分が無力で情けなくて、どうしようもなく涙ばかりがあふれる。 たすけて、たすけて、たすけて、チロちゃんをたすけて。わたしのぜんぶをあげてもいいから……っ! 「おばあちゃん、たすけて……っ」 チロちゃんを両手で抱きしめ、力の限り、叫んだ。 「やれやれ、仕方のない子らだねぇ」 一瞬前までなにもなかったはずの空間から、穏やかな声が降り注ぐ。 まるでもともとそこにあったかのように、次元の切れ目が現れていた。 繊細なダビンチ模様の織り込まれたショールがふわりと翻る。ゆったりとした動きで揺れる黒のフレアスカートに続いて、白髪をきれいにまとめたおばあちゃんがすらしとした姿をみせた。 穏やかな笑みを浮かべると、目元に寄るわずかな皺。けれど凛とした隙のない身のこなし。 心を飛ばしてしまったように佇む女の人に、おばあちゃんがするりと近づいた。とん、と指先で額を押す。 後ろに倒れた体が、地面につく直前に一瞬ふわりと浮き上がり、草地の上にゆっくりと横たわった。 「おば……ちゃ」 しゃくりあげる私を一瞥した後、おばあちゃんの視線はチロちゃんに向けられた。 片膝をついてしゃがみ、チロちゃんの顔に右手を翳す。 「この傷は完全には治らない、魔法といえども万能ではないんだ」 おばあちゃんにならなんとかできる、なんとかしてくれるっていう甘い考えを打ち砕かれ、目の前が真っ暗になった。 「みえるようには、なら、ないの?」 震えの混じる私の問いかけに答えることなく、おばあちゃんが微笑む。 「侑奈、お前の力を少し借りることになるよ」 「いくらでもつかってくれていい!」 おばあちゃんの左手が私の額に触れた。 まず、手足から力が抜け、すっと身体が冷たくなった。 チロちゃんを抱えていた腕がずるりと滑り、まるで自分の体じゃないような感覚に気が遠くなる。 ――どれくらいそうしていたのかは、わからない。 「……なっ、……ゆうなっ!」 呼び声で目を上げたときには、倒れた私をチロちゃんが覗き込んでいた。 白い頬には、まだ少し血がついていたけれど、その双眸はしっかりと開かれている。 ああ、よかった。 ほっとしたと同時に、魔法は万能じゃないという言葉の意味がわかってしまった。 チロちゃんの瞳は、左右でその色が違っていた。 きらきらと輝いていた二粒の黒曜石は、その片側だけチョコレートのような濃茶になっている。 「……っ」 身じろぎした途端、体全体が軋んだ。起き上がろうとがんばったけれど、どうしても力が入らない。 諦めて眼を閉じ、大人しく草地に身を任せてしまう。 「ばかゆうな」 「うう……う? え? ……ち、ろ……ちゃ……?」 重い瞼をどうにか持ち上げると、チロちゃんの上体がふわりと覆いかぶさってきて。しかも、私の肩口に顔を押し付けたチロちゃんから、小さな嗚咽、が。 えええええ? ななななな、なんでないてるの!? 動転してすっかり思考が停止した。それでなくとも体はちっとも言うことをきいてくれないし、途方にくれるしかない。 「この子は大丈夫。少し休めば回復しますよ。さあ、次はあなたの番。お父様のもとへ行かなければ」 ……え? おとうさん? あの、がいこくにいっているっていう? 「……このまま、ここに残ることはできませんか?」 「それは、あなたのためにも、あなたのお母さんのためにも良くはないね。それに侑奈は、まだ分別のついてない子供だ」 突然でてきた自分の名前に気づかない程、私は呆然としていた。 チロちゃんが、おとうさんのところにいっちゃう? じゃあ……もう、あえない、の? 「だから別れなきゃいけないんですか? そんなの……っ」 納得できない、と吐き捨てられた言葉。草地に叩きつけられた拳。顔をあげたチロちゃんは、とても苦しそうにみえた。 ……どうしてだろう。ただ、わらってほしかっただけなのに。 青ざめる頬を手のひらで包んであげたかった。でも腕が持ち上がらない。 「そう、理不尽だ。けど、このまま一緒にいることを選べばこの子は貴方の傀儡になる」 「……くぐつ?」 「あなたの望むことを、望むだけ叶えようとする。それこそ人を殺めることすら躊躇わないだろうよ」 のんびりと剣呑なことをいうおばあちゃんに、息をのんだチロちゃんが更に青ざめる。 この時の私には、二人がなにを言っているのかほとんどわかっていなかった。 ただ、チロちゃんがつらそうなことだけは間違いがなくて。 「……ば、ちゃ……、だ、め……い、じめ、な……」 たどたどしい制止に、おばあちゃんが苦笑した。 「まったく。ほんとうに仕方のない子らだよ」 ふう、とため息をついて居住まいを正し――静かな所作でチロちゃんに頭を下げた。 生まれてはじめてみる光景に、目を見開く。 「この子に、主を持つだけの分別がつく時間をあげてほしい」 ――あるじをもつだけの? ああ、そっか。 いつだっておばあちゃんは毅然と、颯爽としていて、なのに、多分、いま私のためにその頭を垂れているのだ。 泣きたくなった。チロちゃんが大切。でもおばあちゃんも大切で、大事な人だから。 「……ずるいです、それは」 くしゃりと前髪をつかみ、チロちゃんがぽつりと呟いた。すまないね、とおばあちゃんが頭を上げる。 「……どれだけ、待てば」 「時が来れば、あなたとこの子は再びめぐり合う。けれどね、その時にはあなたのことをこの子は忘れているだろう」 「なん、で……っ」 「あらためて出会い、そして、まっさな状態から、もう一度、この子に主と認められたとき、すべては元に」 静かに紡がれる言葉は呪文のようだ。 風に吹かれた木の葉が、お互いにこすれ合いざわざわと鳴る。 人の気配がないのは、おばあちゃんが結界を張っているからだろう。 チロちゃんの手が、私の頬をそっと撫でた。そこにはどんな思いが込められていたんだろう。 ただ、確かな決意だけが感じられた。 「待ちます。でも次に会ったときには、もう絶対にこんな別れ方はしない。誰かの都合に振り回されるのは、もうたくさんだ」 はっきりと告げるチロちゃんに、おばあちゃんが少し意地の悪い笑みをつくる。 「この子を手に入れるために、その命をかけることになるとしても?」 「命?」 「魔女の主になるにはね、あなた自身も主の資質を示さねばならない。これもまた、魔女の決まりごとなのさ」 ――資質なしと判断されれば、命を失うこともある。 冷たい一言に、けれどチロちゃんは一度たりとおばあちゃんから視線をそらすことなく、うなずいた。 「かまいません」 ふーっと長い長いため息のあと、おばあちゃんは指先でさっと空中に円を描いた。 湧き出た黒い靄の中から、しなやかな体躯をくねらせ黒猫がすべりでる。 「このブロッシュがあなたの資質を見極める選定者となる。よく覚えておくといい。さて、ブロッシュ、あんたは……まあ、あんまりほだされるんじゃないよ」 ビロードの毛並みをおばあちゃんが苦笑しつつ撫でると、ブロッシュが実に不満そうに一声鳴いた。 「そう怒るものじゃあない。ああ、やれやれ、まったく、本当に困った子らだ。まあ私も困った婆だがねぇ。この子が自分で選択したことには、できる限り干渉せずにいたかったんだが。やっぱり孫は可愛い」 楽しくてたまらないというようにふふふと笑い声を立てるおばあちゃんは、満面の笑みを浮かべていた。 「チロちゃ……」 「ゆうな、必ずまた会えるから。会いに来るから。だから」 待っていて――。囁きと共に額がふんわりと温かくなる。軽い、軽い触れるだけのキスは、儀式のようだった。 「チロちゃ、ん」 いまはこれでおわかれなんだ。 瞬きするたびに、閉じそうになる瞼の縁からぽろぽろと涙が零れ落ちる。 「さあ、お前は少しお眠り」 「……まって……まっておばあちゃ」 後悔と諦めと、希望。すべてを混ぜ合わせて私を見下ろすチロちゃんに、ポケットから取り出したテディベア――くまきっちんを差し出す。 ――まもって……! わたしがもういちどチロちゃんにあえるときまで、チロちゃんを、まもって……っ! 残るありったけの力を振り絞って、まじないを、祈りを注ぎ込む。 「つぎは、きっと、わたしが、チロちゃん、を……っ」 ――まもる。まもる、から。 最後まで言えたのかはわからなかった。けれど、あらん限りの声で叫び、そこで私の意識はふつりと途切れた。 |
| Back ‖ Next 魔女のルール INDEX |
TOP ‖ NOVEL |
|
Copyright (C) 2014 kuno_san2000 All rights reserved. |